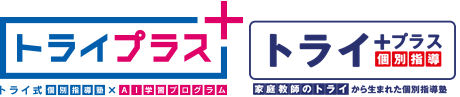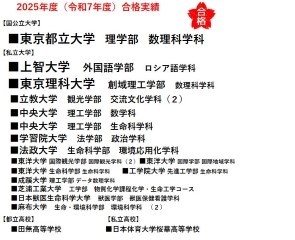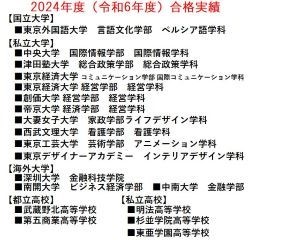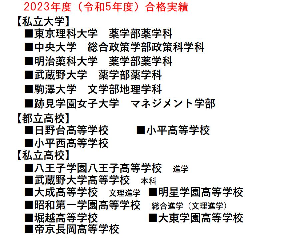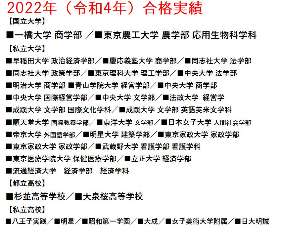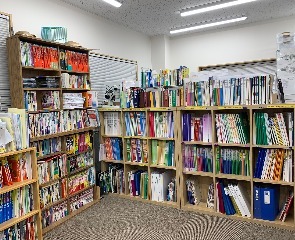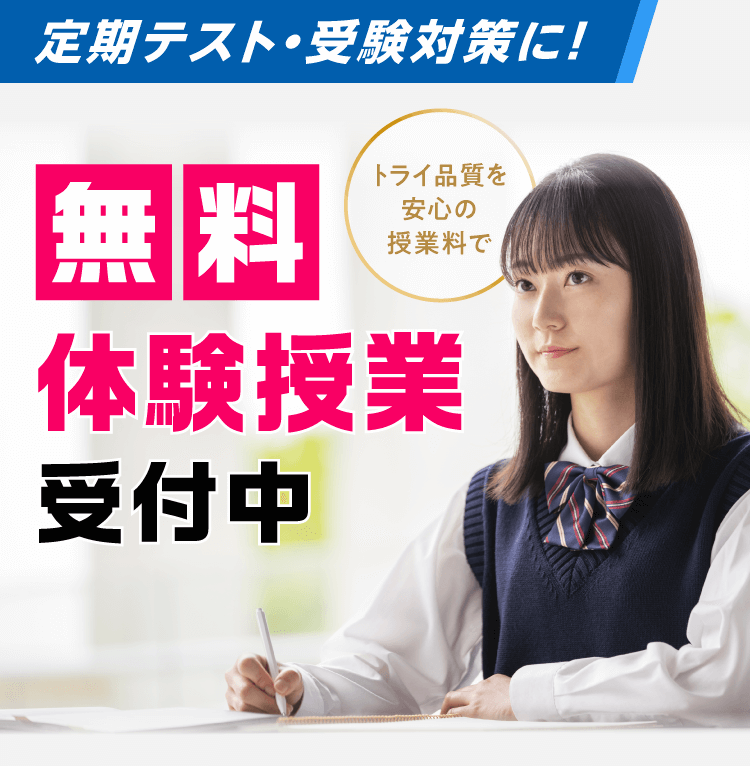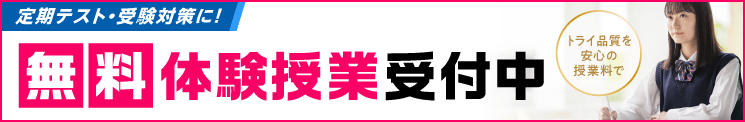東京都国分寺市 国分寺駅北口校
の教室情報
国分寺駅北口校
へのアクセス
通塾エリア
国分寺市
本町、本多、南町、東恋ヶ窪、泉町、東元町、西元町、西恋ヶ窪、東戸倉、戸倉、日吉町、北町
小金井市
貫井北町、貫井南町
小平市
上水南町、上水本町、喜平町、上水新町、回田町、鈴木町、学園西町、学園東町、小川西町、小川東町、津田町、仲町、小川町、たかの台
府中市
武蔵台、栄町、晴見町、新町
【利用可能バス】
ぶんバス・本多ルートの本町二丁目西停留所から徒歩10秒
銀河鉄道バス・国分寺駅北口停留所から徒歩30秒
国分寺駅北口校
の教室長からのメッセージ
通塾生の
在籍校・進学先
対応校を表示しています。
*公立、私立の順・五十音順
【小学生】
(公立)
小金井第四小学校
国分寺市立第一小学校
国分寺市立第三小学校
国分寺市立第四小学校
国分寺市立第七小学校
国分寺市立第九小学校
小平市立小平第三小学校
(私立)
国立学園小学校
明星小学校
早稲田実業学校初等部
【中学生】
(公立)
小金井市立第一中学校
小金井市立南中学校
国分寺市立第一中学校
国分寺市立第二中学校
国分寺市立第四中学校
小平市立小平第一中学校
小平市立小平第二中学校
小平市立小平第四中学校
小平市立上水中学校
東京都立武蔵高等学校附属中
(私立)
学習院中等科
吉祥女子中学校
國學院大學久我山中学校
白梅学園清修中高一貫部(中学)
西武文理中学校
創価中学校
日本大学第二中学校
明治学院中学校
明星中学校
早稲田実業学校中等部
【高校生】
(都立)
国立高等学校
小金井北高等学校
国分寺高等学校
小平高等学校
小平南高等学校
昭和高等学校
杉並高等学校
立川高等学校
田無高等学校
多摩科学技術高等学校
東京都立立川国際中等教育学校
東久留米総合高等学校
東大和高等学校
東大和南高等学校
日野台高等学校
府中高等学校
武蔵高等学校
(私立)
学習院高等科
錦城高等学校
啓明学園高等学校
晃華学園高等学校
国学院久我山高等学校
駒場東邦高等学校
聖徳学園高等学校
白梅学園高等学校
白梅学園清修中高一貫部(高校)
杉並学院高等学校
拓殖大学第一高等学校
中央大学附属高等学校
東亜学園高等学校
東海大学菅生高等学校
八王子学園八王子高等学校
法政大学高等学校
北海道芸術高等学校
明治学院東村山高等学校
明星高等学校
明法高等学校
早稲田実業学校高等部
【高卒生】
大学受験対応可能
合格実績(複数合格は⦅⦆書き)
2025(令7)
【国公立大】東京都立・理学部・数理科学科
【私立大学】
上智・外国語・ロシア語
東京理科・創域理工・数理科学
立教・観光・交流文化 (2)
学習院・法・政治
法政・生命科学・環境応用化学
東洋・国際観光・国際観光 (2)
東洋・国際・国際地域
東洋・生命科学・生命科学
工学院・先進工学・生命科学
成蹊・理工・データ数理
芝浦工業・工・物質化学課程化学・生命工学コース
日本獣医生命科学・獣医・獣医保健看護
麻布・生命・環境科学・環境科学 (2)
【都立高校】田無
【私立高校】日体大桜華
2024
【国公立大】東京外国語・言語文化・ペルシア語
【私大等】中央・国際情報/津田塾・総合政策/東京経済・コミュ・国際コミュ/
東京経済・経営/創価・経営/帝京・経済/大妻女子・家政・ライフデザイン/
西武文理・看護/東京工芸・芸術・アニメーション/東京デザイナーアカデミー
【海外大学】深圳大・金融科技/南開大・ビジネス経済/中南大・金融
【都立高】武蔵野北/
第五商業
【私立高】明法/杉並学院/東亜学園
2023
【私大】東京理科・薬/
明治薬科・薬/武蔵野・薬/中央・総合政策/
駒澤・文/跡見学園女子・マネジメント
【都立高】日野台/小平/小平西
【私立高】八王子学園八王子/武蔵野大学高/大成・文理進学/明星学園
昭和第一学園/堀越/大東学園/帝京長岡
2022
【国公大】一橋・商 /東京農工・農・応用生物科学
【私大】早稲田・政経・経/慶応義塾・商/
同志社・法・法律/同志社・政策
東京理科・理工応用生物/中央・法・政治/明治・商/中央・商・国際マーケ
中央・国際経営/青山学院・経営マーケ/中央・文
法政/成蹊⦅2⦆/順天堂/日本女子/
東洋/武蔵野/帝京/明星/東京家政/
東京医療学院/立正/流通経済
【都立高】杉並/大泉桜
【私立高】明星/女子美術大付属/日大明誠/昭和第一学園/八王子実践/大成
2021
【大学校】防衛大
【私大】成蹊/東京女子/日本⦅2⦆/明星/東京農業⦅2⦆
東京経済/拓殖/帝京/東京国際/帝京平成
【都立高】立川
/小平西/東大和/府中/府中西/東村山西
【私立高】錦城・特進/八王子実践/昭和第一学園⦅2⦆/
白梅学園⦅2⦆/東海大菅生/日体大桜華/聖パウロ/北海道芸術
2020
【国立大】北海道・総合教育部
【私大】 東京理科⦅2⦆/
立教/
明治/
法政/
日本女子/大妻女子
国分寺駅北口校
の講師紹介
国分寺駅北口校
のコース紹介
人気コースランキング
| 小学生 | 私立中学、都立中高一貫校受験対策(難関校も可能) | 英検対策、数学・算数検定対策 | 学校授業の補習 |
|---|---|---|---|
| 中学生 | 都立高校入試対策 志望校合格への得点力を養います | 定期テスト対策 近隣公立中、通学圏私立中すべて対応 | 英検・数検対策 2級・準2級を目標に |
| 高校生 | 大学受験対策 国公立私立難関校対策も可能 | 小論文対策 指定校推薦、総合型選抜、内申点UP対策 | 英検対策 準1級、2級、準2級プラス |
その他人気コース
| 小学生 | ★重点対策強化校 国分寺1小、3小、4小、7小、 早稲田実業学校初等部、明星小
|
|---|---|
| 中学生 | ★重点対策強化校
|
| 高校生 | 高校1年生の出だしから成績が振るわないとそのあとの学習にマイナスの影響を与えます。スタートでつまづかないことが高校3年間を成功させる重要なポイントです。そのためにも「苦手科目の個別指導」を受講して、理解不足の単元を早く克服し、「予習タイプの勉強」に変えていきましょう。 |
国分寺駅北口校
からのお知らせ
-
2026.01.27
都立入試・社会を解く(令和7年度)㊱
5⃣の[問3]、難しかったですね。教科書で言うと、「日本銀行と金融政策」、「財政政策」の箇所で学びます。そこに分かりやすく説明してあります。景気が悪いとき、景気が良いとき、日銀と政府はどういうことをするのかを勉強しておけばよいです。 こんな風に図式化して覚えておきましょう。 政府 【公共事業】を増やす➡働く人の所得が増える➡景気回復 政府 【税金】を減らす➡手取りの現金が増える➡景気回復 日銀 【国債】を買う(代金を支払う)➡世の中に出回るお金が増える(金融機関は余裕ができる)➡金利を下げる➡消費や設備投資が活発になる➡景気回復 これは、景気が悪くなったときに財政政策、金融政策です。良くなったときはこれと反対のことをします。 難しいとは思いますが、教科書の文章と図式化したものがありますから、ゆっくり丁寧に覚えてみましょう。 ちなみにですが、令和8年度入試は、同じような単元の出題はないように思いますから、現在、中学3年生は、思い切ってこの単元を捨ててみることもありでしょうかね。これもヤマ張りのひとつですね。出そうにないものは削る、ということも。 -
2026.01.26
都立入試・社会を解く(令和7年度)㉟
5⃣の[問3]、前掲からの続きです。説明の正しい組み合わせ(A~Dから2つ正しいものを選ぶ)の問題なので、A~Dの選択肢をそのまま示しておきます。 A 政府は、公共事業への支出(公共投資)を増やしたり、減税をしたりする。 B " を減らしたり、増税したりする C 日本銀行は、国債などを銀行から買う公開市場操作を行う。 D ” を銀行に売る公開市場操作を行う。 政府による財政政策は、日銀による金融政策は、どういうことをするのかを問う問題なのです。 いやあ、この問題、最初の長ったらしい、設問文を読んだほうが良さそうです。すでに最初の文を読み、何をどうこたえるのかは把握できています。では、その前は。2001年の経済状況のようなとき、政府と日銀の金融政策は、と書いてあります。この分の前に、I, IIの資料から、とありますから、資料を見なくてはなりませんね。Iは、経済成長率の変化のグラフです。2001年は前年からガクンと下がっています。景気が悪くなったのだな、ということですね。もう解けそうです。 正答率は41.1%と低いですね。難しいように思います。 -
2026.01.25
都立入試・社会を解く(令和7年度)㉞
5⃣の[問2]を解いています。 選択肢ア~エのキーワードを示します。 ア 育児休業や介護休暇 イ 労働組合を組織することを定める ウ 労働条件の最低基準について定める エ 機会や待遇などの男女平等の確保、妊娠・出産後の健康確保 正答率も73.4%と高く、簡単に正解できたように思います。 [問3]この設問文はとても長いです。嫌になってきます。8行もあります。最後の文をさきに読むと「正しく組み合わせているのは、表のア~エはどれか、とあります。 表を見ますと、 ア A C イ A D ウ B C エ B D これだけ見ても、消去法で2つ消せます。つまり、Aが正しいか、Bが正しいかで、2つ消去でき、あとは、CとDのどちらが正しいか選ぶだけです。もしかして、消去の仕方は、CかDのどちらが正しいかを先に決めるのかもしれません。では、A~Bにどんなことが書いてあるのか示してみます。 次に続きます。 -
2026.01.24
都立入試・社会を解く(令和7年度)㉝
5⃣は公民の問題。 ここでも前段の長ったらしい文章、9行もあり、ところどころに下線が引いてあり、(1),(2),(3),(4)の番号がつけられています。4⃣と同じで読まなくてよいです。(1)~(4)が、そのまま[問1]~[問4]に連動していますが、読まなくても問題は解けます。読まないことによる”ひっかけ”はありませんし。 [問1]社会権を規定した憲法の条文は、という問題です。ア~エの選択肢から選びます。 正答率が49.2%と低かったです。基本的人権の分類は、難しいように思います。教科書には、これを表にして区分していますから、説明されている文をよく読んで、表とセットで覚えておくようにしなくてはなりませんね。教科書の説明文を読むことで、そんなに難しくはなくなるはずです。 [問2]最初に文章があります。その文章に述べられている法律にあてはまるのはア~エのどれ、という問題です。文章のキーワードは、1日8時間、週40時間の労働時間は超えてはならない、毎週少なくとも1回の休日をあたえる、男女同一賃金の原則、これが1番目の文章。2番目の文章は、2018年に改正、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定。 -
2026.01.23
都立入試・社会を解く(令和7年度)㉜
4⃣の[問4]の解き方解説をします。くどいですが、設問文の下線部(4)は読まなくてよいです。問題を解くうえで全く関係ない、役にたたないので。 これも毎年のように出る形式です。年表があり出来事が9つ書いてあります。右端にA, B, C, Dと西暦で4つに区切っています。その下に、ア、イ、ウ、エの文章があります。ア~エは年表で区切ったA~Dのどの時期にあてはまるか、という問題。これも地理でも多かった、結び付けの問題です。4つすべて間違えなく結び付けないと5点もらえません。 どのように区切っているかを示します。 A 1926~1943 B 1943~1959 C 1959~1975 D 1975~1995 ア~エのその時代の様子を述べた文章のキーワードを示します。 ア 急激な円高が始まる、地価や株価が上がり続ける イ 政府が議会承認なしに資源や労働力を動員できるようにする法を制定 ウ 経済の民主化が図られ、主権を回復する中で エ 太陽の塔をシンボルゾーンに据える博覧会が開催 どうでしょうか?この問題は正答率が36.1%とかなり低めでした。暗記した出来事の内容を理解している生徒には簡単なのでしょうが。 -
2026.01.22
都立入試・社会を解く(令和7年度)㉛
4⃣の[問3]、記述問題です。毎年どこかに記述の問題が入りますが、今回は、3⃣、4⃣、5⃣に記述問題が入っています。3つは多いほうです。が、今後は、ずっとこれが続くように思います。3⃣の[問3}の解説で述べましたように、空欄とはせず、何らか書くことで、最低でも部分点を得るようにしましょう。記述問題は、与えられた資料からの情報を使うだけで、社会の知識はほとんど関係ないです。今回の問題を見て見ますと、設問の指示は、「日本から出品された絵画の出品数の変化について、簡単に述べよ。」です。資料の出来事と数字を素直に読み取って表現すればよいだけです。模範解答を見ますと、83字です。「1900年は、浮世絵がなくなり、日本画と西洋画だけの出展となった。」まずは、これだけで5点中の部分点で1点はもらえるように思います。 ★ポイント: 記述問題は、簡単!与えられた資料から読み取れる情報を並べるだけ。その際、時代前後での変化を書けという指示に従うことです。 -
2026.01.21
都立入試・社会を解く(令和7年度)㉚
4⃣の[問2]、前文の文章を読む必要がない、これを確認しましょう。 「美術品は、価値が高まるとともに、作り手の経済的基盤や作風が変化してきた。」と、下線(2)が引かれています。これに対して、問いは、ア~エの文章が並べてあり、それを古いものから順に並びならびかえる問題です。ア~エの文章中のキーワードだけ抜粋して示します。 ア 菱川師宣 「見返り美人」 イ 狩野内膳 豊臣家の絵師 「南蛮屏風」 ウ 喜多川歌麿 「ポッピンを吹く女」 エ 雪舟 「破墨山水図」 どうでしょう、文章を読む必要はありますか? [問2]の問題について見ておきましょう。正答率は45%と低めでした。アとウの時期の違いが理解出来ていないことでの誤りが多かったようです。確かにそうですね。しっかり覚えるには、どうしたらよいのでしょうか。 アとウは、江戸時代の文化で学びますが、大きくは前期・後期で、元禄文化・化政文化と呼ばれています。それぞれ比較できるように表に並べてみてはどうでしょう。 -
2026.01.20
都立入試・社会を解く(令和7年度)㉙
4⃣、歴史の問題の解き方解説です。前掲、長ったらしい前置きの文章は読まなくてよい、と書きました。何が描いてあるか、見てみますか。[問1]の対象となる下線(1)の文、「権力者は、国際的な影響を受け、建築物を造営した。」、この文です。[問1]が求めることは、ア.円覚寺、イ. 飛鳥寺、ウ. 厳島神社、これらが造営されたのを年代順に並べ、さらに、略地図上に、これらの建築物のある場所A, B, Cが示されており、そのうちのAは、ア~ウのどの時代のものか、というものです。どうでしょうか、前置きの文章を読む意味は全くありません。無視しましょう。いやいやと私の言うことを疑う生徒がいるかもしれません。もしかして、「前文からしっかり読むように」と指導している塾や学校の先生がいるならば、優れた授業をしていると認めがたいところです。[問2}でも、読まなくてよいことを確認しておきます。次の掲載に続きます。 -
2026.01.19
都立入試・社会を解く(令和7年度)㉘
4⃣は歴史です。問1~問4で合計20点の配点。毎年、同じスタイルでの出題と思ってよいでしょう。ただし、年度によって、記述式の問題が入る場合があります。今回もそうです。前年もそうでしたから、今後も記述式の問題が1つ入ると考えていた方がよさそうです。1つです。2つ出すことは、おそらくないはずです。4⃣のなかだけの話です。 同じスタイル、というのは、最初に長ったらしい文章が示されます。その文章の4か所に下線が引かれてあり、それについての質問が[問1]から[問4]と順番に続きます。それについての質問、と申しましたが、解くにあたっては、読まずとも全く問題ないと考えてよいでしょう。もう一つの特徴は、[問1]から[問4]は、年代順どおりに出題されることです。[問1]が江戸時代で、[問2]が平安時代、といった順番で出ることはありません。これは、問題にも[問1]では、「飛鳥時代から鎌倉時代にかけて」と書かれてあるので、どの時代の知識が必要なのかはすぐにわかります。[問2]「室町時代から江戸時代」[問3]「江戸時代末期から明治時代」[問4]「大正から平成」、こんな具合です。 -
2026.01.18
都立入試・社会を解く(令和7年度)㉗
3⃣の[問3]の解き方解説をしています。 最初に地図を眺めてみました。そして、茨城県ひたちなか市と設問の冒頭に書いてあることを前掲で書きました。場所がどこであるのかを考える必要は全くない問題ですからね。私が余計なことを書いてしまいました。[問3]の最大の特徴は記述式であるということ。何を書かせるよう求めているか、情報から読み取れることを書かせるだけです。具体的には、「交通の利便性の変化について」述べよ、との問題です。条件として、「~する前と比較し、移動手段に着目して」とあります。そして、「簡単に述べよ。」と。I,II,IIIの資料から読み取れる情報です。その前に、最初の設問文7行もあるのですが、どんなことを書くのかを書いてあるので、これもしっかり読んで解く必要があります。「鉄道が新しくできるので、観光地Bに行くのにとても利便性が高くなる。」たったこれだけでも5点中3点はもらえるのでは。部分点は高校ごとに設定が異なります。まあ、こんなことは気にせずともよいです。 -
2026.01.17
都立入試・社会を解く(令和7年度)㉖
3⃣の[問3]の解き方解説をします。 Iに略図があります。簡単なイラスト地図です。鉄道の路線が描いてあります。そして、観光地Aと観光地Bと描いてあります。観光地の近くには、本線と思われる鉄道の駅から支線のように延びている線路の駅が、それぞれあります。太平洋と描いてあるので、それに面している場所です。駅の一つに「那珂湊駅」がありました。鉄道好きの中学生にはすぐにどこか分かるのでは。あ、です。設問文が、7行もあり、「長ったらしいなあ、いやだな。」と私は思いましたが、1行目に、「茨城県ひたちなか市」と書いてありました。[問3]の大きな特徴は、記述式での説明が求められることです。必ず「簡単に述べよ。」との指定です。模範解答は76字です。正答率を見ると、65.8%です。高めです。何か書けば必ず部分点も含め、点数がもらえる、という、問題なのです。記述式だから敬遠するのではなく、必ず書くように、模試や過去問を解くときには、トレーニングすべきです。うまく書けないから、という気持ちは払拭してください。 -
2026.01.16
都立入試・社会を解く(令和7年度)㉕
3⃣の[問2]のIIIの記述文を読みます。 社会のこうした記述文は3⃣のみならず、随所に出てきますが、共通して言えることは、キーワードを探すだけで、じっくり読まないことです。最初の文章の2行目に「さくらんぼの収穫量は全国1位」、これで県が指定できます。日本の都道府県は、小学生ですべて覚えておくことですから、覚えていない人は、これまできちんとやっておかなかったことを反省すべきで、すぐに覚えましょう。たった47個しかないのです。やる気だけの問題です。2つ目の記述文を見ると(じっくり読まなくてよいので、見る、で良いのです。)、「5億円を超えている」とあります。そこで、IとIIの表に行けばよいのです。金額はIの表です。アとイしかありません。次に果実の収穫量を見ます。アかイに限定できたので、ウ、エは見なくてもよいのですが、アは、ぶどうの数値がずばぬけて高いです。イはりんごがずばぬけて高いです。これで「さくらんぼ1位の県」の数値がアかイかを特定できそうです。正答率は45.0%と低めでした。ぶどう、りんごの数値の見極めで間違えた生徒が多かったのではないかと思います。 -
2026.01.15
都立入試・社会を解く(令和7年度)㉔
3⃣の[問2]は、地図上のW, X, Y, Zの県を対象にします。まず、IとIIに数値の表がしめされています。それぞれ、ア、イ、ウ、エの欄に分かれています。これもW~Zとア~エの結びつけの問題です。ただし、うれしいことに、IIIに文章が示されてあり、その記述が表している県はどれかを当てる問題です。ただし、さらに、その県がア~エのどれにあたるかを選ばなくてはなりません。県名と数値の表の両方を当てなくては得点できません。 I 観光農園年間売上金額と観光農園数 II 果実収穫量 みかん、りんご、日本なし、ぶどう この数値を見るのは、私はとても嫌です。金額を見ても、t数を見ても、全くピントきません。たぶんほとんどの人がそうかと思います。「りんご 41500t」とかありますが、想像がつきますか?最近では備蓄米〇〇tとかニュースで毎日聞かされたことがありましたが、どうだったでしょうか?まずは、IIIの記述文を読んで、どの県かを限定させるのが解き方です。表の数値は、あとで、特徴的な数値を発見するだけでよいです。 -
2026.01.14
都立入試・社会を解く(令和7年度)㉓
3⃣の[問1]のア~エの記述文を読んでいます。キーワードを探すことです。 アは、最初の自然環境の記述だけで正解できますが、次の国立公園の記述でも正解を確証できます。「火山活動により形成された湖」、の記述です。 イ 「南部は黒潮の影響」、もうこれで一発です。あとは読まなくてよいです。国立公園の記述には、リアス式海岸のことが書いてありますし、間違いなし。 ウ 国立公園の記述に「世界最大級のカルデラ」、これで一発です。 もう、エは読む必要はないわけですね。念のため読むと、「水不足に備えてつくられたため池」、もうこれで間違いなしと確信できるはず。 [問1]はかなり易しい問題のはずです。あれ、正答率54.4%と高くはないですね。きっと間違えた生徒は、記述の文章をじっくり読みすぎているか、もともと地理の基礎知識をしっかり身につけようとしてこなかっただけかと思います。 -
2026.01.13
都立入試・社会を解く(令和7年度)㉒
3⃣は日本地理です。まずは、最初に地図を眺めましょう。 A, B, C, DとW, X, Y, Zと8つの県が示してあります。2⃣の世界地理もそうですが、A, B, C, Dのまとまり、W, X, Y, Zのまとまり毎に設問が作られています。年度によりますが、P, Q, R, Sも入り、3つのまとまりの場合もあります。今回は2つのまとまりです。 [問1]の対象は、A~Dの県です。これに対し、ア、イ、ウ、エに、その県についての記述があります。もうわかりますね。2⃣の正解地理でもあったように、A~Dが、ア~エのどの記述にあてはまるか、を問う問題です。結び付けの問題です。今回の記述は、「自然環境と国立公園の景観」についてです。記述は、それなりに長いので、キーワードだけ探すつもりで早くさらりと読んだほうがよいでしょう。時間が足りなくなりますので。 ア これは瞬時にどの県かわかりそうです。「山脈が南北に」、「冬期には山脈の西側では降雪量が」とあります。中央に山脈が走っているのはア~エでは、ひとつしかありません。Cに示した県、雪などほとんど降らないですし。 -
2026.01.12
都立入試・社会を解く(令和7年度)㉑
2⃣の世界地理を解説してきました。都立受験をする生徒さんが期待する、令和8年度はどこが出題されるか、[問2],[問3]とも、自動車工業、工業に関する問題でした。よって、次は、農業、漁業にヤマを張るのもよいかもしれません。鉱業もありましたね。商業なども。自然環境に関する問題かもしれませんし。要は、工業関連は出ない、というだけで、勉強を進めるのには役立つかもしれません。[問1]の雨温図はどうでしょうかね?今回は、熱帯気候のサバナ気候で、インドのコルカタが正解でした。雨温図で多く出題されると思われるのが、温帯です。ヨーロッパあたりで、西岸海洋性気候か地中海性気候など出るのではないでしょうか。 社会のヤマ張り用に過去問から出題された国、都市、地域など、過去7年分くらい表にまとめたりしたことがありました。2023, 2024, 2025年分をサボっていましたから、これからまとめようと思います。塾生にはこれを使って私が教えることもあります。塾生でなくとも、解き方解説はできますから、塾に来ていただければ、教えますよ。 -
2026.01.11
都立入試・社会を解く(令和7年度)⑳
2⃣の[問3]の解き方解説をしています。 結局、I,IIの地図は全く見ずとも、IIIの文章だけ読んで、正解は得られると理解できたかと思います。都立入試の社会においては、すべての情報を読み取らずとも解けるような作問をしているように思います。読まなくてよい情報の方がかなり多いと感じます。 前掲に⓵~⑦のポイントを書き出しましたので、一発で正解にたどりつけない生徒もいるでしょうから、細かくみてゆきましょう。 ⑥と⑦に数値がありますね。⑥の数値からスペインは消去できます。⑦の数値からドイツ(スペインも)が消去できます。答はイギリスかフランスのどちらかに限定できます。ここから、⑥に首都は北部にある、とあるので、簡単にどちらかが分かるはずです。 私の場合ですが、すぐに正解できたのは、似たような記述が教科書にあることを覚えていたからです。令和7年1月20日発行の帝国書院の教科書のP.74です。教科書を繰り返し読み込んでおくことが重要なのがよく理解してもらえるように思います。 -
2026.01.10
都立入試・社会を解く(令和7年度)⑲
2⃣の[問3]の解き方解説をしています。 2つの地図を眺めました。次です、大事なのが。IIIの文章です。設問の指示は、ずばり、IIIの文章はどの国をのべているか、選択肢から選べ、というものです。選択肢は、イギリス、ドイツ、フランス、スペインです。 IIIの文章は5行あります。文は3つです。 以下にポイントを抜き出します。 ⓵北東部で産出された鉄鉱石 ②これを利用し近代工業が発達 ③現在、航空機産業でヨーロッパの中心 ④南西部の都市に本社を置く、航空機メーカー ⑤その工場で、各国製造の部品が集められ、最終組み立て ⑥2019年、北部にある首都などに、429社の日系現地法人 ⑦日本への輸出額は、約4763億 この中のどれか一つだけでも分かれば、正解できます。私の場合は、「航空機メーカー」ですぐに分かりました。さらに念押しとして、「北部にある首都」で、間違いなしと確信できました。ドイツの首都も北部と言えば北部なのかもしれませんが。 -
2026.01.09
都立入試・社会を解く(令和7年度)⑱
2⃣の[問3]の解き方解説です。 どの問題も共通で、まず、示された地図を見ます。その前に、出題形式をお話しておくと、都立入試の2⃣は、最初に提示された地図だけで完結するもの、今回のように[問3]で別の地図を示すものの2通りがあります。過去問を5年以上解いておけば、その違いが把握できると思います。[問3]で使われる地図は、IとIIの2種類です。具体的に今回の出題でお話するのが分かりやすいでしょう。 I ヨーロッパ州の国々の2019年における日系現地法人数を示したもの II ヨーロッパ州の国々の2019年における日本への機械類及び輸送用機器の輸出額を示したもの。 といことで、地図は同じものを左右に並べて、数値毎に模様を変えて示してあります。例えば、Iの地図ならば、400社以上はグレイ塗り、50社未満は、色塗り、模様なし、といった具合に。 地図を見てもさっぱり分からないでしょう。日系企業が多く、かつ輸出額が多いのは、ドイツ、イギリス、フランスでしょうか。車の輸出が数値に影響してそうです。よって、イタリア、スウェーデンも輸出額は高いです。オランダ、スイスも高いです。こんなことを読み取る必要はありません。 -
2026.01.08
都立入試・社会を解く(令和7年度)⑰
2⃣の[問2]の解き方解説をしています。 問題を解くための核となる「自動車工業などの様子」の記述を再チェックしてみます。自動車工業のさかんな都市、地域はどこか、また、どこに輸出されているか、が共通した記述となっています。ここで、輸出に注目してください。輸出するとき、輸入するとき、最も最初にくる共通事項というものがあるように思います。過去問を多く解いてみても、強く感じます。それは、輸出入は、隣国、近隣国ほど取り扱い量は多い、ということです。なぜか。輸送費が比べると安上がりだからです。アからエの記述には、「アジア諸国」、「ヨーロッパの国々」、「同じ大陸内の国々」、「隣国を中心に」輸出されているとあります。地図と見比べれば、「輸出入は近いところほど多い」の原則どおりにどんぴしゃ解けると思います。これって、学校の授業では教えているでしょうか?当たり前すぎて教えていないかもしれません。当然、例外もあるでしょうから。ダイアモンドなど、きっと例外なのかと思います。 -
2026.01.07
都立入試・社会を解く(令和7年度)⑯
2⃣の[問2]ですが、データは使用せずともよい、と申し上げました。もちろん使用しても問題ないですが。 このようなデータを学校の授業で習うことはありません。そして、このようなデータを探して覚えておくことが必要でしょうか?データは毎年少しずつですが変化してきますし。そこでですが、教科書にその国の人の車の保有台数が出ているか、探してみたいと思います。令和7年1月20日発行の帝国書院の地理の教科書を使います。 P.5 「地図帳の統計資料の使い方」があります。地図帳にある統計資料を見てみます。「おもな輸出品」の欄に「自動車」が載っている国が少なからずあります。が、保有台数のデータはありません。 P.53 「世界の電気自動車保有台数の変化」のグラフがありました。環境問題に関連した情報として載っています。中国、ヨーロッパ、合衆国、日本の順位で載っていますが、他はその他、です。[問2]のデータには全く役立ちませんね。 P.57 「タイに進出した日本の自動車メーカーの組み立て工場(バンコク近郊)」の写真が載っています。保有台数の情報とは関係ありません。 -
2026.01.06
都立入試・社会を解く(令和7年度)⑮
2⃣の[問2]の解き方解説。少し発展させて、問題の中に出てくるデータは、教科書から学べるのか、を確認する作業をしています。北アメリカ州の前までのP. 91まで、自動車に関する情報はちらほらでてきました。P.57以降もわずかにちらほらと。[問2]のデータとは全く関係ありません。 お、ありましたよ。P.102 「主な国の100人あたりの自動車保有台数」で、棒グラフが載っています。1位合衆国で88.1です。[問2]のデータは千人あたりで、860.4です。2位以下、カナダ、ドイツ、日本、メキシコ、中国まで載っています。[問2]の対象国は、合衆国を除けば、どこの国も出ていません。こんなデータを覚えておいても役に立ちそうにないですね。教科書では、合衆国では「モータリゼーション」が世界で最初に始まった、という説明がありますが、これを覚えておくべきですね。関連事項としてデータが示されているのですね。 もう[問2]に関する情報は探すのは終わりにしますね。 -
2026.01.05
都立入試・社会を解く(令和7年度)⑭
2⃣の[問2]の解き方解説をしています。 前掲で、私は自動車の台数のデータを最初に使用してみました。このデータですが、過去問においては、全く見ずとも解ける問題も多かったよう思います。必要ないと思えば使わなくともよいでしょう。では、記述を読んでゆきましょう。真面目に読まずに、キーワード、それに類似する表現を探すだけでよいと思います。 ア 「生産された自動車は、輸出入に対する関税が原則として撤廃されているアジア諸国を中心に輸出」とこれは長いですが。「アジア諸国」がキーワードとしてもよいかもしれません。 イ 「海峡に面した北部の都市に集中」、「ヨーロッパの国々」 ウ 「国内で産出される鉄鉱石」、「同じ大陸内の国々」 エ ここの記述は注意が必要でしょう。これは、2025年度2月の入試です。「トランプ関税」、一時毎日のように報道されていましたね。ここの後半の記述は、今では間違ったものとなっていますね。 国と記述が結びつくでしょうか。 実は、大人にとっては、社会科はとても簡単なのです。なぜなら、長く生きているから。それだけです。中学生は比べれば長く生きていない分、情報量が少ないからそれなりに難しいのです。 -
2026.01.04
都立入試・社会を解く(令和7年度)⑬
2⃣の[問2]の解き方解説をしています。 P, Q, R, Sの国名が言えるでしょうか?すべて言えるくらいであれば、問題も簡単に思えたりするものです。 P 南アメリカ大陸にあり、40%くらいの面積を占めているように見えます。この地図は面積を正しく表す地図ではありませんから、50%以上は占めているかもしれません。 Q 北アメリカ大陸にあり、これもかなりの面積を占めています。おもしろいのが、真ん中に国をはさんで、2箇所に分かれているところです。おそらく誰しもが知っている国のはずです。 R 赤道直下付近で東南アジアにあり、いくつもの島にまたがっています。東南アジアの国は、ごちゃごちゃしていてたくさんありますが、すべて覚えるように頑張ってみましょう。 S アフリカ大陸。海峡をはさんで、イベリア半島があります。国名が言えない受験生もいそうです。 こんな国の記述がどれかを選べばよいのだなと、理解して、詳しく見てゆきます。 私は、この問題に関しては、千人当たりの自動車保有台数のデータを最初に比べてみました。 ア 77.7 イ 112.3 ウ 214.5 エ 860.4 エが圧倒的に多いですね。すぐに国が特定できそうです。 -
2026.01.03
都立入試・社会を解く(令和7年度)⑫
2⃣の[問2]です。地図上に示された、P, Q, R, Sの国についての問題です。これらの国について、ア、イ、ウ、エでそれぞれの国についての記述があります。P, Q, R, Sとア、イ、ウ、エを結び付けるだけの問題です。注意点ですが、すべての結び付けが合っての完答ですから、4つすべて合っていないと0点です。 一致させる問題なので、[問1]ほどではないですが、長ったらしく、設問の指示の文があります。これも読まなくてもよいように思います。過去問や模試で、どういう指示の文であるのかを学習しておくだけで大丈夫かと思います。ア~エはどんな記述なのか、今回は、「自動車工業などの様子」とあります。その前に、P, Q, R, Sの国を眺めておくことが必要でした。国名が言えるくらいの力をつけておくことは必要かと思います。暇さえあれば地図を見る習慣がつけば言うことなしです。さて、ア~エの記述ですが、もう一つ、数値データの欄もあります。今回は、「千人あたりの自動車保有台数」です。それぞれの記述、3行もあって長いです。ここは私は、真面目に読む必要はないと考えています。キーワードを探すだけでよいと思います。 -
2026.01.02
都立入試・社会を解く(令和7年度)⑪
2⃣の[問1]の解き方解説をしています。東京の雨温図を頭に入れておくとよいかと思います。最新の帝国書院の教科書の雨温図の説明のページにも、東京の雨温図が出ていますね。年平均気温が15.8°、年降水量が1598mmです。雨の多い月、少ない月も見ておきましょう。月別の平均気温の最低値、最高値も見ておきましょう。データは、[理科年表2024]からのものです。都立入試の問題にも[理科年表]からと小さく書いてありますね。 ところで、10年後は雨温図の問題はどうなっているでしょうか。少し心配ではあります。地球の温暖化、気候変動など、近年変化が大きいように言われていますから。 それから、雨温図ですが、日本の各地の雨温図は都立入試には出ないと思ってよいでしょう。2⃣の[問1]の世界地理の問題に出るだけです。かと言って、3⃣の日本地理の問題などに、地域の気候や自然の様子を問う問題が出ることもありますから、日本地理の復習をするときには、必ず日本の地域の雨温図は見ておいたほうがよいとは思います。 -
2026.01.01
都立入試・社会を解く(令和7年度)⑩
2⃣の[問1]の解き方解説をしています。前掲にて、ピントきた生徒は鋭いなと感じます。 A, B, C, Dの都市の雨温図を、それぞれア、イ、ウ、エに結び付けてゆく問題なのです。ただそれだけです。そして、Iの文章がありますから、その文章がどの都市を述べたものかを選んでゆく問題なのです。[問1]はほぼ毎回同じ形式での出題ですから、前掲に述べた「長ったらしい」最初の設問文は過去問を解いて覚えておき、テスト本番で読まなくてよいのです。記号を結びつけよ、ということが書いてあるだけです。 さあ、雨温図を見てゆきます。雨温図で最初にみるべきは、気温の山や谷の形です。これでまずは、北半球か南半球かを見極められることが多いです。南半球の都市は一つしかないので、一発で分かります。ここで、Iの文章を見ると、どうも、その南半球の都市ではなさそうだと思います。「年間通して高温」、「雨季」はジュート(黄麻)の栽培に適している、などと書いてあるので。もう雨温図はどれかを特定できるように思います。雨温図を見るときには、私は、東京の雨温図を頭にいれておくことがよいと思います。問題を解くときのひとつの基準にはなると思います。 -
2026.01.01
令和8年も勉強を一緒にがんばりましょう
あけましておめでとうございます。 トライプラス国分寺駅北口校は、今年も元旦から開校しています。年末年始のお休みなし、3年前からそうしています。来年もその予定です。 本日授業を入れている生徒もいます。もちろん、2日、3日も。4日の日曜日も開校し、11日の日曜日も開校します。1月17日、18日の共通テストに備えるためです。試験間近の勉強も得点力アップにつながります。最後の最後まで、勉強時間をしっかり確保して本番に臨むことが大事かと思います。 トライプラス国分寺駅北口校は、受験生が志望校合格できるよう精一杯後押ししています。 -
2025.12.31
都立入試・社会を解く(令和7年度)⑨
2⃣は世界地理の問題。[問1]、[問2]、[問3]の3問。各点で、計15点の配点。 まず、最初に示されている地図を見ましょう。地図上の都市や地域にアルファベットが示されています。問題を解く前に覚えておきましょう。 A, B, C, D P, Q, R, S 今回の問題は、このグループで問題設定がされています。すわなち、[問1]がA, B, C, Dについて、[問2]がP, Q, R, Sについての問いとなります。年によっては、W, X, Y, Zが示されていることもあります。(むしろ、こちらのほうが多い。)これが[問3]となります。 [問1]を解いてゆきますが、問題文を読む前に、A~Dの都市を眺めましょう。ここで、都市名がずばり出てくるような生徒は、正答確率もかなり高いように思います。 Aはオーストラリア大陸の南端あたり、Bは中国の海岸部でおよそ中央あたり、Cはインドでバングラデシュ国境近く、Cはトルコの中央部。まだ問題文を読まないようにしたほうがよいです。[問1]には、最初に長ったらしい文章、Iに3行のその都市や地域の説明をした文章、そしてIIにア、イ、ウ、エの「雨温図」が出ています。 -
2025.12.31
今年も今日が最終日
大晦日ですね。令和7年も今日で終わり。 トライプラス国分寺駅北口校は、年末年始も休まず開校しています。受験生は1年振り返っている時間も余裕もきっとないでしょう。教室長の私は、受験生に対しては同じようなスタンスですが、非受験生に対しては、1月からの学習計画を見直す機会にしています。1年間はまことに長いものです。勉強するには、たっぷり時間が確保できるはずなのです。しかし、学力を上げてゆくとなると、計画的に勉強を進めてゆかなければ、現状維持というよりも成績は下がります。計画的に進めている人の成績がどんどん上がってゆくからです。 トライプラス国分寺駅北口校では、1月に翌年の受験までの計画や次学年での計画をしっかり点検できるよう、三者面談を実施するようにしています。来年すぐにやってくる入試はそわそわして落ち着かないのですが、来々年の入試には、生徒がどのくらい成績を上げていってくれるか、どんな合格実績を出してくれるか、期待が高まります。 -
2025.12.30
都立入試・社会を解く(令和7年度)⑧
1⃣の[問2]、令和8年度入試に出る問題を予想しようとしています。 世界遺産、しばらく出ていないですね。三内丸山遺跡、吉野ケ里遺跡なんかどうでしょうか。その場所を選ぶ問題。縄文時代、弥生時代ですね。ちょっと注意が。吉野ヶ里遺跡は世界遺産ではないです。ならば、山内丸山遺跡の場所を選ぶ問題が出ますかね? 明治時代が出ていませんね。「明治日本の産業革命遺産」、これは、岩手、静岡、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島のそれぞれにありますから、問題にするには難しいでしょうか。明治時代、大正時代、昭和時代、なにか出題される気配もあります。 -
2025.12.29
都立入試・社会を解く(令和7年度)⑦
1⃣の[問2]の歴史の問題、過去問のチェックをしてみます。 令和6年 戦国大名がキーワードになっています。 令和5年 千利休を選ぶ問題。桃山文化のところで学びます。 令和4年 世界遺産の場所を選ぶ問題で、「鑑真和上坐像が御影堂に納められ」がキーワードになります。 令和3年 これも世界遺産です。平安時代中期の貴族が建立とあり、「阿弥陀如来坐像を安置する阿弥陀堂」とあります。 令和2年 これも世界遺産。場所を選ぶ問題。「日本最大の面積を誇る前方後円墳」とあります。 平成31年 「東海道中膝栗毛」を著した人物を選ぶ問題。 平成30年 モヘンジョダロ、ハラッパ、のある古代文明の地を選ぶ問題。 平成29年 これも世界遺産、奥州藤原氏が建立、とあり、場所を選ぶ問題。 平成28年 2代藩主の徳川光圀、この藩の場所を選ぶ問題。 平成27年 この地での戦いから戊辰戦争と呼ばれる内戦が、と。その場所を選ぶ問題。 平成26年 ポルトガル人を乗せた中国の船がこの地に漂着、と。その場所を選ぶ問題。 平成25年 聖武天皇が建立した寺院、この場所を選ぶ問題。 これらから、令和8年度入試のヤマがはれるかどうか。皆さんはいかがでしょうか。 -
2025.12.28
都立入試・社会を解く(令和7年度)⑥
1⃣の[問3]は公民の問題です。これも一問一答方式のような問題で、基礎知識として知っているかどうかを確かめる問題です。「義務教育、公共事業や社会保障などの特定の仕事の費用を一部国が負担する依存財源の一つ」、これを何というか、という問題です。ア~エの選択肢から選ぶ問題。正答率が51.4%と少し低めでした。「地方交付税交付金」を選んでしまった誤答が多かったそうです。 1⃣は各3点で15点の配点です。しっかり得点を確保したいところです。[問1]は地図の読み取りですから、これも過去問などでよく練習しておくべきでしょう。[問2]、[問3]は、過去7年分くらいの問題を見て、どのあたりが出るのか、予想してみるのも面白いかもしれません。令和7年度に出た問題が繰り返し出ることはないはずです。[問2]は、鎌倉時代末期、[問3]は地方財政、この範囲は令和8年度入試には出ないと思われます。 -
2025.12.27
都立入試・社会を解く(令和7年度)⑤
1⃣の[問2]は歴史で、キーワードから簡単に解けることを説明しました。ただし、それは、教科書をしっかり読んでおき、知識として定着していることが前提です。キーワードとして、「幕府」を上げましたが、「御家人」もキーワードとはなるでしょう。「幕府」だけでも解けるのですが。幕府と御家人はセットで覚えられるはずです。文章では、「御家人の不満が高まる」、「幕府を倒した後、天皇を中心とした政治を」とあります。 政権の移り変わりに注目して歴史をたどってゆく勉強方法も大事かと思います。移り変わりには、必ず理由があります。そしていろんな歴史上の事件が起こっています。こんなことを知っておくことは現代未来を少しでもよくしてゆくためには必要なことかもしれません。 「幕府」という用語が出てきました。皆、何気なく使っていて、理解している用語かとは思います。用語集、国語辞典、古語辞典で調べて見ました。もともとは、「中国で出征中の将軍が幕を張って軍務を決裁する陣営を指した。」とあり、そこから転じて、最終的には「武家政権」を指す語となった、とあります。社会科においては用語はとても大事です。確実に覚えてゆきましょう。 -
2025.12.26
都立入試・社会を解く(令和7年度)④
1⃣の[問2]は歴史。1問1答のような問題。文章で述べた人物は誰かを選択肢ア~エから選ぶものです。完全に知識として覚えているかを試す問題です。暗記重視の試験には批判が向けられてきてはいますが、知識として覚えてゆくことは基本ですから、教科書をしっかり繰り返し読んで知識を蓄えましょう。教科書のよいところは、歴史の流れや出来事の背景・理由が簡潔にわかりやすく説明されていることです。特に社会科は教科書を徹底的に読み込むことが得点力アップにつながります。 選択肢を見ます。 ア 後白河天皇 イ 聖武天皇 ウ 桓武天皇 エ 後醍醐天皇 どのあたりの時代に何をした人なのか、覚えておけば簡単です。教科書を繰り返し読んでおけば、教科書のどこに出ていたかは思い出されるはずです。そしてどの時代で何をした人なのかも思い出されるはずです。では、提示された文章を見てみます。文章のたった3行の文です。キーワードが必ずあります。 「幕府」こんなのもキーワードになります。幕府は鎌倉時代以降です。よって、2つは簡単に消去できますね。もう一つも、教科書のどのあたりに出ているかく思い出せば、鎌倉時代の前だな、とすぐに分かると思います。 -
2025.12.25
都立入試・社会を解く(令和7年度)③
1⃣の(1)は、地理で、地図を読み取る問題です。今回はとても簡単、正答率も83.1%。令和8年度は、きっと難しくなるように思います。問題を難しくするには、以下の項目を入れることかと思います。 ・等高線の読み取り ・地図上の距離 ・選択肢の地図の地点を複数入れる ・地図記号をじっくり見なくてはならない 今回の問題は地図上にD点が入っているだけです。A, B, C, Dを入れて順路を示されたものは、時間がかかってしまうでしょう。(過去にも何回か出ています。)平均点を下げの方向に向かわせるためにも、令和8年度は、4地点を入れた地図が出てくるように思います。 1⃣の(1)の対策は、過去問、Vもぎ、Wもぎの解き直しや過去問をできるだけ多く解くだけで大丈夫です。地図の読み取りの知識が足りないと思ったら、教科書で復習するだけで大丈夫です。 -
2025.12.24
都立入試・社会を解く(令和7年度)②
1⃣の(1) 地理の問題。 必ず地図の読み取りの問題が出ます。 問題文より先に、ざっと地図や写真を眺めます。写真に<D点から➡(矢印)の方向に撮影した写真>との説明があります。広い砂浜があって海の向こうに半島が見える写真です。地図はア、イ、ウ、エの4つ示してあり、それぞれにD点が示してあります。写真の風景が見えるのは、どの地図に立っているものか、という問題だと分かります。問題文を読まずとも、正解を導けそうですね。結論から言いますと、とても簡単ですぐに答が出ると思います。地図上のD点が砂浜の上ではなく、道路上にあるものがあります。これは消去できます。➡(➡)の方向にとありますが、これを示した簡単な「ルートマップ」があります。これでどの方角を見ているのかを確認しなくてはなりません。このルートマップ、上が北ではなく、方位の記号が入っていますから、これで方角を確定させねばなりません。ア~エの地図は、国土地理院発行2万5千分の1の地図で、方位記号も入っていますが、この地図は、上を北に必ずしていると思って大丈夫でしょう。問題を解くときには、ルートマップのD点から東西南北の線を引いてみるとよいです。 -
2025.12.23
都立入試・社会を解く(令和7年度)①
都立入試の社会の解説をしてゆきます。社会も過去にも何度か解説してきていますが、1年以上は経っているかと思います。久しぶりの感があります。 大問は1⃣~6⃣までで構成されています。問題数は20個で、すべて5点配点です。 1⃣地理、歴史、公民の基本的知識を問う問題 2⃣世界地理 3⃣日本地理 4⃣歴史 5⃣公民 6⃣地理、歴史、公民の融合問題 令和7年度入試の平均点は59.9点でした。令和6年と比べると4.4点ほど高くなっています。令和8年度入試は、少しだけ問題を難しくなるかもしれません。 -
2025.12.22
都立入試・英語を解く(令和7年度)55
まとめの続きです。 単語、文法をしっかり勉強しましょう、とまとめました。どうやって勉強するの?、と思うかもしれません。とても簡単です。ひたすら音読です。「読んで、読んで、読んで、読んで、読みまくりましょう。」教科書だけでも十分です。1レッスンに3つのパートしかありません。レッスン8まであります。これが3年分。 3x8x3=72 たったこれだけです。100にも満たないのです。パートの1, 2はたかだか80語程度、パートの3も400~500語程度です。覚えなくてはならない、と思わず、ひたすら音読をすることです。覚えようとしなくとも、自然にすらすら歌謡曲のように出てくるようになります。校歌を覚えるのと一緒です。英語なんてしょせんは刷り込みです。朝起きて歯を磨く、夜寝る前に歯を磨く、これと同じで習慣化するだけでよいのです。歯磨きをした後に5分音読をする、夜寝る前に5分音読をする。教科書が飽きてきたら、英語の音楽を聴いて、まねして歌いまくってください。お風呂につかって、防水スピーカーを持ち込んで聴いて歌うのがお勧めです。お風呂では、皆、歌がうまいと錯覚して、よい気分になるはずです。 -
2025.12.21
都立入試・英語を解く(令和7年度)54
まとめをします。 大学入試にも共通して言えることですが、単語と文法をしっかり勉強することです。 ・単語 小学生から英語が必須科目となりましたので、その延長線上になるので、覚えておくべき単語数は増加しています。教科書に出ている単語は、隅から隅まですべて覚えるつもりで学習してください。入試では英作文を書かせる問題がありますから、スペリングも確実に覚えましょう。英熟語も英単語のうちに含めます。 ・文法 文法事項は、実は大した量ではありませんから、冬休みなどの長期休暇を利用して集中的にやることで、中学生の文法はマスターできます。1年~3年までの各レッスンで「基本文」を学びます。すべて書き出してみると、たったこれだけか、と感じるはずです。1週間あれば、丸暗記できます。普段から予習復習をきちんとやっておれば、1日あれば丸暗記できる生徒もいるはずです。 -
2025.12.20
都立入試・英語を解く(令和7年度)53
大問4⃣、最後の[問4]です。(1)と(2)の2問あります。それぞれ、質問がなされています。本文の内容に関する質問に対し、4つの選択肢から適切な答えを選ぶ問題です。 (1)姉のえみさんが弟のしょうた君に地域のスポーツの日のポスターを見せたのはなぜか?という質問。 (2)しょうた君がボランティアから何を学んだか?という質問。 とても簡単だと感じましたが、正答率が54.7%, 53.9%と少し低めのように思いました。(1)は第4段落に答がダイレクトに出ています。第3段落から内容的にはつながっていますが、第4段落だけでも正解は導けます。 (2)は、最後の6段落目に答が出ています。ともに、考える余地もなく正解を選べるはずです。 あまり難しい問題ではないのですが、本文を正しく読み取れていないことが不正解だったように思います。同様の文章は模試や問題集にたくさんありますから、多く読み慣れておけば、得点力が上がるように思います。 -
2025.12.19
都立入試・英語を解く(令和7年度)52
大問4⃣、[問3]の(3)の続き、選択肢のイの文は簡単ですが、選択を迷わせるような問題です。けんと君の家族のところへ行って、お話するのですが、これはフェスティバルでのことで、おうちに行くわけではありません。よく読まないで選んだ人も多かったかもしれません。 ウはso~thatの構文で、この構文は覚えやすいですし、訳すのも簡単でしょう。ウは簡単に間違いとわかるかと思います。これを選んだ人は少ないと思われます。 エ これは文法的にも難しい文章です。Shota asked the staff to help him carry water bottles.です。 1. 動詞ask いろんな型をとる動詞なので、辞書を活用し、全部の型を覚えてみましょう。 2. help+人+動詞の原形 昨年まで3年生後半で習うものでしたが、今年度からは、1学期早々に習うことになっています。文法的に難しいだけでなく、しょうた君とスタッフがやることが文章からきちっと読みとれていないと間違えるでしょう。都が公開している解説にも、エの誤答が多かったとあります。選択文のhim,これが誰を指すのか、勘違いしたように感じます。 -
2025.12.18
都立入試・英語を解く(令和7年度)51
大問4⃣、[問3]の(3)です。 On the local sports day, □、□に適切な文を選ぶ問題。正答率は35.7%と低めでした。正解に迷うような選択肢ばかりのように思いました。そして、選択文の文法を正確に理解しておく必要があったように感じます。 ア Shota was told to guide ~. この形にしっかり慣れておくことです。「受け身」の形ですが、しっかり理解できている生徒も多いのですが、日本語で訳すときに難しいことも多いように思います。英語のほうが、「受け身」の表現が格段に多いように感じます。一番の対策は、「慣れる」ことです。「慣れる」には、たくさん英語の文章を読むことです。言うのは簡単ですが、いざやるとなると、文章を探すのに困るのではないでしょうか。トライプラス国分寺駅北口校では、入試問題や長文の問題は、ありすぎるくらい保有していますから、1日1つ必ず読む、ということを決めたなら、学力レベルにあわせてお渡しもできます。 -
2025.12.17
都立入試・英語を解く(令和7年度)㊿
大問4⃣、[問3]です。「本文の内容と合うように」文を完成させる問題です。選択肢から選ぶだけです。(1), (2), (3)の3問あります。さすがに、1問ごと独立していて、それぞれに得点できます。すべて正解でないと正解としない、という問題ではありません。 (1)しょうた君が美術館のお店でけんと君とあったときに、□ 2段落目に書いてあることです。正答率は68.9%と高かったです。けんと君が何をしていたかを問われていますから、簡単のように思います。間違えるとすれば、多くの人がいろんな動作をしているので、他の人の動作と読み違えたためでしょう。 (2)しょうた君が美術館から帰宅した後、姉が彼に□と言った。 第3段落目に書いてあることです。正答率は58.3%。低くはないですね。しかし、(1)よりも迷わずずばり選べるように思いますから、時間不足であわてて読んだ生徒がいたことも影響しているのかもしれません。 -
2025.12.16
都立入試・英語を解く(令和7年度)㊾
大問4⃣、[問2]はお話の内容の順番に並び替える問題。ア~エの4つがあります。アから順番に見てゆきます。 ア けんと君がボランティアの仕事が本当に好きだ、としょうた君が聞いた。 イ しょうた君は、スポーツの日に大忙し、しかし、楽しんだ。 ウ しょうた君は、ボランティアリストに載っている美術館を訪れた。 エ しょうた君は、地域の人々のために働きたい、と言った。 都立入試は解答とともに、問題の解説が公開されています。この問題では、ウとアを取り違える誤答が多かった、と説明されています。おそらくですが、第一段落でのボランティアに興味を持っただけしか書いていないところを、ボランティアが好きであると拡大解釈して読んでしまったのかと思います。想像を働かせすぎて読んではいけないのですね。入試問題というのは、ある意味いじわるにも感じてしまいます。 -
2025.12.15
都立入試・英語を解く(令和7年度)㊽
大問4⃣、最後の5段落目です。ついに、しょうた君がボランティア活動をやって喜びを見出したところまで来ました。最後の段落は、次の冬休みには何のボランティアをやろうかと期待を膨らませる話の展開になるのでは? 姉とのお話をしています。ボランティアを勧めてくれてありがとう、と。姉は、スポーツの日の情報を教えただけで、やると決めたのはあたなよ、なんて言っています。そして、まとめ。しょうた君は心配せずに何でもやってみることが大事、なんて言っています。しょうた君は自信がついた、と。とても微笑ましいお話ですね。言ってしまえば、ありきたりのお話で、すらすら読めてゆける文だと思います。面白いと思うお話ではないですが、そこは我慢して解いてゆくしかないですね。さて、読み終えて、設問を解いてゆきます。[問1]は、下線部文についての問で、読み進めながら解くとよい問題でした。[問2]は、「本文の内容の流れに沿って並べ」かえる問題です。必ず出る問題ですね。すらすら読み進められる文章ですから、簡単なはずです。あれあれ、正答率は36.2%しかありません。なぜ?また、違った理由を考えてみなくてはなりません。 -
2025.12.14
都立入試・英語を解く(令和7年度)㊼
大問4⃣、問題文を読み進めます。美術館でのボランティア活動をしてみたい、しかし、最後の文、しょうた君は、何か新しいことをするときは、心配になってしまう、そして、ボランティアの仕事は出来ないと思って悲しくなった、とあります。ボランティアをやらなくては、このお話はここで終わってしまうので、やるための経緯が展開してゆくのかなと予測がつきます。読みやすい文章なのだということが分かるかと思います。 全部で6段落あり、2番目の段落です。ある日しょうた君が美術館にいると、けんと君がボランティアで働いていた、というお話です。3段落目、しょうた君が家に帰って姉とボランティアの話をして、地域の人のために働いてみたい、と言っています。4段落目、9月のある日、姉がしょうた君に地域スポーツの日のポスターを見せて、そこでボランティアをやるように勧めた、というお話。5段落目、スポーツの日が来ました。しょうた君はゲートでの誘導係をしています。休憩時間に他のボランティアが重いものを運ぶのを手伝った、と。そして、けんと君が家族と一緒に来ていて、対話しています。ボランティアの仕事が楽しいよ、と言っています。 -
2025.12.13
都立入試・英語を解く(令和7年度)㊻
前掲続き。 第1段落、3番目の文、ポスターにプログラムリストがある、と。単なるリストがある、というだけで、2人がしたい、という文ではありません。4番目の文、やっとここで、しょうた君が美術館のボランティアに興味を持ち、5番目の文で、けんと君もボランティアに興味を持ったとあります。6番目の文は、けんと君が、美術館のボランティアだ!芸術に詳しくないが、試しにやってみようと思う、面白そうだし、と言っています。そして、続く下線部のShota also wanted to do that.、と続きますから、じゃあ僕もやってみよう、でtryを選べばよいのですが、その前にある文のget interested inに目が言ってしまい間違えてしまったのかもしれません。 -
2025.12.12
都立入試・英語を解く(令和7年度)㊺
大問4⃣の[問1]、簡単すぎる問題、なぜ、正答率67.1%にとどまったのか?その原因を探っています。前掲でその1つと思われることを示しました。設問文の選択肢を今一度見てみました。設問文、Shota also wanted to につづく動詞を変えているだけです。 ア find イsee ウ try エ get interested in 対象となる段落1、8つの文、下線部は6番目の文。Shota also wanted to do that.、です。also, that、けんと君と同じように、thatしたい、thatは、けんと君がしたいと思ったことを指しているはずですね。見つけたい、でもなく、見たい、でもなく、興味を持ちたい、でもないと簡単に分かるように思うのですが。 下線部までの5つの文、1番目の文は、しょうた君が中1だ、という紹介文、解答にあたり全く関係ないし、選択肢にもあるはずがありません。2番目の文、しょうた君とけんと君がポスターを見た、と。見て、どう思ったのかと話がつながるので、イのsee、見たい、というのはありえないと思います。 -
2025.12.11
都立入試・英語を解く(令和7年度)㊹
大問4⃣の[問1]、簡単すぎる問題、なぜ、正答率67.1%にとどまったのか?正解だった生徒はおそらく、なんでこんな問題を間違えるの?、と感じることと思います。間違ってしまった生徒、なぜ間違ったかを探ってみることが大事かもしれません。 間違った生徒のうち、何割かは、設問文を先に読むという方法を取っているように思います。私はこの方法はお勧めしていません。(当塾では、絶対にやめろ、と指導しています。)問題文を読まずに、[設問1]を読んだ生徒、ア~エの情報を読むわけです。正解は1つなのに、ありえない3つの情報を頭に入れるわけです。 ア ボランティアプログラムを見つけたい イ ボランティアのポスターを見たい ウ ボランティアをしたい エ ボランティアプログラムに興味をもちたい 下線部の前の文のに、「やってみないな!」と書いてあり、Shota also wanted to do that.、とあります。僕もやってみたい、ということですね。問題文をそのまま読んで答えればよい問題を、わざわざ設問文の選択肢ア~エを読んでから問題文を読んでゆく方法、全く意味のないように感じます。 -
2025.12.10
都立入試・英語を解く(令和7年度)㊸
最後の大問の4⃣です。[問1]~[問4]で、[問3]が(1),(2),(3), [問4]が(1),(2)となっており、各4点x7=28点満点の配点です。問題文は1ページ半弱です。6段落構成です。しょうた君が高校1年生でした、の文で始まります。設問文を先に読むやり方は、無駄ですからやめましょう。2番目の文で、夏のボランティアプログラムのポスターを友達のけんと君と見た、とあります。「よし、おもしろそうだ、一緒にやってみよう!」なんて展開の話になるのかと予想がつくのでは。「1学期の成績が悪かったから、そんな暇があったら勉強したほうが良いよね。」、という展開になると話が続いてゆきませんね。3番目の文、いくつかあるプログラムのち、2人が、あるプログラムに興味を持ったようです。図書館の芸術博物館での仕事のようです。けんと君がこれに興味を持ち、しょうた君もやってみたい、と。そこに下線があります。これに対しての設問があることが分かります。すぐに[設問1]を見ます。簡単すぎるくらいの問題と感じます。to do that, thatの内容を具体的に書き直した文を選ぶ問題です。正答率67.1%。低すぎでは。 -
2025.12.09
都立入試・英語を解く(令和7年度)㊷
3⃣の[問4]から。Kさんが英単語の意味に興味を持つ話となります。下線(4)が出てきます。[問4]を見ます。これも後に続く4つの対話を読まないと正解が難しいかもしれません。正答率は58.2%でした。選択に迷ってしまうような作問をしているように感じました。読み進めると、A君が町でみかける説明看板の話題を始めました。それでK君が看板探しの提案をし、下線(5) That's a good idea.と。[問5]を見ます。これは、後に続く対話を読まずとも解けるでしょう。ただ、続く文は読んでから解答するようにはなると思いますが。[問6]は、対話文の中段あたりのOさん何を通じて日本食を学んだかを聞いています。割と長い該当箇所を読み直すことになると思います。しっかり読まないと正解しないかも。しかし正答率は67.4%と高かったです。[問7]は、留学生のOさんが対話した内容を日記に書いており、□の空欄AとBがあり、そこにどんな単語が入るのかという問題です。Aが動詞、Bが名詞です。対話文全体を通してのまとめの問題と思ってよいでしょう。これはとても簡単でしょう。あれあれ?正答率40.9%とかなり低いです。 -
2025.12.08
都立入試・英語を解く(令和7年度)㊶
3⃣は4人の対話文。解き方解説。 最初から素直に読んでゆきましょう。3行目に下線(1)が引かれた文が出てきます。これは、[問1]で質問するよ、という合図です。そのまま読み進めてもよいですし、ここまで読んですぐ解いても良いです。都立入試の問題は、対話の流れどおりの順番で質問してきます。とてもやりやすい試験ですね。落ち着いてやれば簡単な試験なのです。[問1]の正答率は77.8%。最初から3人の短い対話文を読めば簡単に正解出来ます。続けて8個の対話文を読むと下線(2)を引いた文があります。That's nice, Yuka.に下線(2)です。なんでniceなのかを選択肢から選べという問題です。答えは8個の対話文中にあるはずですね。これもここまで読んですぐに[問2]の選択肢を選んで解けます。対話文すべて読んでから解答してゆくのではなく、読みながら問いを解いてゆく方法で大丈夫です。下線(2)の後、8つ対話が続きます。下線(3)が出ています。[問3]を見ます。この問題は、すぐ後に続く対話文を読まなくては正解できないようになっています。そのせいかどうかはわかりませんが、正答率が40%と低いです。 -
2025.12.07
都立入試・英語を解く(令和7年度)㊵
3⃣の解説です。4人の対話文です。学校の放課後に教室で。一人はオーストラリアからの女子の留学生です。対話文はまるまる2ページにまたがっています。4人が38回しゃべっています。「Thank you.」や「That's nice.」や「I see.」などの分もありますから、見かけほど長くはないです。安心して臨めるはずです。 どんな内容か、ごく大まかですが、見てゆきましょう。 星の話をきっかけに対話が広がります。Yさんは星をより深く学んでいる。留学生は日本食をきっかけに日本各地を学ぶようになっている。K君は英語に興味をもつようになった。A君は町の歴史について。町にある歴史説明の看板を探しに行こう!、こんな会話です。実際の学校生活ではこんなまじめな会話はないのかとは思いますが。テレビドラマでも観ているつもりで読むことですね。 いよいよ具体的に解いてゆきます。 -
2025.12.06
都立入試・英語を解く(令和7年度)㊴
3⃣の解説です。これも対話文です。4人の対話文ですから、2人の対話文よりも難しいのかもしれませんが、正答率を見るとそうでもないようです。問1から問7まであります。すべて記号選択で、各4点、合計28点。 ★ここで重要なことをお伝えします。 「設問文から先に読むことは、絶対にしないこと!」 こうしろと教えている指導者が少なからずおり、そうしている生徒も少なからずいるようです。時間の無駄、そして、混乱するだけですから、トライプラス国分寺駅北口校では、こんな指導はしていません。 対話文の内容を読み取れれば簡単なので、余計なことはしないことです。 実例を示してみますか。 [問1] ア テレビでのシーンは最高 イ 本でのシーンは最高 ウ オーストラリアからのシーンは最高 エ 科学館でのシーンは最高 これらの主語は、Oliviaで、thinkする、との選択肢です。Oliviaがどう思うのかを選ぶ問題です。当たり前ですが、答は一つです。対話文を読んでいけば、この中の一つの情報にぶちあたるのです。関係ない情報まで入れておく必要が果たしてあるのか?無駄なことです。問7までありますから、28個中、21個は無駄な情報なのです。 -
2025.12.05
都立入試・英語を解く(令和7年度)㊳
2⃣の3の英作文、模範解答を見ましょう。どんなことを書けばよいか、分かりますし、なんだ簡単だ、と難しく考えなくて済むでしょう。 【模範解答】 I want to practice making cookies more. My father often teaches me how to make them. I will be happy if I can make delicious cookies. 自分の趣味や好きなこと、クラブ活動など、今取り組んでいることを書けばよいことが分かりますね。年によって条件が違うと思います。乱暴ですが、過去問題の模範解答をすべて見ておいて、練習しておけばよいのです。極端なことを言いますと、上記の文のcookiesをcakes, My father をMy motherに書き換えた文を書けるようにしておけば よいと思いませんか。まあ、これは、最後の手段ですかね。好きなこと、取り組みをまずは日本語で書き、それを英語に直すという作業をしっかりやってゆくことです。 -
2025.12.04
冬期・入試直前講習開講!
いよいよ始まりました!トライプラス国分寺駅北口校の冬期・入試直前講習! ■12月3日(水曜)~2月23日(月曜)*国公立大、中期、後期日程の対応が必要なときには、延長あり。 ■開校時間 13:00~22:00 ■年末年始のお休みはなし ■日曜日はお休み (1/4, 1/11は開校予定。他、必要に応じ日曜日も開校することがあります。)祝日も開校しています。 どの塾よりも冬期・入試直前講習の日数、時間は多いのではないでしょうか?もしうちよりも多い塾があるようならば、当然、見直します。 来年度入試で、多くの生徒が合格を勝ち取れるよう、寸暇を惜しまず徹底的な協力体制を敷いています。高校2年生、中学2年生も再来年度入試に向けて、すでに受験体制に入り始めました。より早い準備が必要なことを、トライプラス国分寺駅北口校の生徒たちは皆理解しています。だから、難関校合格の実績を多く出せているのです。 -
2025.12.04
都立入試・英語を解く(令和7年度㊲
都立入試2⃣の3の英作文、どんな形式なのか見てみましょう。毎年同じですから、対策もしやすいです。 「<条件>に合うように、下の□の中に、三つの英語の文を書きなさい。」とあり、<条件>が示されています。 <条件> 〇前後の文につながるように書き、全体としてまとまりのある返事のEメールとすること。 〇Lucyに伝えたい内容を一つ取り上げ、それを取り上げた理由などを含めること。 こんな条件です。Lucyとは、Eメールを送ってきた友人です。 何を書けばよいのか、それは、Lucyが聞いてきたことについてです。Lucyは、「Do you have something that you want to practice more? Please tell me about it.」とメールで聞いており、それに答えればよいのです。 Lucyへの返信なのですが、自身の趣味など好きで取り組んでいることを書けばよいのです。 -
2025.12.03
都立入試・英語を解く(令和7年度)㊱
2⃣の3は「英作文」の問題。読む、聞く、話す、書くの四技能と言いますが、英語力が最も試されるのは、書くことと思います。英検では英作文の問題増をしましたね。 英作文の力を上げてゆくには、どうすればよいか? 書くこと!、です。 当たり前ですね。書けるには、総合力が必要です。単語が正確に書けますか?中学で学ぶ基本文をすべて理解していますか?知っている単語の量は多いですか?書く練習はどのくらいしていますか?読む、聞く、話す、これの力も書くことに大きく関わってきます。トライプラス国分寺駅北口校では、聞く、読むことを徹底的にやることを勧めています。これで英語が体にしみついて、すらすら書けるようになります。皆さん、学校の校歌は何を見なくても歌えますね。何度も練習しているからですね。 そう、英作文、英語力を高めるために良い方法があります。英語の曲をたくさん聞いてみることです。聞いても歌詞がさっぱりわからないことが多いでしょう。文字にした歌詞も一緒に使いましょう。英語の教科書の巻末には、必ず、何曲か掲載されていますね。最新のNEW CROWN3年、Taylor SwiftのShake It Off、ありますよ。 -
2025.12.02
都立入試・英語を解く(令和7年度)㉟
2⃣の3, これの2番目が都立入試で最も差がつく問題です。つまり、「三つの英文」を書く問題です。これだけで配点が12点。もちろん、部分点ももらえます。一番目の問題は内容とあっているものを4択から選ぶものです。3の内容は、1, 2の経験を振り返っての友人へのEメールとそれへの返信です。毎年この形式なので、模試や過去問解くことで十分な事前対策となります。対話文の設定は、必ず留学生の体験で、帰国後に、留学中の感謝とか体験の感想とか、そして何をしているかを書き、そして、最後に、相手への質問事項が書いてあります。その質問に対して返信するという形式になっています。この「英作文」の問題、得点率は53.7%と公表されていますから、6点以上平均で取っているということですね。何らか書けば、得点になるものだと思って、決して空欄で終わらないようにしたほうがよいですね。 -
2025.12.01
都立入試・英語を解く(令和7年度)㉞
2⃣は、1, 2, 3のパートに分かれます。それぞれのパートは、連続性のあるお話です。1, 2は2人の対話文です。2人の対話文は読むには比較的楽だと思います。3人以上になると難易度が上がることが多いように思います。 どちらも、□Aと□Bを穴埋めする問題で、AとBの組み合わせを示した4択から選ぶものです。選択肢を先に目を通すやり方をする人は、これを先にやることで何のメリットがあるのかさっぱりわかりません。間違っても、これを先に目を通すことで対話の内容が理解しやすくなることは、100%ありません。土曜か日曜日か、そして、A駅かB駅かの組み合わせが書いてあるだけですから。このような形式で毎年出題されているので、形式だけは事前に知っておくべきでしょう。模試、過去問を重ねれば十分です。2のパートも、1のパートと全く同様です。AとBの組み合わせの4択を選ぶだけです。1も2も対話文のほか、案内チラシも同時に見る必要があります。ただ対話文だけ読めばよい問題から少し難易度が高くなります。 -
2025.11.30
都立入試・英語を解く(令7年)㉝重要!
1⃣リスニングの解説を終わりました。おさらいですが、事前の放送時にやること、事前の放送は聞かなくてよい(毎年同じなので覚えておけばよい)、そしてその放送時間の間に、設問文の選択肢を見て、質問されることを予測しておく。 2⃣の解説を始める前に、重要なことをお話します。1⃣は先に設問文を読むようにお伝えしましたが、2⃣以降は、設問文を先に読んでから解く方法は止めたほうが良いです。トライプラス国分寺駅北口校では、「絶対に止めること。」と指導しています。信じられないことですが、指導者にもこの方法を推奨する人がいるようです。2年前にこの方法でやっている生徒がいました。時間を余計に使うことになるからと詳細に説得し、改めさせました。模試を一回やっただけで、「先生の言う通りですね。」と。この生徒、模試で70点も取れない生徒でした。都立入試本番では100点でした。 -
2025.11.29
都立入試・英語を解く(令和7年度)㉜
あとちょっとです。 55. Where did you buy the books? (1年P.143) 56. How many soccer balls do you have? 57. What do you like about the pen? 58. How long will I fall? (1年P.145) 59. What's your name, little girl? - My name is Alice. 60. What does it mean? 1年の教科書、まだ「付録」のページにも多く出ていますが、ほぼすべて拾ってみました。60個ですね。授業や定期テストを通じて何度も繰り返しやっておれば、都立入試の英語の1⃣のリスニングは、そう難しいとは感じないと思います。2年、3年の教科書でも、さらにたくさん出ていますから。 来年2/21に都立入試をひかえた中学3年生の皆さんで、英語が不得意と思っているならば、1年の教科書から復習してみるのもよいかもしれません。英語というのは、結局のところ慣れなのです。まだ3か月以上もありますから、教科書を繰り返し読むだけでも得点力は上がります。 -
2025.11.28
都立入試・英語を解く(令和7年度)㉛
もうひと踏ん張りです。 47. What sports do you like? (1年P.113) 48. What's up? (1年P.116) (都立入試のリスニングの質問文にはこれは出ないと思いますが、対話文には出る表現です。) 49. How was it? -It was great. 50. What are you drawing? - My favorite manga character.(1年P.123) 51. What manga do you like? - I like One Piece. I'm a big fan of Luffy. 52. Who's your favorite cartoonist? 53. Oh, the look sad. What's wrong? (1年P.125)(これもリスニングの質問には出ないですが、対話文には出るでしょう。) 54. How can you save the environment? (1年P.127) -
2025.11.27
都立入試・英語を解く(令和7年度)㉚
あと少し、続けますよ。 41. Where did you go in Japan ths year? - I went to Nagaoka. (1年P.107) 42. Who is that boy? - He's Momotaro. (1年P.108) 43. How many hats do you have? - I have five. 44. Whose shoe is this? - It's mine. (shoesになっていないことに注意ですね。シンデレラのガラスのくつの持ち主を王子が探すイラストが載っています。) 45. Where are you going? - I'm going back to the moon. (かぐや姫のイラストが載っています。) 46. Where is a good spot for visitors? - Ah, Wakaba Shrine is a good spot for visitors. What can they do there? - They can get good luck charms. -
2025.11.26
都立入試・英語を解く(令和7年度)㉙
疑問詞を使った文を教科書から順番に拾っています。 35. How about this blue T-Shirt. - I like the design, but I don't like the color. (1年P.93) 36. What are you doing? 37. Whose key is this? Is it yours? - No, it's mine. I't's Riku's. (1年P.94) 38. What did you do last Sunday? - I went to Wakaba Zoo. (1年P.101) 39. What is my best memory of this year? (1年P.105) 40. How can I get to ABC cake shop? -Um, go straight on the street. Then turn left at the second corner. (1年P.107) 41. Which do you drink for breakfast, milk, tea, or juice? -
2025.11.25
都立入試・英語を解く(令和7年度)㉘
都立入試の1⃣のリスニングについて、質問の形を中学教科書から順番に拾っています。前掲、Which~, A or B?の文が出てきました。この形は、過去7年分、出てきていませんね。今後出ないとも限らないので、これも覚えておきましょう。 26. Where does this bus go? (1年P.83) 27. What do you like about your school? 28. What is the boy eating? - He's eating a taco. (1年P.86) 29. Who's in the picture? - Hana, Dinu, and Jing. (1年P.87) 30. What do you do after school in Japan? (1年P.89) 31. What's a good topic? (1年P. 91) 32. What can I say about it? 33. What can I write? 34. How can I write? -
2025.11.24
都立入試・英語を解く(令和7年度)㉗
中学教科書の疑問詞を使う疑問文を拾っています。しばらく続けます。 17. Who is your favorite entertainer? (1年P.68) 18. What do you see in these pictures? (1年P.69) 19. What do you know about the U.K.? 20. What time do you get up? - I get up at six. How about you? (1年P.71) 21. Where is your favorite place in Edinburgh? (1年P.75) 22. What are your plans today? - I have soccer practice. (1年P.79) 23. What time does it start? - It starts at two o'clock. 24. What instrument do you play? 25. Which do you want, strawberry or lemon? - I want lemon. -
2025.11.23
都立入試・英語を解く(令和7年度)㉖
英語1⃣リスニングの質問を見てきて、中学校教科書でどのくらい出てきているのかチェックすることにしました。前掲の続きです。 前掲6. What food do you like?がありましたが、ちょうど今、小学5年生の英語の授業で、教師が What day was it yesterday? -It was Friday.と教えています。 7. How many butterflies do you see? - I see six butterflies. (1年P.46) 8. What is this? - It is a library. (1年P.54) (What's this?) 9. Who is this woman? - She is Makiko. (1年P.58) 10. What do you have in your hand? - I have a book. (1年P. 64) 11. How much ~? 12. How long ~? 13, How far ~? 14. How often~? -
2025.11.22
都立入試・英語を解く(令和7年度)㉕
英語1⃣リスニング。質問を見てきました。質問の形は、中学1年から何度もやってきているものです。教科書にどんなのが出ているのか、見ておきましょう。教科書は三省堂のNEW CROWNを使ってみます。現在中3生が使用した、1,2年のもの、3年からは、改訂が入ったものです。 1. Who's absent? - Kato-kun is. (1年P.4) 2. How do you say 'jisho' in English? (1年P.5) 3. How do you spell 'January'? (1年P.5) 4. What does 'wheelchair' mean?(1年P.5) 5. How was Kobe last week? (1年P.14) 6. What food do you like? - I like rice balls. (1年P.34) *[Exercise1, 2]で、上記foodの箇所を、fruit, animal, movie, TV program, music, color, subjectに変えて練習するようになっています。 -
2025.11.21
都立入試・英語を解く(令和7年度)㉔
英語1⃣リスニング。もう少し過去問をさかのぼってみましょう。 【平成31年】 1. What is Bill going to do? 2. What will Lucy buy at this shop? 3. Who is the tallest in John's familly? 4. How long will the ABC Department Store hold the World Lunch Festival today? 5. What did Mori Taro want people in other countries to do? Who~?の疑問文は令和なってからは出ていませんね。そろそろ出るのでは?おなじみのwant+人+to doもありますね。最上級の表現もありますね。 -
2025.11.20
都立入試・英語を解く(令和7年度)㉓
英語1⃣リスニング。もう十分かとも思いますが、さらに過去問をさかのぼってみます。 その前に、前掲の【令和3年】の都立入試ですが、新型コロナによる学校の休校の影響を受け、出題範囲に配慮、英語の場合は、関係代名詞を出題しない、ということがありました。この年の入試を受けた生徒は、今や大学2年生です。当塾にもコロナ休校を経験した大学生が何人も授業を担当しています。 【令和2年】 1. When are Tom and Lisa going to buy ~? 2. What does Ken want Bob to do? 3. Why was Yumi surprised? 4. Where will they meet ~? 5. If they want a picture, what should they do tomorrow? If ~, のおまけがついた疑問文が出てきましたね。おなじみのwant+人+to doも出ています。be going to~の形もしばしば出てきますね。 -
2025.11.19
都立入試・英語を解く(令和7年度)㉒
【令和4年】 1. When will they practice tennis? 2. Where will she go first? 3. How old is it now? 4. What sports does she like the best? 5. What does she think about ~? What sports does she like~?の形が出てきましたね。 【令和3年】 1. Where are they talking? 2. Why will Jane go to the ~? 3. When will the woman take the train? 4. How long has she tautht English in Japan? 5. What does she want the students to do? How long~の形が出てきました。そして、現在完了形も出てきました。おなじみのwant+人+to doも。これはしょっちゅう出ていますね。 ここまでで過去5年分見てきました。対策するには十分のように思えます。 -
2025.11.18
都立入試・英語を解く(令和7年度)㉑
英語1⃣のリスニングの問題。過去問を徹底的に研究しておくことも得点力UPのために有効です。どんな質問がされるか、令和7年度、6年度を見ましたので、さらに過去問をさかのぼってみます。 (人名などの固有名詞は代名詞に書き換えて示すようにしています。) 【令和5年】 1. Why did he go to ~? 2. What was he doing at one o'clock? 3. How did he get to the concert ~? 4. What made her happy? 5. What does she want the students to do in the future? いかがですか?過去3年分を見ると、どんな質問の文がくるのかが、分かってきたと思いませんか? 直近の過去2年間では出ていない、Why~?の疑問文が出てきましたね。make+人+形容詞の形も出てきましたね。3年連続で、want+人+to doの形が出ていますね。次回、令和8年度の入試は、この2つの形には要注意ですよ。 -
2025.11.17
都立入試・英語を解く(令和7年度)⑳
英語1⃣のリスニングの対策の一つ、過去問を徹底的に研究しておく。 前掲、令和7年度を見ました。過去分も見ておきます。 【令和6】 1. How many dogs does he have? 2. What will they buy at ~? 3. When will they meet at ~? 4. How old is it? 5. What does the zoo want people to do for the new rabbit? 過去2年分を見てきましたが、また新しい疑問詞が出てきましたね。また、want+人+to doの形が2年連続で出ていますね。疑問詞とあとは、助動詞か一般動詞か、そして現在形か過去形か未来形、その違いを整理して一覧表にまとめておけば、どんな質問文が放送されるか、すべて網羅できますね。 -
2025.11.16
都立入試・英語を解く(令和7年度)⑲
前掲で、リスニングの対策を述べました。 過去問からどんなことを聞いてくるのか、具体的に見ておきます。簡易的な表現で書いておきます。 (また、質問は5つなので、番号づけしています。) 【令和7】 1. Where are they going to do~? 2. What will they do? 3. What does she want him to do? 4. When did it open? 5. What can people do~? これだけでも、すべて「疑問詞」で始まる文で質問してくることがあります。疑問詞の数、たかだか知れています。1年の教科書からすべてノートに書き出してまとめても大した作業にはなりません。やってみる価値は大いにありますよ。 -
2025.11.15
都立入試・英語を解く(令和7年度)⑱
英語1⃣リスニングのリスニングが終わりました。 皆さんはどうやって対策してゆけばよいのかを一番知りたいのかと思います。ここでは、過去問を解説しておりますが、過去問を通して、どんな形式で、どんなことを聞いてくるのかを徹底的に知っておくことが十分な対策となります。しかし、その前に、普段からリスニングのトレーニングをしっかりやっておくことが一番の対策です。学校の教科書のQRコードからダウンロードしての音声を何度も繰り返し聞くことです。ここで大事なこと、聞くだけでなく、音読も必ず何度もやってください。しゃべるトレーニングが、<Question 2>の記述で解答することにつながってくるのです。もし、中学1年生、2年生の生徒がこれを読んでいただけているならば、そして、QRコードの音声を聞く、そして音読をしてきていないならば、すぐに始めてください。信じて1週間毎日続けてみてください。必ず、英語力が上がってきます。都立のリスニングなどは屁でもない、と思えるようになります。 -
2025.11.14
都立入試・英語を解く(令和7年度)⑰
英語1⃣リスニングの[問題B]。 <Question 1>は、簡単だったかと思います。正答率は71.1%でした。 <Question 2>は、質問に対する答えを記述式で書かねばなりません。正答率は36.5%と低めでした。いったい、どんなことを聞いてくるのか?そのまま書きます。 What can people do with the comedians in the event hall after the show? この質問でどこに注意すべきか? canがありますね。主語に注意。peopleですね。質問に対する答は、必ず主語、動詞で始める。そう訓練しておきましょう。 People can do ~. do が具体的に何をするのか、これを聞き取ってメモできていれば、簡単にかけるはずです。 模範解答は、They can take pictures. です。They はそのままpeopleで書いても減点には絶対にされません。回答としては正しいのですから。 -
2025.11.13
都立入試・英語を解く(令和7年度)⑯
前掲続き。メモ部分を最初から記載しておきます。 <いつ><どこで><誰が><何を><なぜ><どのように> ショップセンター 2つエリア、イベントホール ブルーエリアにいる 花屋オープン 2しゅうかんまえ せんしゅう ワールド花week はじまる たくさん花がみれる たべたいとき、はしをわたる、グリーンエリア 30以上レストラン 今しゅう、アイスフェス フルーツいっしょに バナナ、イチゴ、ピーチ グリーンエリアとなり、イベントホール パフォーマンス 今日、コメディアン 5じはじまる あとでしゃしん いっしょに 私はこのようなメモが取れました。実際には、1度目で完全に取れたわけではなく、2度目を聞いて、取れました。事前に選択肢を目にし、When~で聞いてくると予測できていましたから、時に関するメモは1回目でしっかりできたと思います。さらに、<Question2>の質問が放送されますから何を聞いてくるかがわかります。What~?の質問です。この質問中で、with the comediansがあり、これが大ヒントですね。 メモの最後にありますね。 -
2025.11.12
都立入試・英語を解く(令和7年度)⑮
前掲続き。リスニングのメモの例。問題の説明の放送で、「ある商業施設」とありました。そして、<Question 1>の選択肢から、When~?で質問することが分かっています。「ある商業施設」の説明なので、必ず、どんな施設かは、冒頭すぐに出てくるはずです。最初、Hello, everyone.ですが、挨拶です。これが最初に来るのが当然でしょうか。さっそく出てきました。Tokyo Shopping Centerです。ショッピングセンターのお話です。 メモを取る場合、英語のほうがよいでしょうが、日本語でも構わないと思います。漢字だと時間がかかるので平仮名やカタカナでもよいのではないでしょうか。 <いつ><どこで><誰が><何を><なぜ><どのように> ショップセンター 2つエリア、イベントホール ブルーエリアにいる 花屋オープン 2しゅうかんまえ せんしゅう ワールド花week はじまる たくさん花がみれる たべたいとき、はしをわたる、グリーンエリア 30以上レストラン 【次回につづけます。】 -
2025.11.11
都立入試・英語を解く(令和7年度)⑭
英語1⃣リスニング、解き方解説をしています。 [問題B]の続きです。前掲でメモを示しましたが、<Question 1>を対象にしただけですから、実際に聞いて取るメモは、何を聞いてくるかわからない<Question 2>にそなえて、メモの項目は膨らませなくてはなりません。メモの取り方は、Vもぎ、Wもぎを受験することで鍛えてゆく方法、英検過去問、都立入試の過去問を通じて高めてゆけばよいと思います。またリスニング用の問題集も利用してもよいでしょう。 いろんな方法がありますが、私は、5W1Hに気を付けてメモを取る方法がよいように思います。 <いつ><どこで><誰が><何を><なぜ><どのように> これを問題用紙の余白に書いておき、聞いたことをメモしてゆくことを試してみては。 実際に音声を聞いて実例を示してみましょう。 (今回は、実際の過去問でメモを取りますので、過去問を解く生徒は、解き終わってから御覧ください。) 続く。 -
2025.11.10
都立入試・英語を解く(令和7年度)⑬
英語1⃣リスニング、解き方解説をしています。 [問題B]、ある施設の館内放送を聞いて、2つ質問されます。<Question 1>は、開始後の1分24秒で、問題用紙の選択肢から、When で聞いてくる予測が簡単についたはずです。ただ、[問題A]よりも難易度は高くなると思います。情報量が多く、適切な答がどれか混乱してしまいがちですから。施設を案内する放送ですから、施設内のお店や場所、食事施設、イベント、それの時間などが話されるはずです。放送では大きくわけて3つの場所が紹介されています。それぞれの場所の説明があり、どんな店があるか、イベントがあるかの放送です。質問は時についてされるはずなので、「いつ?」についてのメモがそれぞれの場所ごとに取れればよいわけですね。 以下のようなメモが取れればよいと思います。 (場所)(いつ) A last week, 2weeks ago B this week C every day, today 5p.m. , after ~ メモの記載の一つが選択肢にありますね。 -
2025.11.09
11/9(日曜日)開校
本日は11:00-17:00にて開校です。 トライプラスは日曜・祝日は全国的にお休みの日としていますが、国分寺駅北口校は、日曜日を開校する日が多いです。先週11/2(日)も開校しました。続く文化の日、11/3(月曜・祝日)も通常どおりの開校で、授業も実施しています。本日の開校は、公立中学生の期末考査の対応のためです。授業も入れています。そして、自習室として開放しています。勉強のための利用の幅が広い、これは良い塾の条件の一つです。塾選びには、こうしたことも確認したほうがよいと思います。実際に塾に足を運び、自分の眼で確認することです。皆さんお気づきかと思います。SNSの情報、便利なようですが、実際に塾に来て説明を受けると、とんちんかんなことが書かれているな、と感じる方が多いようですね。 -
2025.11.09
都立入試・英語を解く(令和7年度)⑫
英語1⃣リスニング、解き方解説をしています。 [問題文B]、冒頭の問題の説明が、日本語で40秒くらいあります。ここでは、どんな場面設定であるかを最初に話されますから、そこだけ注意すればよいです。残った30秒強は、質問文をもう一度チェックしてもよいでしょう。 問題文は、今回の問題では、1時間20秒くらいです。語数は165語です。数年前の問題に比べて多くなっています。英語に関しては、難化傾向が著しく感じています。ただ、それに比例して、皆さんの実力が上がっているので、難しくなってきていると意識する必要はないでしょう。古い過去問を解くときには注意することですかね。簡単に感じるはずです。何が放送されるのか、今回は、「ある施設の館内放送です。」(過去問を解く生徒のために、「ある」と特定されているところをぼかしています。)その施設について、来場者に説明するような文章です。大きく3段落で、総行数は12行ですから、情報量は多いです。聞いた内容のメモが取れる能力が正答率を高めるように思います。情報量が多いですが、質問が2つしかないので、メモが有効になると思います。 -
2025.11.08
都立入試・英語を解く(令和7年度)⑪
英語1⃣リスニング、解き方解説をしています。 [問題A]の3つの対話文を終え、[問題B]が始まります。ここでも、問題についての説明文が日本語で放送されます。この放送では、最初の一文、つまり、どこの場面での放送かがしゃべられますから、それだけ聞く程度でよいです。あとは、聞き流して今一度、選択肢を見て、冒頭の1分24秒で予測した質問を再確認しておくとよいです。時について聞いてくる、つまり、When~?で質問されるはずですね。これは、<Question 1>で、<Question 2>は何を聞いてくるかは放送文を聞かなくては事前予測は不可能、そして、一文の記述で解答しなくてはならない点で難易度が少し上がります。正答率は36.5%ですから、そこそこ難しいとは言えますかね。前掲まで正答率を示していませんでしたので、[問題A]の<対話文3>の正答率を示します。33.1%です。あれあれ、とても低いですね。やはり、want + 人+ to doの形は、しっかり身につけていないと難しいように思います。 -
2025.11.07
都立入試・英語を解く(令和7年度)⑩
英語1⃣リスニング、<対話文3>を見ます。 これも最初の放送時間の間に選択肢に目を通して、何を聞いてくるかを予測していますから、簡単でしょう。 What does A-san want B-san to do?と聞いてくるはずです。ここでもう一つ重要なのが、want + 人 + to doの形がしっかり身についているかです。少し難しい形にはなりますが、中学で習う文の形はたかだか知れた数です。本番までは、100日以上ありますから、全部暗記することは難しくはありません。教科書の巻末にまとめてありますから見ると、わずかなページ数ですから、簡単です。 対話は、これまでと同様、男子と女子2人でそれぞれが4回ずつしゃべっています。質問の答は、誰が誰に○○してほしいで、男子と女子を逆にして、動作の主体、つまり主語がどちらなのかを間違えないことです。少し難易度は上がりますかね。しかし難しくはないはずです。対話の内容は、映画を見たことと、それの原作の本のことです。 -
2025.11.06
都立入試・英語を解く(令和7年度)⑨
英語1⃣リスニング、解き方解説です。 [問題A]の<対話文1>を見ました。次に<対話文2>を見ましょう。女子と男子2人の対話文です。それぞれが4回ずつしゃべっています。すでに、最初に選択肢に目を通しどんな風に聞かれるかの予測がついています。What will A-san and B-san do?で質問されるはずですね。会話の内容は、女子がどうやら物をなくしたようで、探しにゆくというものです。その物は大事なプレゼントでもらったもののようです。これから何をするのか?と聞いていますから、簡単に選べそうですね。やはり大事なのは、What~?で聞いてくるぞ、という予測をたてておくのが大事です。<対話文1>もそうですが、物、場所、時など会話会話に出てきます。Whatで聞かれた場合には、ある特定の物、または何をするかの動作が聞かれますから、場所や時の情報は注意をあまり向けなくてよく、注意して聞くことができると思います。そう考えるととても簡単な問題です。 -
2025.11.04
都立入試・英語を解く(令和7年度)⑧
英語1⃣リスニング、解き方解説です。 これまで、1⃣の試験時間を問題ごとに具体的に見ました。そして、冒頭の説明の放送を聞く必要はなく(毎回決まっているから。VもぎWもぎでもそうです。)、その放送の間に、問題用紙の選択肢に目を通して、何について質問されてくるのかを予測する作業をしましょう、とお伝えしました。 具体的に、どんな放送なのかを見てゆきます。 [問題A] 2人の対話文です。男子と女子です。それぞれが4回ずつの対話文です。最後の女子のせりふは「OK.」だけですから、男子4回、女子が3回しゃべっている会話と思ってよいでしょう。 新しいお店ができたので、一緒に行こう、という内容です。 ここですでに予測していた質問、Where~?という質問がされるはず。場所を意識して、聞いてゆくとよいですね。 -
2025.11.03
都立入試・英語を解く(令和7年度)⑦
英語1⃣リスニング、解き方解説をしています。 1⃣の時間を示しておきます。 ・開始時の説明 1分 ・[問題A] -問題の説明 24秒 【開始からの時間:1分24秒】 -<対話文1>と質問 1分40秒 *2回放送されての時間 -<対話文2>と質問 1分40秒 *2回放送されての時間 -<対話文3>と質問 1分40秒 *2回放送されての時間 ☆途中途中で待ち時間があり、[問題A]は5分45秒 【開始からの時間:6分45秒】 ・[問題B] -問題文の放送+質問 4分15秒 *2回放送されての時間【開始からの時間:11分】 1⃣の配点は20点もあります。2回読まれますから、過去問で練習を積んでおけば、満点が楽にとれる問題です。自校作成校、上位校を目標とする生徒さんは、ここで確実に満点を取ることが必須と思って勉強したほうがよいです。 -
2025.11.02
都立入試・英語を解く(令和7年度)⑥
英語1⃣リスニング、解き方! ☆スタートから放送される日本語での説明、約1分24秒は、問題文の選択肢に目を通すべし! 対話文1, 2, 3の選択肢を見て、質問文の放送が簡単に予測できます。おそらく20秒あれば大丈夫。よって、[問題文B]も同様に出来ます。残念ながら、[問題文B]は、<Question 1>と<Question 2>の2問構成で、1は4つの選択肢ですが、2は聞かれたことに英語で答える、つまり、文を書くようになっていますので、何を聞いてくるかは予測できません。しかし、過去問を7年分くらい解いておけば、こんなことを聞いてくるのだろうな、と分かってきますから、入試前に十分に備えておくことは出来ます。 [問題文B]の4つの選択肢と質問文の予測は、1分24秒の中で十分可能と思いますので、一気にみてみましょう。 [問題文B] <Question 1> (*過去問を解く生徒のために、表記を変更しておきます。) ア Three months ago. イ Last month. ウ This month. エ The day before yesterday. もう何で聞いてくる質問文かすぐに分かりますね。 -
2025.11.01
都立入試・英語を解く(令和7年度)⑤
前掲続き。英語1⃣リスニングの解説をしています。 <対話文3>の選択肢。 (*注:過去問を解く生徒のために、表記を一部変更しています。) ア She wants him to clean~. イ She wants him to buy~. ウ She wants him to play~. エ She wants him to make~. こんな選択肢。<対話文2>と同様、She wants him to do~.が共通です。「彼に○○してほしい。」という文ですから、「何をしてほしい?」と聞いてくるはず。What~?の質問文になるはずです。2人の対話文だから、Sheとhimを会話している人物にした質問文になるはず。EthanとJuliaと仮にしておきます。つまり、What does Julia want Ethan to do?との放送文が流れると予想出来ます。 この分、want + 人 + to doの形がしっかり身についているかどうかも問われます。似たような形、help + 人+do, show+人+物、call+人+何、make+人+形容詞、こんな形を整理して一覧表にまとめておくとよいです。 -
2025.10.30
都立入試・英語を解く(令和7年度)④
前掲続き。英語1⃣リスニングの解説をしています。 [問題A]は対話文が3つ。それぞれに質問がされ、正解を選択肢から選ぶだけです。前掲で<対話文1>を見ました。場所を聞いてくるのだな、すなわち、Where~?と質問してくると分かります。 <対話文2>(*これも過去問を解く生徒のために、実際の表記を変えます。) ア They will study~. イ They will catch~. ウ They will visit~. エ They will watch~. こんな選択肢です。すべてThey will +動詞の文ですね。これで質問文は予想できますね。「彼らは○○する(することにします)。」が答えなので、「何をしますか?」と聞いてくるはずです。What~?の質問文が放送されるはずです。ついでに加えますと、選択肢のThey、2人の対話文からの質問ですから、Theyは、対話している2人のはずです。DonaldとSanaeと仮にしておきましょう。つまり、What will Donald and Sanae do?との放送文が流れると予想できます。 -
2025.10.30
都立入試・英語を解く(令和7年度)③
前掲続きです。 英語1⃣リスニング、冒頭の1分の説明は聞かなくてよい、と申し上げました。そこで何をやるか、を説明します。が、冒頭説明の次に、「問題Aは、英語による対話文を聞いて、…」という放送が入ります。これが24秒くらいです。これも、毎度毎度決まった文句なので、覚えておいて、聞く必要はありません。よって、開始から1分24秒の間、聞かずに出来ることがあります。さあ、何をやっておくとよいか、説明します。簡単です。 問題用紙の選択肢を見ておくと良いのです。実際の問題用紙を見ます。(過去問を解く方もいると思いますから、 そっくりそのままでないように工夫して示します。 [問題1] <対話文1> ア At the department store イ At the library ウ At my house エ At the musium (*注: 実際の問題の表記からは変えております。) 確認するのに5秒もいらないです。ピントくるはずです。質問文は、Where ~?の文になると予測できます。場所を質問してくるのだな、と準備ができるわけです。 -
2025.10.29
都立入試・英語を解く(令和7年度)②
都立入試、英語の過去問解説をしています。都立入試は、2月21日(土曜)です。残り、4か月を切りました。内申点につながる2学期末テストが11/12, 13, 14の学校が多いと思います。内申点が1でも上がるよう頑張ってください。 都立入試、英語の1⃣はリスニングテスト、前掲を参照ください。細かく見てゆきましょう。 問題に入るまえに「開始時の説明」の放送があります。「これから、リスニングテストを行います。問題用紙の1ページを見なさい。」これで始まり、この部分の時間は、なんと1分強もあります。トライプラス国分寺駅北口校の生徒には、こんなものは聞かなくてよい、と指導しています。なぜなら、毎年同じことを言っていますから、VもぎやWもぎを受けておれば、何をしゃべっているかは覚えてしまいます。この約1分の間にやるべき事を教えています。問題用紙の選択肢を見ておくように教えています。 -
2025.10.28
都立入試・英語を解く(令和7年度)
今日からは、都立入試の過去問解説をしてゆきます。 令和7年度の問題です。平均点は63.7点です。 問題の構成は1⃣、2⃣、3⃣、4⃣で、配点は、それぞれ20点、24点、28点、28点です。 1⃣はリスニングの問題です。ここで11分かかります。残りの2⃣、3⃣、4⃣を39分で解くことになります。リスニングは問題文と質問が2度読まれますから、20点満点も取りやすいと思います。問題構成は、大きく[問題A]と[問題B]の2つがあります。 [問題A] 対話文が3つ用意されており、それぞれ質問が1つ出され、その質問に対する答えを選ぶものです。 [問題B] 令和7年度は、「ある商業施設の館内放送」を聴いて、<Question 1>では、質問に対して、4つの選択肢から正しいものを選び、<Question 2>も質問がなされますが、その答えを筆記するものです。単純に答えればよく、筆記だからと言って難しいものではありません。リスニングテストの解き方解説書なるものを、トライプラス国分寺駅北口校にて作成し、都立高校を受験する生徒にはお渡ししています。当塾では、100点満点を取った生徒もおりますよ。 -
2025.10.27
共テ英語リーディング令6追試を解く134
一緒に解き直しをしましょう。 第6問のBを解いています。問4です。まずは対象となる「スライド」の5を見ます。スライドの題名が「Acoustic Fabric Experiment 2」とです。問題文では5段落目が対象です。1番目の実験に続き、もう一つの実験では、とありますので。スライドの空欄箇所が、 Future benefits: ・□ ・Maternity clothing となっています。この問題は、解答の想像がつきやすく、簡単なように思います。cardiacという単語が出来ていますが、かっこ書きで、(heart)とありますから、とても分かりやすくなっています。 いよいよ最後の問5です。 スライド6の題名が「Application Beyond Clothing」となっています。 A,B,C,Dの4つの利用法が挙げられているのですが、誤りが1つあり、それを選ぶ問題です。6段落を読めば、簡単に正解できるように思います。 このように簡単に解ける問題もあるのですが、最後の問題まで読み切って解ききれるかが勝負になってきますね。そうするには、過去問やそれ相当の問題を多く解いてゆくしかないように思います。 -
2025.10.23
共テ英語リーディング令6追試を解く133
<前掲つづき> ⑤The researchers moved a shirt to different places. こんなことはどこにも書いていないとすぐに分かるのでは。4段落の5番目の文にある、various angles away from the shirt と勘違いさせることをねらって作問したのかもしれませんが、簡単に見抜けますね。 ⑥Various types of sounds were measured by a shirt. 一見正しそうにも見えますね。音に反応する布のシャツ、これを音を計り取るシャツ、としても間違いではないのかもしれません。しかし、various type of sounds とは書いておらず、various angleからの音としか書いていないので、この選択肢は間違いですね。 微妙な違いを見抜けるか、見抜けないかを試しているような作問をしているようですね。正確に読み取れているかを試す試験なので、真正面から取り組んで、なぜこれが正解なのか、不正解なのかを、誰よりも詳しく説明できるまで取り組んでみてください。こうした努力が得点力を上げられるのだと信じて。 -
2025.10.22
共テ英語リーディング令6追試を解く132
<前掲つづき> ③音に反応する布が音を記録した。←音波を振動に変え、それを電気信号に変えるのだから、「記録」とは少し違うように思いますが、ニュアンスとしては、音を吸収して、結果的に電気信号を発生させるのだから、記録でもよいのかとも思います。迷うところかもしれません。3段落の1番目の文は、a fabric that can detect soundsとあり、音を「見つけ出す」のと「記録する」は類似しているようにも読み取れるので、この文が残像として残っていると、③は正解としてしまうかもしれません。 ④The output from each fiber was saved. 第4段落の6番目の文の後半に、electrical signals that were stored on a deviceとあります。deviceは、日常的によく使われるようになった言葉ですが、ここでは、音に反応する布のことでしょう。選択肢のoutputとはelectrical signalsのことですね。どうも、これが正解として良さそうですね。 <続く> -
2025.10.21
共テ英語リーディング令6追試を解く130
一緒に解き直しをしましょう。 大問6のBの問3を正解するのは、意外に難しいのかもしれません。第4段落の4番目から6番目の文の内容を言い換えた文を選べばよいだけなのですが。選択肢が6つあり、そこから2つ、順番どおりに選ばねばならず、迷わせるように作問していると思います。 スライド4の箇条書きを示してみます。 1. シャツに音に反応する織物が縫い込まれた。 2. □←選択肢から選ぶ 3. 音が電気信号に変換された。 4. □←選択肢から選ぶ 次に選択肢を見てみます。 ①機械的な振動が布によって曲げられた。→前の3段落に、when (a fabric is) mechanically bentという文があり、これと読み違えることをねらって作問されたように思います。曲げられるのは振動ではなく、布です。 ②いろんな方向から音を発した。←5番目の文に、They clapped their hands at various angles~、とありますから、これは簡単に正解だと選べるでしょう。 <続く> -
2025.10.20
共テ英語リーディング令6追試を解く130
一緒に解き直しをしましょう。 大問6のBの問3を解いています。第4段落を読んでいます。clapという単語が出てきました。clapped their handsですぐに分かるように思います。「音」の振動のことが書いてありますし。いろんな角度から手をたたいてシャツに音を伝えるという実験をしているのですね。pinpointという単語が出ています。辞書には、「~の正確な位置を示す」とあります。実験に使った布がどの方向(角度)からかを正確に示すことが出来た、と書いてあります。aidという単語が出ています。hearing aidとあり、特定の音がどの方向から聞こえているかの手助けとなることが書いてあります。第4段落は、8つの文から成っていますが、4つ目の文から6つ目の文が正確に理解できれば、問3は簡単かと思います。ただし、選択肢が微妙に「ひっかけ問題」のように作られているので、私の場合には、解き直しにおいても考えさせられました。 -
2025.10.19
共テ英語リーディング令6追試を解く129
一緒に解き直しをしましょう。共テの英語は1月17日ですから、ちょうど3か月を切りました。まだ過去問を解いていない受験生も大丈夫です。マーク模試は何度も受験してきたはずです。模試の問題の解き直しを徹底的にしてみて、そして共テ過去問を解いて、解き直しをしっかりやれば対策は十分にできます。 大問6の問3を解き直しています。解くに必要となる第3段に続き、第4段落を読んでゆきます。第3段落では、音の振動が電気信号を作りだすことの説明があり、この知識を使って、Massachusetts Institute of Technologyなどが"acoustic fabric"を作りだした、とあります。そこに至るまでの実験を順番に説明するのが問3になっています。woveという単語が出てきました。原形がweaveの動詞です。身近な単語のようですが、以外に覚えていないかもしれません。スライドの4の1.の文を読めば、「編む」という意味がすぐに分かるように思います。すぐ後にsewの単語も出てきました。これは「縫う」です。問題文では、繊維を編んで、それらをシャツの裏側に縫いつけた、と書いてあります。 -
2025.10.18
共テ英語リーディング令6追試を解く128
一緒に解き直しをしましょう。 大問6の問3を解きます。解くにあたり、スライド3を見なくてはなりません。スライド3の表題が「Acoustic Fabric Experiment」。acousticとfabricの意味が分からなければ、これだけ見ても何のことだかわかりません。分からなくても大丈夫です。少し長いですが、3段落~5段落を読めば、理解できます。3段落は、a fabric that can detect soundsから始まります。2段落まで読んできているので、fabricは意味を知っていなかったとしても類推できるはずです。detectは知らなければ、読み進めるとわかるはずです。Detective Conanは皆知っているでしょう。これから類推するのは難しいかもしれません。「音が探偵できる」とやってはだめです。detectからdetectiveが発生したものなので、detectの意味を覚えなくてはなりません。"piezoelectric materials"という言葉が出てきました。これも文章で説明されていますから大丈夫です。「ピエゾ電気の素材」が電気信号をつくる、と訳せば十分です。 -
2025.10.17
共テ英語リーディング令6追試を解く127
一緒に解き直しをしましょう。第6問のAは難しい単語がたくさん出ていた印象です。Bは、比較すると、難しい単語はそんなにない印象です。Bのほうが読みやすいだけかも、とも思います。単語チェックをしています。問2に出てくる単語を拾っています。 ✅reflect: 単語帳を見ると、「~を反映する」が最初に来ています。入試に最も出題される意味だからなのでしょう。意味としては、鏡などに映す、光などを反射する、<物、事が>反映する、熟考する、の順に覚えるほうが自然なように思います。後半の意味は後から出来てきたように思います。 ✅invent: 中学で習う単語になっているようです。 問3にある単語をチェックします。 ✅conduct: 名詞と動詞のアクセントの違いを覚えておきましょう。ツアーコンダクターはこの単語から来ていますが、動詞のすべての意味を辞書で調べておく必要があるでしょう。 ✅acoustic: アコースティックギターはよく知られていると思いますが、元々の意味が出てくるでしょうか? 問3は難しいと思います。3,4、5段落を理解し、スライド4を見ながら解きます。 -
2025.10.16
共テ英語リーディング令6追試を解く126
一緒に解き直しをしましょう。 第6問のBの第2段落に書いてある実験内容を読み直す必要があります。Huazhong University of Science and Technologyの科学者が、"metafabric"という布を作ったことが書いてあります。中国の武漢にある華中科技大学です。HUSTでとおるようです。とても有名な大学です。これは問題を解くことにはまったく関係なく、知らずとも問題ないです。熱を逃がす布を作ったそうです。この布で作った服を着て実験をしたら、皮膚表面の温度が32℃になったらしいです。問2は、実験内容の文も難しくなく、スライドで綿とmetafabricを着ている人のイラストがあり、簡単に正解できるように思います。設問中の単語のチェックに戻ります。 ✅outfit: このような単語は、知らない受験生が多いように思います。私の推測するに、一般的な日常生活でよく使われる単語(言葉)が、共テにはよく出てくるのかと。 ✅suitable: suitable for で覚えましょう。suitも覚えましょう。関係ありませんが、suiteの単語も覚えましょう。 -
2025.10.15
共テ英語リーディング令6追試を解く125
一緒に解き直しをしましょう。 第6問B、問2に出てくる単語です。問2は、What does the result imply?「実験の結果は?」です。 ✅imply: 過去にも出ている単語です。これを単語帳で調べると、「~を暗に意味する;~を必然的に伴う」です。例文は、The very idea of a society implies that its members have responsibilities., です。「社会というまさにその考えが、その成員に責任があることを暗に意味している。」という訳を載せています。何だか難しいですね。辞書には、<...を>(必然的に)含む、<...を>(暗に)意味する、との訳もあります。このような日本語に訳すと難解になってしまう単語は、英英辞典で調べると、意味やニュアンスがクリアに理解できるようになると思います。英英辞典には、類義語として、suggest, meanが出ていました。 問2を解くに、スライドの3を見なくてはなりません。スライドの表題が「Metafablic Experiment」となっています。その実験は第2段落に説明されています。 -
2025.10.14
共テ英語リーディング令6追試を解く124
一緒に解き直しをしましょう。第6問のBを解いています。今回は設問にある単語から見ています。 ✅textile: textの単語は頻繁に見るように思いますが、これはどうでしょうか?textの意味、textbook, texter, textual, textural, texture, texturedの単語、きちんと調べておきましょう。 ✅fabric: この単語は、問題文の題名「”Smart" Fabrics」で出ています。smartは、「スマート農業」という言葉をニュースなどで頻繁に聞くようになりましたが、これですね。fabricという単語、いきなり出てきて意味がわからない生徒も多いように思います。大丈夫です。本文を読めばすぐに分かります。 ✅address: 住所という名詞だけでないので、辞書を引いて確認しておきましょう。アクセントは二通りありますから注意です。 ✅clever: 中学履修の単語です。 ✅fiber: 一段落目に、the fibers of a plant, とありますし、意味も覚えやすいのでは。これを漢字で書くのは少し難しいかも。 -
2025.10.13
共テ英語リーディング令6追試を解く123
一緒に解き直しをしましょう。トライプラス国分寺駅北口校では、共テをはじめ、英語の入試問題を解くときの「読む時間」を意識し、事前に計測することを薦めています。音読しての時間でお願いしています。共テのリーディングは80分。問題を読む時間にどれだけかかるのかを知っておいて、作戦を練ってみてください。 いよいよ最後、第6問のBを解きます。今回の問題は、第6問Aに手こずり、Bを解く時間がなくなってしまった生徒もいるように思います。衣服の繊維についての説明文でした。7つの段落構成です。加えて、説明文の内容をプレゼン用のスライド6枚にまとめたものが付いています。スライドのところどころに□の空欄があり、これに適切な答えを選んでゆく問題です。読みやすいようですが、知らない単語も出てきているようで、簡単な問題とは言えないでしょう。 問1から見てゆきます。これは簡単です。最初のスライドで、文章のタイトルを選ぶ問題です。今回は、設問文にある単語からチェックしてみます。 ✅bio-based: バイオは日本語になっていますから問題ないと思いますが、そもそも日本語ではどう言うか、また、元の単語は書けますね。 -
2025.10.12
共テ英語リーディング令6追試を解く122
一緒に解き直しをしましょう。共テまで残り、3か月と少し。2次試験、私立大入試も並行して対策してゆくには時間確保が大事になってきますね。過去問を軸においた学習となってくるでしょう。トライプラス国分寺駅北口校でも、受験生には、過去問を解いてもらい、それを個別指導の授業で解き方を教えてゆくことにしています。 大問6のAの問題、「Belief Perseverance」についての説明文を扱ったものです。これは難しいと思いました。説明文が難しいが、設問場面では簡単だ、と感じる問題が過去にありましたが、今回のこの問題は、設問に答える際にも難しいと感じました。私の場合ですが。 設問文の単語チェックをしています。 ✅observe: 覚えやすいと思います。observant, observation, observatory, observer, observing も一緒に覚えましょう。 ✅occupation: 海外への飛行機の中で「入国カード」を書くときに必ず見る単語かと思います。"Occupied"も飛行機の中で必ず見るように思います。トイレの「使用中」の表示ですね。 -
2025.10.11
共テ英語リーディング令6追試を解く121
一緒に解き直しをしましょう。今日は塾生、保護者の方と三者面談をしました。国公立大学が第一志望の生徒です。受験する学校の共通テストの配点を見ました。 国語 100 地歴公民 50 数学① 50 数学② 50 理科(物理)50 理科(化学か生物)50 英語リーディング 80 英語リスニング 20 情報 50 合計500点です。2次試験が600点、調査書等 10点で、1,110点で合否が決まります。この配点を見て、英語のリスニングを全くやらずに受験勉強に打ち込むという手もあるのだと思いました。入試には作戦も大事だなと思います。 大問6のAの単語チェックをしています。問2を見ていますが、この問題も難しいなと感じます。 ✅application: 「アプリ」を知らない高校生はいないでしょうが、この単語の意味を理解していない生徒も多いかもしれません。しっかり辞書を引いて、例文からしっかり理解してゆくことです。 問3を解き直していますが、これも難しいと感じます。 ✅BP appears to have an influence on anyone, という文があります。第何文型か答えられるでしょうか? -
2025.10.10
共テ英語リーディング令6追試を解く120
一緒に解き直しをしましょう。もう共テまで残り3か月ちょっとです。私立大学入試の共テ利用の出願をする生徒もとても多いですね。出願する大学の目標点数の把握が大事ですね。 大問6のAの設問文にある単語をチェックしています。 ✅obstacle: 辞書を引くと、impediment, obstructionを類語として細かな違いを説明しています。 問1は難しいように思います。私は何度読み直しても、うまく説明できません。 次は設問2から。 ✅consequence:in consequence, in consequence of, consequently と一緒に覚えると忘れないです。 ✅an obstacle preventing us from keeping our beliefs strong: prevent + 人 + from doingとkeep + 目的語+ 補語の形ですね。慣れれば何てことないです。keepという動詞はいろんな形をとりますから、その形を覚えてみると、他の動詞の形も連動して覚えられ、とても英語力が上がると思います。 -
2025.10.09
共テ英語リーディング令6追試を解く119
一緒に解き直しをしましょう。昨日、共テの英語の目標点についてお話しましたが、トライプラス国分寺駅北口校の生徒で、数学①、数学②、物理、化学をすべて満点目標にしていた生徒がいます。実際の点数は、およそ9割でした。 大問6のAの単語チェックの続きです。 ✅sufficient: 動詞はsuffice, 発音、アクセントを正しく。 ✅initially: initicalが日本語になっていますが、アクセントは正しく。意味も大丈夫ですね。 ✅practical: practiceを中1で「練習、練習する」で習います。この意味だけでは足りないので辞書で確認しておきましょう。 次は設問文にある単語チェックです。 ✅stop + 人+from doing: 10/7にprotect you from fake informationを。同じ形ですね。 ✅prevent + 人+from doing: これも同じ形ですね。 ✅outcome: 覚えやすく、一度覚えたら忘れないように思います。 ✅convince: これも覚えやすいでしょう。設問文では、who are easily convinced で使われています。 -
2025.10.08
共テ英語リーディング令6追試を解く118
一緒に解き直しをしましょう。トライプラス国分寺駅北口校の教師とも共テの目標点について話をよくします。英語は、準備をしっかりしておけば200点を狙えると言います。実際に、ほとんどの教師は185点以上を取っており、聞いた中での最高は197点です。 単語チェックをしています。問題文はすべて終わり、2番目にある「Your notes:」のシートにある単語です。 ✅tendency: 動詞tendは、今や中学生で履修する単語になっています。トライプラス国分寺駅北口校では中学生の生徒には辞書を徹底的に使うよう指導しています。tendを辞書で引いてtendencyも同時に覚えるわけです。 ✅maintain: これも今や中学生で履修する単語になっています。これも当塾の中学生なら、maintenanceも同時に覚えるわけです。 ✅despite: ここでは前置詞です。(in) despite of, ここでは名詞です。発音も大丈夫ですね。 ✅remark: よくみかける単語ですが、的確に訳そうとすると難しいかもしれません。形容詞のremarkableもしばしば出てきます。形容詞は日本語訳は覚えやすく思います。 -
2025.10.07
共テ英語リーディング令6追試を解く117
一緒に解き直しをしましょう。大問6のAは、難しかったですね。もちろんすらすら簡単に読めた生徒さんもいらっしゃるでしょう。難しい単語も多かったように思います。多読しましょう。語彙力を高める一番の方法です。市販の単語帳は私には?です。教科書を徹底的に読みまくれば、単語帳での勉強は必要ないように思っています。 単語チェックをしましょう。最後の5段落の途中から。あと少しです。 ✅desirable: 動詞のdesire、大丈夫ですね。 ✅convey: これも大丈夫ですね。conveyor(conveyer)は日本語にもなっていますし。 ✅accurate: 辞書を引くと、precise, exact, correct, 反意語inaccurateが出ています。ラテン語由来の単語のようです。語源を見てゆくのも単語を覚えてゆくのがおもしろくなるかもしれません。 ✅protect you from fake information: 前置詞fromの他、againstも使われます。defend, guardも同じ形を取ります。 ✅keeping your life balanced: この形も覚えましょう。 -
2025.10.06
共テ英語リーディング令6追試を解く116
一緒に解き直しをしましょう。共テの英語は1/17(土)です。時間はご存じでしょう。リーディング15:20~16:40, リスニング17:20~18:20。リスニングは実質30分です。ICプレイヤーの作動確認、音量調整のため、30分用意されています。終えて帰路につくときは、もう真っ暗ですね。 ✅stubborn: 問題では、意味がわからなくても理解できるように思います。辞書を引くと、(as) stubborn as donkey が出ていました。私は高校の時、これを辞書で覚えました。忘れていたのを思い出しました。類語に、obstinate, dogged, persistentが出ています。難しい単語ですね。意味的には覚えやすいように思います。 ✅persistence: persistentを前掲に。すぐ次の文にこの単語が出てきています。問題文では、ここで初めて、Belief Perseveranceを肯定的に述べていますね。続く文で、Belief perseverance can also protect you from potentially fake information.,と。 -
2025.10.05
共テ英語リーディング令6追試を解く115
一緒に解き直しをしましょう。共テ、国公立大学を目標にしている生徒は科目数が多いですね。科目数が多いことから”逃避”することはないでしょうか?私の実感、かなり多いです。挑戦する前に、他人への同調でそうなることも多いのかなと感じます。きちんとやれば、高得点は狙えるのにもったいないな、と思います。当塾生は、毎年国公立大学の受験をする生徒がいます。近辺の個別指導塾ではそうはないはずです。大学、社会に出てからもとてつもなく学力は問われます。当塾は学力UPさせることを第一目標に運営しております。 ✅warn: なんでこんな単語を、と思う生徒もいるかもしれません。発音を正しく理解していますか、ということです。warm, wormの単語も大丈夫ですね。 ✅Your internal voice warns you not to act~ 前掲しました、not to不定詞、すぐにまた出ています。warn+人+to doの文型、たくさんありますね。 ✅It is time to remind yourself of belief perseverance. よく使う形ですね。慣れですね。 -
2025.10.04
共テ英語リーディング令6追試を解く114
一緒に解き直しをしましょう。現在三者面談を実施していますが、共テの過去問をいつどのように解き、解き直しから対策まで入念にお話し合いをしています。ただ対策の授業を取ればよいというものではありません。解いてから解説授業をしないと全く意味がありません。当塾は高3生はもちろん、1年、2年生にも、どうやってゆくのかを面談でお話しています。 ✅trust the opinioins of an authority このフレーズを見てつくづく思うことがあります。塾選び、参考書、問題集選び、commercialismに乗りすぎていませんかね?今も昔もです。トライプラス国分寺駅北口校に入会問い合わせや入試相談に来ていただければ、塾選びに納得いただけるお話が出来ると思います。失敗例も多くお話できますよ。 5段落目に入ります。 ✅hard-to-believe: 読んで字のごとくで、簡単だと思います。こんな単語は、辞書には載っていないかと思いますが、英作文で使える単語のように思います。 ✅be careful not to reject: 不定詞ですが、notが付いたものは慣れておけばなんてことないはず。 -
2025.10.03
共テ英語リーディング令6追試を解く113
一緒に解き直しをしましょう。トライプラス国分寺駅北口校では、共テ対策授業は夏期講習から急増しています。総合型選抜入試の学力テスト対応の授業も急増です。個別指導塾の強さを発揮できているとの実感です。共通テスト英語は、昨年生徒、190点以上が2名おりました。春先に80点もない生徒が、この成果です。 さて、大問6のAの単語チェックの続きです。 ✅こんな文があります。 An alternative approach might be needed. なんだ、と感じるかもしれません。昨日の英語の授業に耳を傾けていると、教師が、「be動詞を上手に使えるようになるとかなり上達してきます。」と生徒に説明していました。英作文力がかなり高くなるように思います。 ✅on one's behalf: behalfの単語で覚える必要はないように思います。behalfを辞書で引くと、「援助、見方、利益」と書いてありますが、〖次の成句のみで用いる〗と書いてあります。 ✅take advantage of これもそのまま覚えたほうがよいと思います。ただし、advantageは辞書で引いて一度は見た方が良いと思います。 -
2025.10.01
10/5, 12, 19の日曜日は開校
トライプラス国分寺駅北口校は、10月5日、12日、19日の日曜日を開校します。 高校生の中間テストが控えており、テスト対策の勉強をしたい生徒が多いので、教室を開放してご利用いただけるようにしています。また、テスト対策の授業が必要な生徒には授業を実施できるようにしています。 開校時間は11:00~17:00としております。 生徒のみんなは、静かに集中して勉強しています。 次は、公立中学生の2学期末テスト、これは都立高校入試の内申得点に直結するもの、11/2, 9, 16の日曜日も開校しなくてはなりませんね。授業もできるよう、教師をスタンバイさせています。 -
2025.09.30
共テ英語リーディング令6追試を解く112
一緒に解き直しをしましょう。大問6のAの単語チェックをしています。難しい単語がたくさん出てきます。語彙力と読解力、速読力の関係を身に染みて感じます。 前掲、physicianの単語がありました。physical, physically, physicist, physics, physiography, physiological, physiology, これら一気に覚えましょう。 ✅occurrence: 動詞のoccurと一緒に覚えましょう。 ✅ignore: ignorance, ignorantも一緒に覚えましょう。 ✅harass: harassmentが日本語になっていますから大丈夫ですね。 ✅ground-breaking: 文脈から想像はつくでしょう。ここでは形容詞。名詞は、「起工(式)、鍬入れ(式)」 4段落目に入ります。 ✅insight: inとsightから容易に連想でき一発で覚えられますね。 ✅encounter: counterの単語をしっかり辞書で学習してみるとよいです。 ✅alternative: alter, alternateなども一緒に覚えましょう。 -
2025.09.29
共テ英語リーディング令6追試を解く111
一緒に解き直しをしましょう。私も今、大問6のAの問題を詳細に読み直ししています。前掲で、専門用語を示してみました。そして学習してみました。倫理政経の教科書には載っているのかもと調べてみましたが、まだ載っていないようです。少し古い教科書だからかもしれません。ふと頭に浮かんだのは「メディアリテラシー」の用語です。最近では常識な用語になったかと思います。現代社会の教科書にはすでに出ていますね。英語の単語literacyを使います。意味は、1. 読み書き能力、活用能力、教養[教育]があること、反意語はilliteracy 2. (主題。領域の)知識能力、応用力、です。2.の意味では、computer literacyの用例があります。今後、リテラシーを扱った文章が入試問題に出されることは多いかと思います。リテラシーとはどういうことなのかを理解しておくだけで、問題が解きやすくなることもあろうかと思います。どの教科も万遍なく学んでおくことも大事だと思います。 単語チェックを少しでも勧めておきましょう。 ✅physician: surgeon, doctorの違いを調べましょう。 -
2025.09.28
共テ英語リーディング令6追試を解く110
一緒に解き直しをしましょう。大問6のAは、「Belief Perseverance」の題名の心理学の説明文です。難しい文章です。単語チェックをしていますが、まだ2段落が終わったばかりです。ここで、問題文中、太字で書いてある「用語」をおそらく心理学での専門用語と思いましたので、それぞれ調べてみました。 ・belief perseverance ・confirmation bias ・backfire effect ・Semmelweis reflex インターネットだと即座に出てきます。やはり心理学の専門用語です。それぞれ日本語用語に訳されており、「信念の固執(概念保守主義とも呼ぶ)」、「確証バイアス」、「バックファイア効果」、「セメルヴェイス反射」と出てきます。これだけ読んでもさっぱり分かりません。大問6のAは、具体例を挙げて説明しているので、どういうことかがよく理解できます。問題文の5段落目が結論です。そこには、新たな情報に出会ったときには、すぐに拒絶しないよう注意しなくてはならない、と書いています。昨今、インターネットから情報を得る機会が多くなり、注意することの重要性を指摘しています。 -
2025.09.27
共テ英語リーディング令6追試を解く109
一緒に解き直しをしましょう。大問6のAは、精読してみて、繰り返し何度も読んでみてください。読むごとに、このような難しい文章が出題されたときにきっと役立つはずです。 単語チェックの続きです。 ✅reluctant be reluctant to do で覚えるとよいです。この形が圧倒的に多いはずです。覚えてしまえば簡単な単語です。 ✅conclusion 動詞concludeから覚えましょう。include, excludeも一緒に覚えましょう。conclude, conclusion, conclusive, conclusively もまとまりで覚えましょう。includeなども、すべて同様に覚えられます。 ✅bias 日本語でもよく使われるようになっている気がします。 ✅consistent consist, consistency, consistently もあわせて覚えましょう。ついでに、insist, resist, assistも覚えましょう。 ✅stick この単語は辞書をじっくりチェックしておくべきかと思います。辞書では、stick toの連語で、どんぴしゃな訳がありました。 -
2025.09.26
共テ英語リーディング令6追試を解く108
一緒に解き直しをしましょう。大問6のAは、人の心理についての説明文(科学的説明文)です。難しい単語がたくさん出てきます。単語力がある生徒は、読むスピードも内容理解も高いはずです。単語力は大事なのです。単語力を高めるには、その場しのぎ的に訳せるだけでなく、単語ひとつひとつ、辞書でじっくり噛みしめて学習してゆくことでしょう。現代文、古文、漢文も同様のように思います。英単語1900とかありますが、これだけでは、実戦的な単語力はつかないように思います。 単語チェックの続きです。 ✅range 前にも扱ったはずです。この単語も辞書をじっくりチェックしたほうがよいです。たくさん意味があります。 ✅ちょっと難しいかな、と思う文がありましたので、抜粋。 The participants were presented with evidence that led them to conclude that firefighters who were willing to take risks performed their jobs better.難しいと思います。第2段落全体としてもとても難しいと思います。 -
2025.09.25
共テ英語リーディング令6追試を解く107
一緒に解き直しをしましょう。大問6のAは、難しい単語がたくさん出てきましたね。説明的文章なのでそういうものなのでしょう。英語の説明的文章を読むにも、現代文の説明的文章を読む力が関係してくるように思います。卒業した塾生で、国語力がずば抜けて高い生徒がいました。もちろん、英語も数学もずば抜けて成績が良かったです。お話を聞くと、小学生の頃からたくさん本を読んでいたそうです。そのおかげかどうかわかりませんが、読むスピードがとても早いのです。トライ模試の国語などは、必ず時間を余らせていました。国語の語彙力も高いのでしょう。だから、英語になっても、読解するときに国語の語彙力がすばやい理解に関係しているように思えてなりません。 単語チェックの続きです。 ✅conflict 私はこの言葉は、高校の倫理社会で覚えたように思います。だから、私の場合は、まず、「葛藤」という意味がきます。 問題文でもそのように訳してもよいでしょう。辞書を引くと、「衝突」、「対立」とも出ています。こちらのほうがよいかもしれません。大事なのは、文脈から言葉のニュアンスがつかめ、それを適切な日本語にあてはめられるかだと思います。 -
2025.09.24
共テ英語リーディング令6追試を解く106
一緒に解き直しをしましょう。 前掲、neitherの単語に触れました。桐原書店の「Next Stage」で調べました。多くのページ(項目)で、たくさん説明があります。最初は第9章代名詞のところに出ていました。neither of A の説明がありました。「neitherはbothに対応する否定語で、対象は2つ[2人]であることに注意。」と。「対象が3つ[3人]以上の場合は、none を用いる。」とのことです。前者はAのうちどちらも~でない、と訳し、後者はAのうちどれも~でないと訳すとの説明も。これで、違いが理解しやすいですね。この文法書のよいところは、入試に出た文を問題形式にしているところでしょうか。ただ文法の説明を読むより理解は深まると思います。似たような形式の文法書に、「いいずな書店」の「Vintage」があります。これらを教材に指定している学校も多いように思います。できれば1,2年のうちから、徹底的に繰り返し覚えてゆくようにすると、とても良いと思います。 -
2025.09.23
共テ英語リーディング令6追試を解く105
一緒に解き直しをしましょう。 大問6のAに出てきた単語をチェックしています。まだ1段落目です。 ✅neither A nor B neitherという単語は難しいなと私はずっと感じてきました。AもBも~ない(しない)、と簡単に覚えられるのですが。日本語にはない形だからのような気がします。文法書(いいずな書店)を見ると、Section22 接続詞の箇所に説明がありました。接続詞のnorの箇所にありました。neitherは副詞や形容詞です。私の場合ですが、このようななじみにくい表現は、簡単な例文で覚えこむようにしています。そこで、中学の教科書から拾ってみました。あれれ、難しいぞ。 I'm only a child and I don't have all the solutions, but I want you to realize, neither do you! 中3光村のHere We Go! の教科書。もう1か所あり。対話文。 A: I can’t believe you're leaving within an hour. B: Me, neither. この表現、慣れないと使えないです。 -
2025.09.22
共テ英語リーディング令6追試を解く104
一緒に解き直しをしましょう。高1、高2生も解いてみるとよいです。トップクラスの進学校は、高1の共テ同日の日に解かしていますよ。その意図はわかりますね。 ✅objection ✅reasonable ✅cause ✅psychological ✅characteristic ✅maintain ✅exist ✅despite これらの単語のある文章をそのまま、抜き出してみます。 Most of their objections will be reasonable, but some may be caused by belief perseverance, the psychological characteristic of maintaining an existing belief despite any new information. 単語の基本的な意味が理解できていると、簡単にすらすらと読めるのではないでしょうか。単語帳でひたすら勉強するよりは、多読することで、これらの単語はしょっちゅう出てくるかと思います。単語帳での暗記は、修行、忍耐が伴いますから、私はほどほどにしたほうが良いと考えます。 -
2025.09.21
共テ英語リーディング令6追試を解く103
一緒に解き直しをしましょう。共テまでは、約4か月。対策するには十分に時間があります。まだまだ、得点力は伸ばせます。頑張って! 大問6のAの単語チェックをしています。 ✅out-of-date out-of-xxxx の単語は辞書を見る限りでは、そう多くはありませんから、全部チェックしてみましょう。辞書に載せていないものもきっとたくさんあるようには思ったのですが。 ✅update 高校生がそうだそうだ、と言いそうな文の中にある単語です。If you ask your teachers to update these rules, your ideas may be rejected. these rulesとは、全文にあるout-of-date rules at schoolのことです。今も昔も、そしてこれからも、学校と生徒の”闘い”はなくなることはないのでしょうね。身近なところで、非常に疑問に思う学校の規則があります。「学校の帰りに塾に行ってはならない。いったん帰宅してからでないと、行ってはいけません。」、という学校があります。理解に苦しみます。禁止にする理由を説明できるのですかね。 -
2025.09.20
共テ英語リーディング令6追試を解く102
一緒に解き直しをしましょう。 大問6のAに出てきた単語チェックです。 ✅belief perseverance これは題名となっていますが、最後まで読んで、私は、どういう訳をつければよいものか、思いつきません。「人の思い込み」について書かれたものだと読み取りましたが、題名としてはしっくりこないようです。そこで、問題の2つ目にあるまとめのメモ書きを見ると、Belief perseverance is a tendency to maintain an existing belief despite any new information.と書かれています。正しいと思っていることを保とうとする(人の)傾向、と書いてありますね。 ✅assign 順序が逆になりましたが、これは、冒頭説明文にある単語です。すでに何度も何度もお伝えしてきていますが、この冒頭説明文は、読む必要はないと私は考えています。これを読まなければ解答に影響するものは、これまで皆無です。単語としては、過去何回か掲載もしており、大事な単語なので、挙げておきます。assign A to B, assign B A の形で覚えましょう。 -
2025.09.19
共テ英語リーディング令6追試を解く101
一緒に解き直しをしましょう。大問6のA、難しいと思いますが、学習教材としても、良問ですから、しっかり読み取れるまで何度も読んでみましょう。 第四段落に入ります。「Belief Perseverance」という題名で、これまで読んできて、私は「思い込み」について書かれている文章だととらえました。第二、三段落とも、事例を挙げて同じことを説明しています。第四段落も事例をあげ、最後に、人は、「the opinions of authority」の意見は用意に受け入れる、ようなことが書いてあります。最初からしっかり内容理解できれば、あとはすいすい読めるように思います。第五段落は、まとめの段落です。これまで、「belief perseverance」の悪い側面を述べられてきたのですが、正しい情報を読み取るときには、必ずしも悪いことばかりではない、と書かれています。インターネットの情報の真偽を見抜くときに役立つようなことが書かれています。全体を通して、初見で読むには難しい文章だったと思います。 -
2025.09.18
共テ英語リーディング令6追試を解く100
一緒に解き直しをしましょう。大問6のAの問題文はとても難しいと思います。文章を正確に日本語訳しようとすると難しいと思います。そんな必要はありません。どんなことが書いてあるのかが理解できればよいのです。もちろん、解き直しで精読して、きちんと日本語訳できるようにしたほうが良いです。 第三段落、これも難しいですが、第一段落、第二段落と読み進めた上ですから、読みやすくなってくるように思います。「belief persererance in one group in society」について書かれています。医師が証拠に基づいた事実を示しても、それを受け入れようとしない事例が書いてあります。このような現象を「Semmelweis reflex」と呼ぶそうです。医師の名前をそのままとっています。ここでも、人は「思い込み」から抜け出すことが難しい、という事例を書いています。難しい単語がたくさん出てきますけれども、言わんとしていることは、理解しやすいと思います。意味の分からない単語は、文脈からつかめればよいのです。 -
2025.09.17
共テ英語リーディング令6・追試を解く99
一緒に解き直しをしましょう。大問6のAです。文章理解が難しいと思います。解き直しでは徹底的に精読してみましょう。その後、徹底的に何度も音読を繰り返しましょう。読解力、速読力が必ず上がります。 第一段落から難しいのですが、人が持つ「思い込み」のことを説明してゆく文章であると、私は理解し、読み進めました。第二段落も難しいです。ある学者の研究内容が書かれています。途中、「我々が正しいと思うことを変えるのは難しい。」、とあります。その理由に、我々は「confirmation bias」を持っているから、とあります。そして、これを説明しています。a psychological tendency to look for information consistent with our existing beliefs、と説明しています。さらに、他人が正しいと思っていることを誤っていると説得しようとすればするほど、かたくなに、考えを改めようとしなくなる、と言っています。そしてそれを「backfire effect」という用語にしています。人の誤った認識を正すのは難しい、ということを私は読み取りました。 -
2025.09.16
共テ英語リーディング令6・追試を解く98
一緒に解き直しをしましょう。大問6のAは難しい文章だと思います。何度も読み直しをすることで、得点力は確実に上がりますから、面倒くさがらずに繰り返し読むようにしてみてください。 「Belief Perseverance」という題名、perseverance という単語、意味が分からない生徒がかなり多いように思います。もちろん私も。前掲に説明した続きに、maintaining existing belief とあります。これまで信じてきたことが正しいとする、人間の特徴だと書いています。私が第一段落を読んでbelief perseveranceの意味を考えるとき、思い浮かぶことは、「運動中は水を飲んではいけない。」と教え込まれてきた時代があったことです。これが正しいと思い込んでいる教師がたくさんいた時代があったのです。そう、「思い込み」と訳して読み進めても問題はなさそうです。perseverance を辞書で引きました。「忍耐、がんばり、ねばり(強さ)、不屈」です。無理やり訳す必要はないように思います。読み進めてゆくと、「人間の思い込み」を心理学的に説明していっている文章だと分かりますので。 -
2025.09.15
共テ英語リーディング令6・追試を解く97
緒に解き直しをしましょう。どの科目もですが、かなりの量です。これに少しでもなれるためにも過去問を多く解いてゆきましょう。 いよいよ最後の大問6です。AとBの2つの文章を読むことになります。それぞれに、内容をまとめたシートもあります。相当な量を読まなくてはなりません。大問6だけで配点が24点あります。量のある文章を読み取るトレーニングは、まだまだ日数がありますから、しっかりやってゆきましょう。 Aから解いてゆきましょう。問題文はほぼ2ページで、次が、内容を箇条書きにまとめた「ノート」で5か所ほど空欄になっており、そこに最適なものを設問から選び埋めてゆく形式です。読み取るに難しいと感じました。単語も難しい単語が多くあると感じました。「Belief Perseverance」の題名の記事です。いきなり題名から、分からないかもしれませんが、1段落目に説明がありますので、理解はできそうです。 学校には時代錯誤の規則があるかも、という書き出し。教師に規則の見直しを求めても、反対されることがあり、「Belief Perseverance」による反対があると思う、と言っています。 -
2025.09.149月ご入会でスタートしてみませんか? 9月、10月は、転塾が最も多い時期です。トライプラスの分析によりますが、夏期講習での成果が思わしくなかった生徒、保護者様が、塾を変えてみようとお考えになることが多いようです。トライプラス国分寺駅北口校でも、同様の理由で入塾される生徒さんが多いです。ということは、トライプラス国分寺駅北口校をお辞めになって他塾へ移る生徒さんがいるかというと、この時期ではこれまでありません。他の時期で転塾されるケースは、これまでありましたが、当塾では、転塾で去る生徒さんよりも、他から入ってくる生徒さんのほうが圧倒的に多いです。そして、入塾してからの継続期間が長いことも特徴でしょう。そのおかげもあってなのかと思います、より上位校への合格実績がずば抜けて多いです。当塾は国分寺駅の北口からすぐのところです。塾も多いですが、実績を比べるだけで、質の高い授業が出来ていることの想像がつくように思います。難関校を目指したい生徒、入塾大歓迎です。
-
2025.09.13
国分寺駅北口校の三者面談
トライプラス国分寺駅北口校では、9/6(土)より、生徒・保護者・教室長での三者面談を開始しております。 お話する主な内容は、以下です。 ・志望校の確認 ・現状の成績、今後の成績の目標設定 ・受験までのスケジュール確認 ・受験までの学習計画 ・冬期講習+入試直前講習での受講計画 これらは、受験生のものですが、中1、中2、高1、高2生でも受験を視野に入れてお話をしています。 トライプラス国分寺駅北口校では、在籍塾生のみならず、高校進学が決まり退会した生徒に対しても、大学入試を目指しての学習、進路相談を受付しております。さらに、塾生以外の生徒、保護者様も受付しています。 面談をして感じますことは、学校によって、また担当する教師によって、随分と内容とその詳細さが大きく異なっていることです。とにかくどこでも良いから大学に入学してもらえればよいという姿勢の学校があることを感じます。私見ですが、勉強したくないのならば、大学へ行く必要はないのではと考えています。 -
2025.09.12
共テ英語リーディング令6・追試を解く96
一緒に解き直しをしましょう。問題文は、旅に関するエッセイ、作者が旅の思い出にと仏像を買いましたね。食べ物は形に残りませんので、私も形に残るものをよく自分のお土産に買います。 大問5の問題文、最後の8段落目、単語チェック。 ✅cause ここでは動詞。名詞もありますから、辞書で調べましょう。発音は大丈夫ですね。動詞の文型も確認しておきましょう。 ✅disagreement 簡単かとは思います。大事なことは、日本語でぴったりの訳が瞬時に思い浮かぶようになることかと思います。英語を母国語とする人は、そんな必要はないのですが、日本人が外国語を学ぶときは、大事なことかと思います。辞書では、不一致、相違、意見の相違点、けんか、争い、という訳が載っています。もっと難しい単語も多いかと思います。国語も鍛えておくことも英語上達につながるように思います。 大問5は問題文の後に、内容を箇条書きにまとめたメモが続きます。そこに空欄が設けてありますので、これも設問の一部とみなしたほうがよいでしょう。ここには難しい単語は〖imply〗くらいでしょうか。文脈から簡単にわかるでしょう。 -
2025.09.11
テ英語リーディング令6・追試を解く95
一緒に解き直しをしましょう。今、取り扱っている問題は、旅に関するエッセイです。旅では日常生活では得られない経験が出来てよいですね。この問題文では、旅のパートナーが不機嫌になる場面が。私もしばしば経験あり。 大問5の問題文、単語チェック、あと少し。7段落目続き。 ✅I found myself buying a little figure of the Buddha~. 〖find〗の文型を覚えておくととても応用が聞くように思います。辞書に〖目的語繰り上げ構文〗という説明があり、同じ構文をとる動詞とあり、believe, consider, expect, feel, imagine, know, perceive, prefer, prove, suppose, think, understand, wishが載せてありました。 ✅figure 9/8にも掲載しましたが、これこそ名詞での「お人形」ですね。彫像とかが適訳なのでしょう。木彫りか銅製の仏像なのでしょうかね。 ✅bother 大問5では、irritate, frustrate, annoyと似たような意味の単語がこんなに出ていますね。 -
2025.09.10
共テ英語リーディング令6・追試を解く94
一緒に解き直しをしましょう。解き直しでは、文法事項のおさらいもしておきましょう。高校では、分厚い文法書も副教材として持たせていると思います。この一冊を3年間、何度も何度も見返すことで、文法を体にしみつかせおくととてもよいです。英文法、馬鹿にしないでやったほうがよいです。英語圏の人も、ちゃんと英文法は勉強するのですよ。その人たちが使う英文法書を使ってみると楽しいかもしれません。 大問5の問題文、単語チェック、まだ続きます。7段落目に入ります。 ✅departure 簡単ですね。動詞〖depart〗を引いておきましょう。department, departureともにこれから派生した単語ですね。反意語も大丈夫ですね。飛行場では、はたいてい2階がdepartureで1階がarrivalになっているように思います。大きな空港でのdeparture、ターミナルやゲートを間違えると、とてつもない距離を歩いたり、ときに走ったりしなくてはなりませんから、出発前は、調べておくのがよいですね。大学受験で羽田から地方に行くときなどは。 ✅souvenir これも簡単ですね。書けるようにもしましょう。 -
2025.09.09
共テ英語リーディング令6・追試を解く93
一緒に解き直しをしましょう。大問5くらいまで進むと、問題文が長いですね。私も長いのは嫌なのですが、多く解くことでこれは克服できるはずです。 大問5の問題文、単語チェックをしています。5段落目つづき。 ✅it was you who decided to help me. これは、強調構文ですね。必ず文法で習うはずです。It is ~ that ・・・、It is ~ which ・・・、の形もありますね。It was not until ~ that ・・・も定期テストでは必ず出されているのでは。 6段落目に入ります。 ✅It made me feel a little down because~. make + 人 + 動詞原型の形もおなじみですね。feel downはSVCの文型で、downはここでは形容詞ですね。前置詞、副詞、形容詞の役割を持つ前置詞、まだありそうですね。 ✅I would have had more fun with a friend. 仮定法過去完了ですね。文法書は適宜再確認することはよいように思います。 -
2025.09.08
共テ英語リーディング令6・追試を解く92
一緒に解き直しをしましょう。前掲に音読も、と書きました。だまされたと思って、50回読んでみてください。一度にではなく、1日1回でよく、これを続けてみてください。世界が変わってくるはずです。 大問5の問題文、単語チェックをしています。5段落目。 ✅hesitation 辞書を引くと、そっくりな用例が出ていました。after some hesitation, 。「躊躇」ですが、辞書ではひらがなです。難しい漢字ですね。漢字にも強くなると、英語の上達にも役立つはずです。 ✅ask + 人 + if~おなじみの文型です。ask + 人 + wh節・wh句、ask + (人) + if[whether]節の形も一緒に覚えましょう。 ✅figure 問題文では、we figured it out together., とあります。figure outの連語で勉強しているかと思います。〖figure〗の単語は、名詞と動詞があり、多くの意味がありますので、よく調べておくとよいでしょう。フィギュア、というと、コンビニでくじに当選するともらえるお人形を思い浮かべます。私の学生時代にはこのような言葉はなかったような。 -
2025.09.07
共テ英語リーディング令6・追試を解く91
一緒に解き直しをしましょう。解き直しでは何をしますか?単語、文法は基本ですね。派生語、類義語、接頭辞など肉付けしてゆくととてもよいですね。もう一つやってほしいことがあります。ひたすら問題文、設問文を音読してみることです。そうですね、50回くらい試しに読んでみてください。当塾にいた中学生で難関都立高(Wもぎ偏差値ボーダー66)に合格した生徒が、言ったことがあります。「先生、音読の効果はとてつもないですね。」と。 大問5の問題文、単語チェックをしています。5段落目からです。 ✅ancient 授業を観察していると、これの発音ができないことにでくわすことが多いような印象です。共テで発音を試されることはありませんが、入試で面接試験をやる大学もあります。この程度の単語はきちんと読めて当たり前です。発音を軽視しないでくださいね。 ✅managed to do これもおなじみの連語ですね。単語帳の意味の丸覚えで、「管理する」と訳する人はいないですね。I managed to take a bus there. 問題文ではこれで出ています。 -
2025.09.06
共テ英語リーディング令6・追試を解く90
一緒に解き直しをしましょう。解き直しをじっくりやってみると、問題形式に慣れてきます。運動部の試合はしっかりした準備をして望まないことにはよい結果が出ないのと同じですね。 前掲で、I was irritated~の形をいくつか紹介しました。中学の教科書の巻末に単語を分類したページがあります。三省堂NEW CROWNでは、「気持ち・感情」の欄に、以下のように出ています。過去分詞形のみのものを抜き出します。 ・I am tired. ・I am surprised. ・I am scared. ・I am excited. ・I am shocked. ・I am worried. ・I am bored. このように、同じ仲間の単語を拾い集めてゆく作業を続けてみると、語彙力が上がると思います。 中学の教科書もあなどれないものです。ある高校(自校作成校)の入試問題解説会に参加したときに、先生が、「教科書は、欄外まですべて隅から隅まで徹底的に目を通し、覚えてゆくように。」とおっしゃっていました。その通りだと思います。 -
2025.09.05
共テ英語リーディング令6・追試を解く89
一緒に解き直しをしましょう。現在、高1、高2の生徒も、早くから慣れておくとよいですよ。やってみてください。 大問5の問題文、単語チェックをしています。4段落目に入ります。 ✅interact 問題文中では、I enjoyed interacting with the locals. とあります。文脈からも意味は想像つくかと思います。接頭辞の〖inter-〗の単語も一気に調べてみましょう。 ✅irritable 動詞〖irritate〗は頻出でしょう。I was irritated ~. の表現は多いのかと思います。9/2にI was fascinated~.を紹介していますが、大問5の問題文には、以下のような同じ形がたくさん出てきます。 I was impressed, we were confused, また、be 動詞ではないですが、 I felt a little hurt, He seemed frustrated, I felt bored, ✅annoy 上記irritate と同義ですね。 -
2025.09.04
共テ英語リーディング令6・追試を解く88
一緒に解き直しをしましょう。共テまで4か月以上あります。2次試験とともに並行してやるにも、たっぷり時間があります。頑張れ! 大問5の問題文、単語チェックをしています。ごめんなさい、前掲で、1段落目、と書いてしまいましたが、3段落目に入っています。 ✅left 〖leave〗少し戻ってしまいましたが、また出ています。I had left my travel pouch somewhere, 9/2に掲載していますが、この単語は、徹底的に辞書や教科書で用例を繰り返し読むようにしましょう。 ✅Buddha 仏陀、もう皆さん御存じかと。Buddhism, Buddhistも一緒に覚えていますね。世界三大宗教を中学地理で習いますね。英語でもすべて覚えておきましょう。私が思うに10年後には、中学の社会の教科書の人名、地名、出来事などは、英語表記を併記するようになっているのではないかと。高校はすでにそうなっていますね。 ✅be supposed to 動詞〖suppose〗は必ず覚えておきましょう。これと関連付けて覚えるよりも、be supposed toの形でそのまま例文と覚えてゆくほうがよいと思います。 -
2025.09.03
共テ英語リーディング令6・追試を解く87
一緒に解き直しをしましょう。 大問5の問題文、1段落目の単語などをチェックしています。 ✅struck strikeの過去・過去分詞形です。問題文では、Trouble struck.で出ています。〖strike〗を辞書で引くと、けっこうたくさん意味があります。ストライキをする、という意味もありました。野球用語はおなじみでなないでしょうか。〖strike out〗三振する、三振させる、です。 ✅urge 問題文では、Shinji urged me to think carefully~.とあります。urge + 目 + to do, この文型はいろんな動詞で見られるかと思いますし、学生の皆さんはとても慣れた形かと思います。 ✅impressed 前掲でfascinatedを書きましたが、I was impressed~.、これと同じ形ですね。この形、中学校の教科書にたくさん出ていますね。 ✅initiative initial, initiate, initiator まとめて覚えましょう。 ✅resolve 一緒に〖solve〗も覚えましょう。resolution, solutionも。 -
2025.09.02
共テ英語リーディング令6・追試を解く86
一緒に解き直しをしましょう。目標点を設定して頑張ってみましょう! 大問5の問題文、1段落目の単語などをチェックしています。 ✅I left everything up to Shinji. 〖leave〗の単語が出てきました。この単語、私の場合ですが、しばしば辞書を引きます。ここまで引くと、この単語が好きになってきます。この単語の例文を教科書や辞書やニュースなどで集めると、とてつもない量になりそうです。やってみようかなと考えています。〖up to〗これも辞書で引いてみるとおもしろいなと思います。 ✅destination この単語は調べることもないな、と思いながらも辞書を引きました。destine(動詞)の派生語のようです。この単語は知りませんでした。destinyも派生語のようです。be destined to do/for も辞書にありました。 ✅fascinate 覚えやすい単語でしょう。I was fascinated~、の受け身で使われることが多いような気がします。fascinating も一緒に用例を見ておきましょう。excited, exciting と使い方は同じですね。 -
2025.09.01
トライプラス国分寺駅北口校の冬期講習
トライプラス国分寺駅北口校の夏期講習は、7/1~9/1の期間で開講いたしました。期間中の開校時間は13:00~22:00、8/13~20を夏期休業としました。生徒一人一人が目標を持って、集中的な講習ができました。以下のような講習がありました。 ・共通テスト対策(英語、数学、物理、古文) ・小論文対策 ・英検対策(準1、2、準2、3級) ・中学入試対策(算数) ・都立入試対策(5科すべて、英語、数学、国語、理科、社会) ・数学検定対策(2級) ・内部進学対策(大学附属校、私立中高一貫校) ・英会話コース トライプラス国分寺駅北口校では、早くも冬期講習+入試直前講習の準備を開始しています。 【トライプラス国分寺駅北口校の冬期講習+入試直前講習】 ・期間 12/1(月)~2/23(月)国公立大学、私立大学の中期、後期日程受験がある場合は、延長します。 ・開校時間 13:00~22:00 (算数検定実施の場合は、14:45~) ・お休み 日曜日が原則お休み。必要に応じて開校します。★年末年始はお休みなし。 夏期講習よりも長い期間です。志望校合格を多く出せている理由はここにもあります。 -
2025.08.31
共テ英語リーディング令6・追試を解く85
一緒解き直しをしましょう。共テまでは4.5か月。対策時間はたっぷり。 大問5の単語チェックの続き。 ✅rather 前掲に紹介した文中に。would rather experience となり、would rather do は連語として覚えることが多いでしょう。experienceは動詞ですね。 ✅burst ✅anticipation 問題文の文をそのまま示します。I was sure that this experience would help me grow as a person, and my heart felt like it might burst with anticipation! 期待に胸がはりさけそうに、と。 ✅transportation 接頭辞のtrans-のある単語を一気に覚えてみましょう。 ✅acknowledge ~を認める、と覚えている生徒が多いでしょう。問題文もこの訳でよいとは思います。辞書を引いてみると、<好意・会釈など>に答える、<人>に(手を上げたり微笑むなどして)会釈を送る、あいさつをする、という意味もありました。問題文はこの訳がぴったりかと。 -
2025.08.30
共テ英語リーディング令6・追試を解く84
一緒に解き直しをしましょう。トライプラス国分寺駅北口校の生徒で、夏期講習を利用して、英文法の講座を取得した生徒がいます。生徒曰く、やってよかった、と。過去問を解いていて、読むスピードがあがり、読解力も上がったという感触を得ています。こうした実感を得ることで、ますます今後の自信につながってゆくのでしょう。 大問5の問題文、1段落目の単語などをチェックしています。 ちょっと長い文ですが、紹介しておきます。 He had agreed with me that we would not arrange detailed travel plans before leaving Japan, but rather experience the thrill of choosing what to do each day while we were in the country. ちょっと長いですね。問題文では3行あります。動詞のagreeに注目してください。agree with, agree toには慣れていると思います。agree+前置詞+(代)名詞+that節、この文型にも慣れておくとよいです。 -
2025.08.29
共テ英語リーディング令6・追試を解く83
一緒に解き直しをしましょう。 大問5の問題文、1段落目の単語などをチェックしています。 ✅companion 文脈から簡単にわかるかと思います。友達、ですね。我々が日本語としてよく使うのは、展示会などのコンパニオン、ではないでしょうか。辞書では、3番目の意味で、「付き添い、コンパニオン、ヘルパー⦅老人・病人などの話し相手・手伝いとして雇われる人⦆」とありました。これは名詞ですが、動詞もありました。 ✅be willing to do 覚えやすいように思いますが、辞書でも再確認しておくとよいです。日本語だと微妙なニュアンスに勘違いすることがあるかもしれませんので。 ✅consider この単語は頻出ですね。辞書で文型をしておくとよいです。そして、considerable, considerably, considerate, consideration, considering, 一緒に覚えましょう。以外に難しいかも。繰り返すことです。そして例文で理解するようにしましょう。 -
2025.08.28
共テ英語リーディング令6・追試を解く82
一緒に解き直しをしましょう。 大問5に出ている単語をチェックしています。 問題文の1段落目です。 ✅eagerly be eager to do の熟語はおなじみですね。問題文中、「熱心に窓の外をみていた。」、熱心に、と訳すと何か変に思えます。辞書を引くと「しきりに」という訳がありました。「熱望して」の訳もありましたが、これはますます変ですね。翻訳家さんなら、「ずっと窓の外をみていた」と訳すでしょうか。 ✅gaze gaze atでよく使うように思います。自動詞ですね。辞書には、gaze on, upon, gaze about, around, gaze into, gaze after a person、なども出ていました。 ✅ask him to be my travel companion という文がありました。ask +人+to be、3日前も同じ文型を書きましたね。askはしばしば辞書で引いて文型になれておくととても役立つと思います。 ✅be willing to do おなじみの熟語ですね。「喜んで~する」の訳が多いようですが、問題文ではちょっと変かもしれません。 -
2025.08.27
共テ英語リーディング令6・追試を解く81
一緒に解き直しをしましょう。 大問5に出ている単語チェックをしています。 ✅restless restがない状態、だから休めない、文中は、7時間のフライトの間、だから、ゆっくり休めなかった、という意味でよいのかと思いました。一応、辞書で調べました。ある辞書では、「<気持ちなどが>落ち着かない、そわそわした」、とかありました。「不安な」、もありました。「安眠できない」、もありました。問題を解くうえで、あまり重要度はなさそうですが。 ✅throughout よく使われるし、大丈夫ですね。ここでは前置詞。副詞でも使われますね。 ✅soon after よく使う表現で問題はないと思います。熟語として辞書に出ているかなと調べましたが、なかったです。が、こんな表現も見つけました。shortly after, not long after. ✅Next to me was my good friend Shinji, こんな文があります。これは「倒置」の表現ですね。文法書で「倒置」を見ると、おそろしくたくさんの表現がありますし、かつ難しい。しっかり勉強しておくとよいですよ。 -
2025.08.26
共テ英語リーディング令6・追試を解く80
一緒に解き直しをしましょう。共テを多く解いてきていると、気が付くことがあります。先に紹介した、問題文、 You have been assigned to read a personal essay~. そう、受動態が、あちこちあちこち出てきます。この文では、さらに現在完了形での文ですから、訳すのが難しくなるのでは。受動態、以外に訳するのが難しかったりするケースがあるように思います。日本語が母国語の人は英語を日本語で理解しようとするので、受動態を訳そうとすると戸惑うことが多いのではないかと思っています。英語圏の人たちは、受動態という意識なく使いこなしているように想像しています。何が言いたいのか、「慣れてゆくしかない。」と思います。それには、たくさんの英文に触れてゆくことしかないように思えます。そこには、「コツ」や「要領よく」や「効率」ということには無縁な世界が広がっているのでしょう。日本語もそうです。多く触れることが、最大の学習方法だと思えてなりません。 -
2025.08.25
共テ英語リーディング令6・追試を解く79
一緒に解き直しをしましょう。単語学習だけで、相当な時間を要しますが、これが英語力を強くしてゆきます。 大問5に出ている単語のチェックをしています。 ☑assign これは難しい単語かと思います。動詞です。動詞の場合は、必ず、辞書で「文型」を確認しましょう。何度も何度も繰り返してゆくと「文型」に得意になります。 ・assign A B 第4文型ですね。これは、assign B to Aにも書き換えられますね。これは第3文型。Aには人がきますね。Bには物・事がきますね。何かピントくる動詞が思い浮かびませんか?そう、giveですね。同じ文型をとりますよね。意味も類似していますね。 ・assign A to do 第5文型ですね。 名詞形のassignmentの意味を覚えると、動詞のassignの意味がよく通り、的確な訳ができるように思います。「(割り当てられた)仕事」、「宿題」、「任命」、「(日時、場所の)指定」 ☑graduate 問題文では動詞ではなく、名詞です。「卒業生」と訳しますね。「卒業」はgraduationですね。 ☑everlasting 覚えやすい意味でしょう。 -
2025.08.24
共テ英語リーディング令6・追試を解く78
一緒に解き直しをしましょう。 大問5の単語チェックをしています。前掲でassignを載せました。単語帳だけで単語学習をしていると、英語能力を伸ばすには限界があるように思えてなりません。もう一度、文を掲載しておきましょう。 You have been assigned to read a personal essay written by a graduate of your university. 単語帳の訳は、「を配属する;を割り当てる」だだ、これだけです。「エッセイを読むことを配属された。」、「エッセイを読むことを割り当てられた。」後者は分からなくもないですが、日本語としてどうですかね?そうです、単語を覚えてゆくのは、辞書が一番なのです。単語帳は、その入口で、どんな単語が入試に出ているのかを知るための情報源でしかありません。それよりも、教科書を読むことで、単語に出会ってゆくのが一番です。単語帳はできればなくてもよいかもしれません。よい例文がありました。The teacher assigned some homework to the pupils.、「宿題を課した。」ピッタリの訳ですね。 -
2025.08.23
共テ英語リーディング令6・追試を解く77
一緒に解き直しをしましょう。解き直しは、辞書を確認するだけで、とても時間がかかるものです。市販の過去問題集には、日本語訳が書いてあります。解き直しのときに、日本語訳を確認することがあるように思います。ただ、これは注意が必要です。ただ、日本語訳だけを確認する作業は、あまり英語力、速読力を上達させることができません。それを読んで、その場だけ分かったつもりになってしまうからです。問題集の日本語訳は、自力で和訳したあとに見るだけにしたほうがよいです。 大問5の単語チェックをしておきましょう。 ☑assigned これは、前段の状況を説明する文にある単語です。長らく、HPを読み続けていただける方は、覚えていらっしゃると思います。私は、前段の文は、読まずに解き進めてよいと、しばしばお伝えしています。時間節約のためです。読まなくても問題は解けますから。ここでは、you have been assigned to read ~、という文に使われています。受動態です。そして現在完了形です。assignは皆さんはどう覚えているでしょうか?市販の単語帳には、「を配属する;を割り当てる」と出ています。覚えやすい? -
2025.08.22
共テ英語リーディング令6・追試を解く76
一緒に解き直しをしましょう。まずは、過去問を、決められた時間内で解いてみることは必ず。ぶつ切りでやっては駄目です。大問が全部で6つありますが、一気に80分でやるようにしてください。それができる環境を作ってください。 大問5の問5の選択肢を細かくチェックしています。②、It is important to find a good travel companion.、なんだかこれは正解にも思えますよね。よい友達と一緒に旅行できたわけですし。③、Personal development can happen through travel.、旅を通じて、成長してゆく、ということですね。②よりは、こっちのほうがふさわしく思います。④、Travelling can help us become better at planning.、旅が計画上手にさせてくれる、なんてことは書いていない、即座に消去ですね。この問題も簡単でしょう。問1, 問2が難しかった。あとは簡単。共テでは、こんなのはよくあるように感じます。 -
2025.08.21
共テ英語リーディング令6・追試を解く75
一緒に解き直しをしましょう。トライプラス国分寺駅北口校では、共テの問題を大学入試センターのHPからダウンロードして、生徒にお渡ししています。本試験、追試験が3年分ありますから、6回分、出来るわけです。もちろんそれ以前の問題も持っていますので必要な生徒にはお渡ししています。 大問5の問4,選択肢の④は、was thinking of visiting the country again、気持ちの中ではそう思っているのかもしれませんが、行きたいとか、行きたくないとかは全く書かれていないです。問3, 問4は、簡単でしたね。 問5は「What kaita learns after his trip?」、これの答を選択肢から選ぶものです。 ①Imagining our ideal self is helpful for travelling. 何だか意味不明ですかね。理想の自分を想像することが旅に役立つ、と訳してよいのでしょうか?筆者が8段落目に割と長く最後のまとめをしていますが、旅から学ぶものはあっても、旅に役立つ、とは書いていないですね。 -
2025.08.20
共テ英語リーディング令6・追試を解く74
一緒に解き直しをしましょう。勉強時間をたっぷり確保することです。そうは言っても、時間が足りない、との声は多いです。時間不足を補うものは何か、集中力です。効率のよく能力をあげてゆく参考書などはありません。ネット情報なんかをみて、そうした幻想をいだくようにならないでくださいね。トライプラス国分寺駅北口校での個別指導の授業は、能力を高めてゆくためのひとつの手段です。実際に偏差値が30以上がった生徒もいますから。高2の3学期に偏差値が30台の生徒が、共テ本番で197点取っていますから。40近く上げていますよね。 大問5の問4の選択肢を細かくチェックしています。大問3と同じく、②を読んだ時点で、正解を選べます。簡単に、と思います。思い切って③、④は読まずに進んでもよいと私は思います。しかしもしかして、と心配になりますから、たいていの受験生は、チェックしますよね。③、was starting to accept different sides of a person、仏像を異なった角度から見て、表情が違うととらえた、と3段落にありますが、そんなことではないですよね。 -
2025.08.19
共テ英語リーディング令6・追試を解く73
一緒に解き直しをしましょう。共テで最も求められる速読力、どうやって高めれる?単語と文法しっかり身に着けること、とよく聞きます。結局時間をたっぷりかけることが必要なのです。解き直しをたっぷりやることでも単語力、文法力は高まりますね。 大問5の問5、Keita bought the figure for himself. This implies that he □. □に入るものを選ぶ問題です。7段落目に、出発前の空港の土産屋で、仏像を買ったと書いてありますね。なんで、それを買ったのか、を選ぶ問題です。①tried to change his relationship with his friend、友達と気まずくなったことが4段落に書いてありましたが、仏像を買うことと友達関係を変えたいということは関係ないと思います。即座にこの選択肢は削除できると思います。②wanted to remember what he did in the temple、すぐにこれが正解だと分かるのでは。3段落の後半に寺の仏像を見て感じたことが書いてありますね。もちろんダイレクトに7段落に書いてありますし。 -
2025.08.18
共テ英語リーディング令6・追試を解く72
一緒に解き直しをしましょう。解き直しを繰り返すことで、読解力は確実に増すはずです。共テでも何でも、過去問を何度も読むことです。これは信じてやってみてください。そんな時間はない、という生徒、だったら、高い得点を取れる生徒は、どんなトレーニングをしているのでしょうか?よ~く考えてください。 大問5の問3の続きです。選択肢②を読んで、これが正解、とすぐに分かると思います。簡単な問題もありますね。で、その先の③と④はもう読まなくてよいのか?そう、読まずに次に進みましょう。しかし、心配ですよね。選択肢③、tried to change his bad memory into good one、悪い思い出を良いものに変えようとした、ということですね。エッセイ中に悪い思い出は書かれていますが、それを良いものにしようとは書いていないと思います。選択肢④、wanted to communicate with foreign people、外国の人と交流したい、とは思っているとは思いますが、書いてはいませんね。 -
2025.08.17
共テ英語リーディング令6・追試を解く71
一緒に解き直しをしましょう。英語のリーディングを解いて感じることですが、他の教科も解答の選択に迷わせるような点は、共通しているように思います。こうこうこうだから、これが正解、これは不正解、という理由づけ、なかなか本番で判断するのが難しく作問しているように思えます。 大問5の問3です。Keita helped a traveller. This shows that he □. □に正しい文章を入れる問題。選択肢①had improved at reading maps、地図が見づらくて困った、とあるだけで、読み取りの力を磨こうなどとは書いてないです。選択肢②remembered the promise he had made、2段落に、困って助けてもらった旅行者が、お礼はいいよ、他の困った旅行者に親切にしてあげて、とあります。簡単に選べるように思います。共テに限らず、正解が見つかったら、以降の選択肢は読まずに思い切って進んでも良いように思います。しかし、受験生の心理は、いちおうすべての選択肢を確認しておきたいものですよね。 -
2025.08.16
共テ英語リーディング令6・追試を解く70
一緒に解き直しをしましょう。 大問5の問2を見ています。選択肢の④、He relates to the feelings of others to cheer them up.と。6段落目に、He showed this empathy、とあり、これが当たるのかな、と思います。選択肢の⑤、He respects the opinioins of people around him.、1段落目、筆者が旅行仲間に選んだ理由を書いてあります。He was always willing to listen to others and consider their ideas.、と。3段落目、He took the initiative to resolve the situation.、選択肢の③は、ここに書かれてあると思います。 該当する表現が問題文中から探し出せねばならない問題です。それを順番に挙げていかねばならず、そして、余計な選択肢がひとつあることで、とても難しく感じます。速読力が試される試験で、限られた時間内で解かなければならないので、なおさらです。 -
2025.08.15
共テ英語リーディング令6・追試を解く69
一緒に解き直しをしましょう。共テまで5か月。受験科目は多いですが、過去問を多く解く時間はたっぷりあります。焦らずとも大丈夫。 大問5の問1は、嫌な問題でした、私には。すらすら解けた生徒もいるのでしょうが。問2は、旅行仲間の変化を時系列で表す問題です。またいやらしい問題ですね。変化は4つなのですが、選択肢は5つですから、余計なものが一つあるのですね。またまた、迷わせる問題ですね。 選択肢①He displays his negative emotions.、4段落目に友達が急にしゃべらなくなった、とあります。筆者は友達がいらついている、と感じた、と書いています。選択肢②He gets angry at what others say to him.、友達はいらついていますが、他人の行ったことに怒ったとは書いていないように思います。どうもこれが余計な選択肢のようです。選択肢③He is reliable and shows leadership.、1段落にHe was always willing to listen to others and consider their ideas. と。 -
2025.08.14
共テ英語リーディング令6・追試を解く68
一緒に解き直しをしましょう。解き直しをすることで、自分の足りなかったことを発見できるものです。そうして実力アップができるものかと。 大問5の問1。選択肢の③、He refuses to talk with other people.、たくさん他人とお話はしていますよね。ありえない解答ですね。選択肢の④、He welcomes adventurous experiences.、と。問題文では筆者のなさけない姿が描かれており、一見、冒険心のあるように思えないのですが、1段落目にスリルのある経験が人として成長をさせてくれる、なんて書いていますから、これは正解に思います。選択肢の⑤、He willingly helps local people.、と。これは正解だな、と思いました。が、local、とありますね。現地の人々で、よそからきた観光客ではないのですね。筆者は困った人を手助けしたことが文中では書いてありますが、現地の人を手助けしたことはどこにも書いてありません。でも、心優しい人だと感じますから、正解だとついつい思ってしまいます。選択に迷わせるように作っていると感じます。 -
2025.08.13
共テ英語リーディング令6・追試を解く67
一緒に解き直しをしましょう。解き直しに時間をかけることで、共テが求める速読力は高まってゆくはずです。 大問5の問1。やっかいな問題だと感じましたので、こういうのに慣れてゆくためにも、しっかり分析しています。筆者が困った、という様子を表現している文章を順番に探しています。6段落目、I made me feel a little down because~. 、とあります。これは困ったというより、友達が6つの場所に行ったところ、たった2つしか行っていないことに落ち込んでいるだけですね。7段落、8段落は、筆者が困ったことの記述はないです。今一度、⓵の選択肢、He can be at a loss in difficult situation.、です。みんな誰しも、そうなるように思いますし、筆者が困った場面が数か所書いてあります。いぶからずに、正直にとらえて正解とするのが良いのでしょうか?結局、消去法を利用して、やっぱりこれが正しい、とマークシートに印をつけました、私は。 選択肢②、He likes to plan and act individually.、です。友達と一緒なので、これはないな。 -
2025.08.12
共テ英語リーディング令6・追試を解く66
一緒に解き直しをしましょう。本番試験は初見で、解き直しをじっくりすることが役に立つのか疑問に思う生徒もいるかもしれません。解き直しで熟読する作業の繰り返しが、少しずつ上達してゆけるものと思います。 大問5の問1。文脈から推測できることを答えさせるような問題に感じます。ストレートに書かれていない状況を読み取ることは難しいと感じます。前掲の続き、筆者が困った状況の記述を探しています。4段落目、~we were confused.とあります。目的地に到達するのに、地図がわかりにくく混乱した、と。いやあ、誰でも混乱しますよね。4段落目にまた、I felt a little hurt, なんてあります。旅行のパートナーが不機嫌になったことでそうなったようです。このパートナー、勝手に不機嫌になるなんて、自分勝手な奴だと思います。ともかく、旅先で友達と気まずくなることは誰にもあることで、筆者だけが困ってしまうことではないように思いますが。5段落では、困っている人を助けたことが書いてあります。筆者は困るどころか、そんな人を手助けできる人で、困難な状況に困ってしまう人ではないと思えます。 -
2025.08.11
共テ英語リーディング令6・追試を解く65
一緒に解き直しをしましょう。解きながら思いますが、多くの英文に触れ続けることで、英語力は上がってゆくのかと思います。共テの過去問を多く解いてみることでも共テ対策のみならず、英語力UPは期待できるように思います。 大問5の問1、どうして私が迷ってしまったのか、探ってみたいと思います。 選択肢①He can be at a loss in difficult situations. 「at a loss」を連語として覚えておかなければ、いけませんね。「can」も大事かと。ただ、「~することができる。」の意味だけではないですね。これが問題文にどう表現されているのか、探してみました。いやあ、本当にダイレクトに書かれていないと感じます。2段落目、We have no idea how to get transportation into the city.どうしてよいか困っているのですね。しかし、誰でも始めての海外旅行ではこんなことで困ることはあるように思います。3段落目、~I was in a panic. 財布がないので、慌てた、とあります。誰でも財布をなくしたとなるとパニックになりますよね。 -
2025.08.10
共テ英語リーディング令6・追試を解く64
一緒に解き直しをしましょう。第5問まできました。問題文はまるまる2ページ。次のページに問題文を要約したメモがあり、ところどころが空欄となっており、それにふさわしい答を埋めてゆくようになっています。 けっこう難しく感じました。問題文は大学生の個人的なエッセイです。海外旅行をしたことを書いています。なんだかちっとも面白い話ではないな、と思いました。どこの国に行ったのかも明記されていません。仏教のお寺に行ったと書いてあるので、そして、7時間のフライトとあるので、タイあたりなのかなと思いました。設問から見てゆきます。 問1 筆者の特徴を選択肢から2つ選ぶ問題で、2つとも合っていないと正解にはなりません。私は時間がないにもかかわらず読み直しをしてしまいました。選択肢の文が問題文中のどこに書いてあるのかを探すのに苦労しました。選択肢の文がそのまま問題文中に書かれているわけではないところが難しい問題になっています。どこに書いてあるのだ、とイライラしてきます。 -
2025.08.09
共テ英語リーディング令6・追試を解く63
一緒に解き直しをしましょう。解き直しでは、単語を辞書で引くことで、語彙力強化につなげてみましょう。 大問4に出ている単語チェックの続き。 設問文に出ている単語に進んでいます。 ☑forbid 前掲、prohibitで一緒に覚えるようにお願いしました。 ☑swing 8/6に掲載しています。問4の問題にも出ている単語ですが、私は意味が分からなかったのですが、設問の②が正解だとすぐに分かったので、③の文中のswingsが分からなくても、読まずに済んだので解くに何ら影響がなかったです。 ☑interfere スポーツ用語で使われるinterference、日本語でのインターフェアを知っている生徒も多いように思います。意味もここから簡単に類推できるように思います。アクセント、発音は大丈夫ですね。 -
2025.08.08
共テ英語リーディング令6・追試を解く62
一緒に解き直しをしましょう。解き直しのときには、関連学習を出来るだけ多く取り入れましょう。英語の場合は、単語で、語彙力の強化を。 大問4に出ている単語チェックの続き。 前掲でsqueezeを調べました。英英辞典も調べてみました。そこには、野球のスクイズの説明がありませんでした。そのかわりではないのですが、イラストで、次の単語が示してありました。 ・squeeze ・squash ・crush ・press ・crumple ・wring 手や足を使った動作なのですが、とても難しいものですね。 ☑Watch out! これは塾にも、このまま出ていますね。日常的にしばしば使うのかと思います。 ☑get into trouble 簡単に意味は分かりそうですね。be in troubleの連語も覚えましょう。 ☑prohibited 海外旅行したときには、これを書いた標識や看板など多く見るように思います。一度見たら忘れない単語ですから心配ないとは思いますが。知らない生徒は今覚えておきましょう。将来、捕まったり、罰金を取られないためにも。forbid, prohibit, ban、一緒に覚えましょう。 -
2025.08.07
共テ英語リーディング令6・追試を解く61
一緒に解き直しをしましょう。前掲では、鉄棒、ブランコという誰もが知っている用語を調べてみました。知っておかなくても、共テの問題を解くに影響はないとは思いますが。 大問4に出ている単語チェックの続き。 ☑do janken これは日本語ですよね。英語の辞典に出ているか調べて見ましたが、塾に置いてある辞書には、出ていませんでした。和英辞典には出ていました。じゃんけんは日本から世界に広まったと説明されていました。英語では(the game of) rock-paper-scissors。 ☑squeeze 野球の用語もありますが、私は野球用語ばかりで使っていましたから、他の意味を覚えるのに苦労しました。辞書を引いては忘れ、引いては忘れ、の繰り返しでした。夏の甲子園大会の最中です。この単語が毎日のようにテレビ、ラジオから聞こえてくるように思います。アメリカの大リーグの試合では、あまり聞かないような気がします。大リーグの監督は、これの作戦があまり好きではないのですかね? -
2025.08.06
共テ英語リーディング令6・追試を解く60
一緒に解き直しをしましょう。解き直しは、ただその問題が解けるようにするだけでなく、今回のように単語や文法が出来ているかを再確認してみることも大事でしょう。 大問4に出ている単語チェックの続き。 ☑table テーブル、卓、は説明するまでも。「表」、「目録」の意味もありますね。問題中に、活動内容が表に示されていますね。この表のことですね。time-table はよく使っていますから、問題ないとは思いますが。 ☑behind これも大丈夫ですね。問題文では前置詞。副詞もあります。 ☑swing 問題文では、next to playground swings とあります。これ、私は、辞書を引くまで意味を勘違いしていました。swing, ぶらんこなのですね。知っているようで知らないものです。鉄棒、何と言うのだろう、と思いました。a horizontal bar でした。exercise[perform] on a horizontal barの用例が出ていました。そうか、on がないといけませんね。では、すべり台は?a slideでした。ジャングルジム、これはそのまま、a jungle gym。 -
2025.08.05
共テ英語リーディング令6・追試を解く59
一緒に解き直しをしましょう。 大問4に出ている単語チェックをしています。 前掲、handout、英英辞典には、一番目の意味として、1. food, money or clothes that are given to a person who is poor と。2. money that is given to a person or organization by the government, etc., for example to encourage commercial activity. 3番目が、いわゆるよく使用される、handoutの意味。4番目もあります。4. a document that is given to students in class or people attending a talk, etc., and that contains a summary of the lesseon/talk, a set of exercises, etc.4番目の意味のものも共テでは、よく出るように思います。 理解できている単語でも、今一度、辞書を引くこと、大事。 -
2025.08.04
共テ英語リーディング令6・追試を解く58
一緒に解きましょう。問題形式を理解しておくだけで、得点UPが狙える試験ですよ。 大問4の問5は、フリスビーを投げて競うゲームで、そのゲームをするためのレイアウトのイラストで正しいものを選ぶ問題です。まず、会場のセントラルパークには、真ん中に大きな木があります。これは問題文にも書いてあるのですが、イラストのすべてが真ん中に描いてあるので、考える必要はありません。コーンをスタートとゴールに配置するとあります。これで、選択肢の①と③は消去できます。ゴールのコーンは、子供用プールとフラフープの間に、と問題文にありますから、簡単に選べるはずです。 大問4に出ている単語をチェックしておきます。 ☑description 大学入試をするのに、これの意味が分からないのは、相当に単語力が低いと思ってください。単語トレーニングをやり直しましょう。prescription, subscription, conscription, ascription,ついでに覚えましょう。 ☑handout 共テには、毎回出るように思います。もう大丈夫ですね。 -
2025.08.03
共テ英語リーディング令6・追試を解く57
一緒に解きましょう。徹底的に対策して100点満点をねらいましょう。 大問4の問4、これも何度か読み直しが必要で、時間をとられてしまうように思います。こんな問題です。 Because [27], let's switch activities [28]. 27と28に入る文章などを選択肢から選ぶ問題です。27は簡単なはずなのですが、構成されている3つの文章のうち、3つ目の空欄がところどころにあるMemoの中に答えがかくされているので、それに気が付きにくいように思います。このMemoは、問題の一部のようなものなので。28の選択肢は、Activitiesが記載されている一覧表を見なくてはなりません。会場のひとつ、セントラルパークは、音楽を鳴らすことが禁止されており、会場変更しなくてはなりません。よって、もうひとつの会場のスポーツセンターでの活動と入れ替えなくてはなりません。この問のいやらしいところは、問題文を読むだけでは解けません。設問文にある、活動ナンバーをまずひとつ確定さえ、残りは消去法でやるしかないのです。パズルのような問題で、時間がとられてしまいます。 -
2025.08.02
共テ英語リーディング令6・追試を解く56
一緒に解きましょう。高1、高2生も始めてみましょう。早くから対策して損はないです。 大問4の問3続き。 前掲、D. 10枚の音楽CD、これは誤りではありませんが、問題文を読むと#2 Limbo Danceと#5 Musical Hula Hoopsで音楽を流しますから、2枚以上あれば、誤りではないのです。選択肢が2 discsでも100 discsでも誤りではありません。どこかに枚数が分かる記載がないかな、と読み直しをしてしまいがちです。 E. 10 hula hoops これの記載について読み直しをしていると、重大なことに気付きました。D.のdiscsは、音楽CDではなく、投げるflying disc、つまりフリスビーであっても良いのです。このゲームは、1チーム10人が同時にフリスビーを投げてスピードを競いますから、10枚必要なのです。それで10 discsの選択肢にしているのかもしれません。D.の選択肢は音楽CDとフリスビーのどちらでとらえても、10個という数は誤りではないのですね。でも両方合わせて、ということならば、Dも誤りになりますが。解き直しでしっかり読むと余計に混乱させられます。 -
2025.08.01
共テ英語リーディング令6・追試を解く55
一緒に解きましょう。過去問は出題形式に慣れるために必ずやっておくべき。形式に熟知するだけで、偏差値50くらいの生徒なら、10点~20点は差が出てくるはず。 大問4の問3続き。 B.を選んであとは見なくともよいのです。しかし、本番でなかなかそうはいかないのかもしれません。 ★対策: 正解に確信が持てれば、続く選択肢は確認しなくてよい。これは、過去問等でトレーニングを積めば積むほど理解できるようになるはずです。 私は、C, D, Eが正解かどうか、確認してしまいました。結果的に、時間を使いすぎる羽目に。 C. 2 sponges これは、「#6 Sponge Pass」で、使われるとすぐに分かるでしょう。 D. 10 discs これです。時間を浪費してしまうのは。discsとは、音楽CDのことですね。「#4 Flying Disc Throwing」に使うdiscの可能性もあります。「#5 Musical Hula Hoops」では、音楽を流します。これに使う音楽CDと思います。迷ってしまうのが、10 discs とあるので、必要数を確認しようとしてしまいます。これがどこにも書いていないのですね。 -
2025.07.31
共テ英語リーディング令6・追試を解く54
一緒に解きましょう。解き直しは、80分ですべて解いてから。分割して解かないほうが良いです。 大問4の問3の続きです。もう一度、設問を振り返ります。 There is an error in the Additional Materials for New Activities. Which do you need to change? 誤っているものが一つあるので、それを選べという問題。 A.は前掲で。これは正しい。次はB. 2 buckets バケツ2個。バケツは、「#6 Sponge Pass」のActivityで使用されます。5人が2列になってやるゲーム。バケツをその列の前後に置くとありますから、4個必要です。これが誤りですね。ここでマークシートに記載して、残り、C, D, Eは確認しなくてよいことになります。でも実際は、不安ですよね。私も確認をしました。その分、時間を多く取られてしまうことになりました。次に掲載しますが、本当に、時間を使わせるような選択肢になっています。共通テストは、このような余計な時間を取らせるようにも作られていると感じます。 -
2025.07.30
共テ英語リーディング令6・追試を解く53
一緒に解きましょう。解き直しは、80分間、全部解いてからですよ。 大問4の問3続きです。 A. 1pole とあります。Limbo Danceで使われるのは読み取れますね。これ、大きなヒントがイラストにあります。2人のスタッフが1本のポールを持っています。イラストから気づかずとも、ポールが1本あれば、出来ますから簡単にわかりそうです。ちなみに、皆さんはLimbo Danceを知っていますかね。これを知らないと難しくなるかもしれないですね。私はまさに最近、これに触れることができました。NHKの夜ドラで、キャンプを舞台に、しばしばLimbo Danceをやっているからです。気になったので、limboを英和辞典で引いてみました。2つの単語として表記されています。1つ目は、1. 不確実な状態 2. 〖キリスト教〗地獄の辺土≪地獄と天国の中間にあり、キリスト降臨以前の善人や洗礼を受けなかった幼児の霊魂がすむ所≫ 2つ目が、リンボーダンスの意味。 知らなくても大丈夫でしょう。入試の得点にからんでくるような単語ではないように思います。 リンボーダンス、調べてみました。トリニダード島で始まったそうです。 -
2025.07.29
共テ英語リーディング令6・追試を解く52
一緒に解きましょう。ひとつお願いがあります。こちらの掲載を読む前に、過去問を指定された時間ですべて解いてください。そして、解き直しをしましょう。大問ごとに区切って、やってゆく方法はよくないです。時々、学校の授業で、夏期講習、共テ対策授業と称して、そのようなやり方をしていることがあるように見受けられます。限られた数しかない過去問です。そのようなやり方をする講座は受けないほうがよいです。決まった80分間でやりきる、というのが試験ですから。 問3 イベントの新しくやる企画で必要な道具が5つ示されており、そのうち、ひとつが誤りで、それを選択する問題です。これも難しいように思います。私の場合ですが、何度も読み直しをしましたし、ダイレクトに問題文に書かれているわけではないので。いじわるな問題のようにも感じます。具体的に選択肢を見ますと、 A. 1本のポール B. 2個のバケツ C. 2個のスポンジ D. 10個のディスク(音楽のCDです。) E. 10個のフラフープ どれも、ダイレクトに問題には書かれていません。問題文を読んで数を導き出すしかないのです。順番に記載箇所を確認してゆきましょう。 -
2025.07.28
共テ英語リーディング令6・追試を解く51
大問4、続きです。 問2 これは難しいのでは。イベントを運営するためのボランティアがまだ足りておらず、最低何名必要ですか、という問題です。ボランティアに必要な人数が、イベント準備のための最初の問題文に記載されています。イベントの2度の休憩時間に2人必要、そして、イベントの1, 3以外も2人必要だと。イベントは、6つあります。1と3以外、というのがいやらしい問題のように感じます。この問題を解くに、まず、P.25のWhich is the best option for □?⓵4 ②5 ③6 ④7 を見て、前のページをめくって、Find at least □ more volunteers because we're short of them.を見て、さらに、そのページの上にある、ボランティアをする人が決定している表を見なくてはなりません。もちろん、最初の文のボランティア人数の記載も、もう一度めくって見なくてはならないように思います。かなり時間を使うのではないでしょうか。 ★対策: パズルのように、読んだ問題文を見返さなくてはならないように思います。こんな問題が出るのだ、と練習するしかない。 -
2025.07.28
熱い夏期講習!国分寺駅北口校
今年も熱く生徒たちは夏期講習にがんばっています。@国分寺駅北口校! トライプラス国分寺駅北口校の夏期講習は、7/1(火)~9/1(月)です。途中夏休み、8/13(水)-20(水)。 特に受験生、そして、高校2年生にも、この夏、勉強量を増やすよう発破をかけています。こう言っています。夏期講習でがっつり勉強した生徒は、秋からの勉強時間も多く出来る、そして、入試直前の冬休みと入試までの期間も。トライプラス国分寺駅北口校は、実は冬期講習+入試直前講習のほうが期間が長いです。今年は、12/1(月)~2/23(月)の予定です。年末年始のお休みは無しです。ぶっ続けます。もちろん、国公立大学の中期、後期試験を受験する生徒がおれば、延長します。講習期間中は、13:40~授業可能。開校時間が13:00~22:00です。自習での環境が良いと、皆さんの高い評価をいただけています。合格実績がそれを裏付けていると思います。稼働時間は、近隣他塾には負けていないでしょう。東京大学を目指す生徒から、学校の成績が振るわない生徒まで、幅広く対応しています。勉強を頑張ってみよう、という生徒さんたちには、とても良い塾のはずです。 -
2025.07.27
共テ英語リーディング令6・追試を解く㊿
大問4を解きます。一緒に解いてゆきましょう! これも設問を含め5ページ分も。問題文は3部構成。 1. イベント情報の掲載 2. Activitiesの紹介 3. イベントのボランティア用のメモ 私は、設問を読みながら、ページをめくって後戻りすることを何度も繰り返しました。これはとても面倒な作業です。そして、ただでさえ、限られた時間で解かなくてはならないので、ページを何度もめくっていると時間がどんどん取られてゆくように感じてきてあせってしまいます。 3. のメモのところどころに24~29の番号が書かれた□があり、これらに適切な解答をあてはめてゆく型式です。最後の2ページ分に設問が問1~問5までありますので、ページを行ったり来たりめくってゆかなくてはならないのです。 ★対策: このような面倒な作業に慣れておかなくてはなりません。過去問や模試や共テ用問題集をたくさんこなしましょう。 問1 イベントの準備を何時に開始するか?これは意外に難しいのかもしれません。「Set-up 9:00am」なのですが、準備開始時間なのか、準備完了時間なのか、私は迷いました。2択のどちらかなのですが、見事に間違えました。 -
2025.07.16
共テ英語リーディング令6・追試を解く㊾
大問3のBの単語等のチェック、続きます。 ☑rug 今や日本語になっていてほとんどの人が知っているし、国分寺駅の駅ビルのお店でもたくさん売っているはずです。〇印〇品でも売っているはずです。私の学生時代には、まだ今のように使われておらず、そして知らない単語だったと思います。 ☑calm down クリスティナさんがいらいらしたことに、calm downしてね、ということですね。簡単ですね。 ☑try not to get so angry notが入ると難しいと思う人も多いのでは。(私も。) ☑Tomorrow is another day! とっても良い言葉ですね。 ☑She is very organised person. 問3の選択肢にあります。organise ちゃんと辞書を見ておきましょう。ちなみに、organizeのつづりもあります。 -
2025.07.15
共テ英語リーディング令6・追試を解く㊽
大問3のBの単語等のチェック、続き。 ☑I've had to think これの文法も大丈夫ですね。これの全文、I've had to think carefully about the order I'm having stuff delivered. ☑having stuff delivered これの文法も大丈夫ですね。staffの単語もありますが、それぞれ、意味の違い、発音は理解しておいたほうがよいです。 ☑fridge refrigeratorの短縮語ですね。知らずとも推測できますね。 ☑settle 問題文中の意味は簡単でしょう。ただ、この動詞、いろんな意味があるので、辞書を丁寧に見ておいたほうが良いです。settlementの名詞も入試ではよく出てくると思います。 ☑annoy 必ず高校生の英単語帳には出ています。いやいや、今や中学生単語となっています。本文ではannoyedで。気持ち・感情を表す単語、中学教科書にまとめて出ています。全部覚えましょう。tired, surprised, scared, excited, shocked, worried, bored. -
2025.07.14
共テ英語リーディング令6・追試を解く㊼
大問3のBの単語等のチェック、続きます。 ☑agency 問題文中では、apartment agencyです。お引越しの話題で、不動産屋だとすぐにわかるでしょう。以下も覚えておくとよいかも。 ・an insurance agency ・an advertising agency ・a travel agency ・a car rental agency ・a news agency ・a real estate agency 問題文のapartment agencyはこれと同義ですね。 ・CIA the central Intelligence Agency ☑I'd wanted to move in this Wed., but .... これは、文法的な説明はできますか?解き直しでは、こうした文法のおさらいは分かっているようでもしておいたほうが良いと思います。 ☑I'll be getting my key on Fri. 未来進行形ですね。簡単なのでしょうが、文法書でおさらいしたほうが良いと思います。速読力UPにきっと役に立ってくるはずです。 -
2025.07.13
共テ英語リーディング令6・追試を解く㊻
大問3のBの単語等のチェックです。 ☑post これも前段説明の文です。設問文中にもあります。問題文中では、respond to their posts で使われています。文脈から意味は簡単。多く使われる意味は、郵便ポストや郵便物ですかね。postを辞書で引くと、1,2,3と3つの単語がありました。2は地位、等。3は柱、杭、支柱など。ピアス(の留め具)というのもありました。発音ですが、大丈夫でしょうね。[poust](oにアクセント)。ここでの意味は、投稿した日記へのメッセージに対しての返信をするということですね。 ☑dorm dormitoryの略式です。文脈から読み取れるので、覚えておく必要もない単語かと。将来、留学しないとも限らないので覚えておいてもよいですね。発音も似ていますが、違う単語のdomeもありますね。Tokyo Domeのdomeですね。the Atomic Bomb Dome、中3の教科書、Lesson3にはこれのお話がありますね。 ☑the day before yesterday 問題ないですね。分からない人は勉強不足すぎ。「あさって」、言えますね。 -
2025.07.12
共テ英語リーディング令6・追試を解く㊺
大問3のB、続き。 問3は、単純に正誤を問う問題で、誤りを選択する問題です。簡単とは思いますが、共通テストでのこのような問題の場合、問題文の記載を直接的に選択肢に記載されておらず、記載内容から判断させるように作問しています。具体的に。 ⓵誕生日は彼女にとって重要。 ②彼女はしばしばさみしがる。 ③彼女はとても計画的な人。 ④彼女はとてもお金に対して注意を払う。 ⓵だけは、ダイレクトに書いてありますが、②~③は、このように書いた文章はなく、彼女の日記にこう書いてあるから、計画的なのだな、お金使いに注意しているのだな、と推察させるような問題となっています。共通テストに見られる特徴と言って良いかと思います。 単語チェックをしておきます。 ☑You have been asked to keep an online diary available ~.単語でなく文章ですが、文法をしっかり勉強した生徒は難なく読めるはずです。ちなみに、前段説明の文で読む必要はないのですが、解き直しに学習用として示しました。最も学習してほしいことは、askの文型です。体に染みつかせるくらい好きな例文を暗記しておくと良いです。 -
2025.07.11
共テ英語リーディング令6・追試を解く㊹
大問3のB、続き。 問1は、出来事を時系列に並べるのですが、単に並べるのではなく、全部で7つある出来事のうち、3つを取り上げて、最初に起こった出来事、最後に起こった出来事がどれかを当てる問題です。具体的に示します。 ⓵、③、④の最初に起こったのは? ②、③、⑤の最初は? ⓵,②、⑥の最後は? ④、⑥、⑦の最後は? 上記の4つすべてが合っていないと得点できません。私は、⓵~⑦それぞれに日付を記載してみて、それで解きました。注意すべきは、最初はという問と最後はという問があることかも知れません。設問を読んで、問題文の読み直しは必要なように思います。私もそうしました。読み直しをしても、大した時間はかからないはずです。 問2は、3月23日の日記に対しての友達の返信としてふさわしくないものを選べ、という問題です。3/23は引っ越しの前日で、タンスが配達されるはずが、されなかった、それで、annoyedだと書いています。予定どおり進まなかったことに対し、お友達は、ざまあみろ、なんてことは決して言いませんよね。落ち着いて、明日は明日の風が、とか、何か手伝える?、とかが選択肢にあります。もう一つは、消去法でよいかと。 -
2025.07.10
共テ英語リーディング令6・追試を解く㊸
大問3のB、続き。 前段の説明文を掲載しました。読まなくても、問題を解くのに全く影響はないと、私は思います。皆さんも試してみてそう感じるはずです。特に、この前段説明の文はちょっとだけ難しく感じる生徒もいたのではないかと思います。こんな所で、考える時間を使っては時間の損だと思います。 前段文には、「on line diary」とあります。グループ間でやりとりするメールかと思えばよいのでしょう。ただ、前段文を読まずとも、お友達の間でのメールだと、問題文を読んでいるとすぐに分かるはずです。Diaryですから、日付がついています。5つほどあります。最後のものには、タンスと洗濯機の写真(問題ではイラスト)が添付してあります。タンスは両親からプレゼントされたもので、捨てるわけにはいかず、引っ越し先に運び込むようです。日記は引っ越しがもうすぐ、賃貸契約のお金を両親が送ってくれた、引っ越しの日程がいつで、新しい家具をそろえる予定、予定どおりいかなかったトラブルなどを書いてあります。設問の最初、問1では、その時系列を問う問題です。単なる並びかえではなく、真新しい形式でしょう。7つの出来事が選択肢にあります。 -
2025.07.09
共テ英語リーディング令6・追試を解く㊷
大問3のB、続き。 前段の説明文を掲載しました。読まなくても、問題を解くのに全く影響はないと、私は思います。皆さんも試してみてそう感じるはずです。特に、この前段説明の文はちょっとだけ難しく感じる生徒もいたのではないかと思います。こんな所で、考える時間を使っては時間の損だと思います。 前段文には、「on line diary」とあります。グループ間でやりとりするメールかと思えばよいのでしょう。ただ、前段文を読まずとも、お友達の間でのメールだと、問題文を読んでいるとすぐに分かるはずです。Diaryですから、日付がついています。5つほどあります。最後のものには、タンスと洗濯機の写真(問題ではイラスト)が添付してあります。タンスは両親からプレゼントされたもので、捨てるわけにはいかず、引っ越し先に運び込むようです。日記は引っ越しがもうすぐ、賃貸契約のお金を両親が送ってくれた、引っ越しの日程がいつで、新しい家具をそろえる予定、予定どおりいかなかったトラブルなどを書いてあります。設問の最初、問1では、その時系列を問う問題です。単なる並びかえではなく、真新しい形式でしょう。7つの出来事が選択肢にあります。 -
2025.07.09
共テ英語リーディング令6・追試を解く㊷
大問3のB、続き。大学の寮を出て、アパートでの一人暮らしを始める学生が出来事をブログに書いています。高校生がアパートを借りて一人暮らしをすることはほとんどないように思います。その前に、未成年なので、契約は必ず保護者様がするはずです。そうした意味で、経験のある私が読んで読みやすいのと経験のない受験生では読みやすさに違いがあるのかもしれません。 まず、私が読まなくてもよい、とお伝えし続けている前段の状況説明文の内容を念のため見ておきましょう。少し難しいと感じる生徒も多いのではないでしょうか。 You have been asked to keep an online diary available only to other students in the class, to follow at least on other student, and to respond to their posts. You chose to read Christina's diary because you are also thinking of moving into an apartment. -
2025.07.08
共テ英語リーディング令6・追試を解く㊷
大問3のBを解きます。 私は問題を解くときに、どのくらいの量なのかをチラッと見ることが時々あります。そしてたいてい思うことは、「長いな、この問題は。」です。よし、やってやるぞ、という気持ちではなく、解くのいやだなあ、という気持ちです。このような気持ちになる人は、いろいろ聞いている限りですが、少なくないように感じます。大問3のBは、設問を含めて4頁もあります。ちなみにAは2ページ。読んで解いてみると、以外にスラスラ解けました。解くにあたっては、毎度毎度ですが、冒頭の説明文は私は読みまんせんし、生徒たちにもそのように勧めています。今回は4行も書いてありますよ。私の音読スピードは遅い方だと思いますが、これを計測すると22秒もかかりました。私のように速読力に欠ける生徒ほど、少しでも時間稼ぎになることはやった方が良いと思います。問題文を量を確かめるときに、イラストがあると、理解度に少し役立つように感じます。今回は、たんすと洗濯機のイラストが。問題文は、筆者が日記のような記録です。大学の寮をでて、アパートの一人暮らしをすることが書いてあります。大学生からの一人暮らし、やってみると良いと思います。 -
2025.07.07
共テ英語リーディング令6・追試を解く㊵
大問3のAの単語チェック、続き。 ☑task おなじみの単語で、大丈夫かと思います。問題文を抜き出しておきます。 What do you do if it's just you? Finding a "table for one" to enjoy dinner can be a big task. [it]はsolo diningを指します。日本人には書けないような文かな、と感じます。さて、taskです。私はどこかで、job, work との違いを勉強した記憶があります。そこで辞書を見ました。8つ調べました。最後の英英辞典に発見しました。類義語として、duties, mission, job, choreです。workは、単語説明に、a piece of work .... とありますから、あえて列挙していなのかと思います。choreなんて単語は知りませんでしたが、ある辞書では、*マークひとつ(中学、高校学習語以外で高校生に必要な語)ついているので、覚えても損はないと思います。辞書の用例からして、日常生活で多く出てきそうで、共通テスト出題にはもってこいな単語かもしれません。 -
2025.07.06
共テ英語リーディング令6・追試を解く㊴
大問3のAの単語チェック、続きです。 ☑solo 題名がSolo Dining で、これについて語ってあるブログですし、この単語も日本語になっていますから説明も不要ですね。そうは言っても、辞書で調べました。発音ですが、[soulou]、アクセントは最初の[o]に。イタリア語が語源のようです。soloistの派生語もありますね。ソリストも日本語になっていますが、アクセントは[solouist]アクセントは同じく最初の[o]。違う辞書も何冊か見ることもあるのですが、「ソリストはフランス語 solisteから」とありました。イタリア語由来ではないのですかね?面白いものです。受験ではこんなことは出ないですから気にしないでおきましょう。関連語として、二重奏、duetの単語の記載のある辞書もありました。続けて、trio, quartet, quintet, sextet, septet, octet, nonetがありました。soloですが、形容詞、動詞もありますよ。 ☑common ここでの意味は問題ないでしょう。でも、辞書で引いてみるとよい単語と思います。語彙力はそうやって高まるものです。 -
2025.07.05
共テ英語リーディング令6・追試を解く㊳
大問3のAの単語チェック、続きです。 これも冒頭説明の文ですが、blogの単語があります。もう、誰もが知っている単語でしょう。私の学生時代には、この単語はおそらく辞書には出ていなかったように思います。辞書には、〖コンピューター〗や〖インターネット〗の表記がありますね。辞書には動詞の場合、「活用」が出ています。三単現のe, es, ~ingも含めて。blogには動詞もあり、過去形はbloggedです。現在分詞はbloggingです。動詞の変化も注意深く勉強しておいたほうがよいと思います。 ⓵規則動詞の作り方、edをつけるのが一般的ですが、そうでないものも覚えないと。 ②過去形の-ed の発音 3種類あります。 英作文、英検2次の面接などでは、きちんと覚えておかないと減点の対象になるように思います。 ☑frequently 簡単に覚えられると思います。発音も大丈夫ですね。 ☑uncomfortable comfortable の反意語ですし、簡単に覚えられると思います。 これら、最初の1文目にある単語ですが、この1文目に、関係代名詞が2箇所使われていますね。分からなければ、相当努力しないといけません。 -
2025.06.27
共テ英語リーディング令6・追試を解く㊲
大問3のAの単語チェックです。 前掲で挙げた文、2番目の文にtipの単語がありました。共通テストではかなり出てきます。日常生活ではよく使う単語のように思います。が、学校の教科書には出てくるものの、あまり注意が向かない単語のような気もします。 中学生用の辞書を引いて復習しておきます。まず、tipは、tip 1と tip 2 の2つの単語がありました。 tip の1:名詞です。(細長い物の)先、はし the tip of one's finger 指の先 イディオムがあるようです。 What's his name? - It is on the tip of my tongue. tip の2:名詞です。⓵チップ、心づけ ②アドバイス、(役立つ)情報、秘訣、コツ 動詞もあります。~にチップをやる 念のため、高校生以上用の辞書、研究社の辞書を見ました。tip は、1~5までありますよ。 生徒の皆さん、辞書を引いて意味を確認することは英語力を高めてゆくためには必須ですよ。なぜ、辞書を使わない生徒がこんなにも多いのだろう、と嘆くのは私だけでしょうか。国語もしかり、漢字。古文となれば、古語辞典さえ持っていない? -
2025.06.26
共テ英語リーディング令6・追試を解く㊱
大問3のAに出ている単語をチェックしておきます。 冒頭の説明文は読まなくてよい、と申しておりますが、こんな文でした。 You are staying by yourself in Sydney, Australia, and thinking of eating out. You are searching for tips and find a blog. ☑by yourself 意味は大丈夫かと思います。文法書で再帰代名詞は復習しておいたほうがよいかもしれません。これを勉強すると、文法書の同じSectionには、代名詞と限定詞、人称代名詞、itの使い方、指示代名詞、不定代名詞、とページをさいてあります。文法を軽視している生徒が少なからずいるように感じています。重箱の隅をつつくような入試問題は減りつつあるのでしょうが、文法書の隅から隅まで理解して覚えろ、とは言いませんが、もしもです、文法書の内容を徹底的に理解できたらどうなるでしょう。きっと読解力は高くなるように思います。共テで必要な速読力もきっと高くなるはずです。 -
2025.06.25
共テ英語リーディング令6・追試を解く㉟
大問3のA、問2の続きです。レストランのテーブルの配置図、それぞれに座っているお客の人数がかかれています。図が6つもあります。こんなに多いのも嫌になります。テーブルは、テラス席が3、ラウンジに9。座っている人数は、0人から4人、それぞれに。ブログの2段落目だけ読んで解けます。Before I went in, I could see diners eating alone on the terrace, … とあります。一人で座っているのですね。よって、テラス席のテーブルに2人以上すわっている図は、消去です。⓵、③、⑤が消えました。②、④、⑥が残ります。When I entered, in the lounge there were only couples and groups of guests. 図⑥を見ると、すべての席が一人しか座っていません。消去です。②を見ると、一人で座っているテーブルが2つもあります。一方④は一人で座っているテーブルはゼロです。ゆっくり考えると、簡単かもしれませんね。 -
2025.06.24
共テ英語リーディング令6・追試を解く㉞
大問3のA、続き。前掲は省略して書き出したので、これを読むだけでは正解はできません。問1の文には「従属節」があり、オーストラリア旅行前に、と書いてあります。そうです。旅行後に、次回のパリ旅行では、「一人ごはん」をしようと思う、とブログの主は言っています。 前掲の選択肢を見ると、 ⓵複雑な思いと心配 ②経験なし ③否定的 ④肯定的 これだけではまだ分かりません。続く文で答を導きだせます。 ②一緒に食事する人がいなかったから、と。ブログにこんなことは書かれていますか? ③一人での食事を断られてきたから、と。これも書いてない。 ④パリ旅行の経験から、と。この人はパリにはまだ行ったことがないです。 この説明では消去法的にやりましたが、⓵を読んですぐに正解だと選んだ受験生も多かったのではないでしょうか。 問2 これは難しいのではないでしょうか。私の場合、問題を見た瞬間に、「いやだなあ。」と感じました。6つの図が並べてあるのです。図は、レストランのテーブルにどのような人数で人が座っているかを示しており、正解を選ぶ問題です。レストランは、テラス席、ラウンジ席にわかれており、テラス席のテーブルが3、ラウンジ席が9あります。 -
2025.06.23
共テ英語リーディング令6・追試を解く㉝
大問3、問題文は簡単に思えましたが、設問の問1の選択肢の文も少し長め、問2がレストランの座席に何人すわっているのかの図の正解を選ぶもので、難しいかなと感じました。 問題文は、ある人のブログで、オーストラリアのレストランで一人で食事したことについて書いてあります。3段落に分かれています。 ⓵英語圏の国では、一人での食事はあまりない。 ②オーストラリア旅行で、一人での食事が増えていることに気が付き、やってみた。 ③スマホやSNSが広まって、一人で食事することの気持ちが変わってきたことに気が付いた。そして次回のパリ旅行で、一人での食事をしようと思う。 要約するとこんな感じです。 問1 the author ⓵had mixed feelings about solo dining and worred about finding a table just for himself ②had never experienced solo dining ③was negative about solo dining ④was positive about solo dining 省略していますが、こんな問題です。 -
2025.06.22
共テ英語リーディング令6・追試を解く㉜
大問3を解きます。AとBの2部構成です。これは令和6年度の追試験の問題です。令和7年度、これも問1,2と同様、問題構成が変わっています。2部構成でなく、一つだけです。過去問研究を徹底的にやり、時間配分を考えている生徒は注意したほうがよいかもしれません。 問1と問2しかありません。各3点、計6点。毎度毎度ですが、状況説明の前置きの文は読まなくてよいと思います。どんなのかを示しておきますが。 You are staying by yourself in Sydney, Australia, and thinking of eating out. You are searching for tips and find a blog. 「筆者は今、どこの国のどこの都市にいますか?」という質問はありえないと思います。だから、読む必要はありません。問題文を読み取れるかどうかが鍵ですから。 題名が、「Solo Dining」です。一人で食事することです。外食を一人でできるか否か、TV番組で何度か観たことがあります。一人で食事出来ない人、日本も含め、以外といらっしゃるようで。 -
2025.06.21
共テ英語リーディング令6・追試を解く㉛
大問2のBの問2、もう一つ難しい単語がありました。reluctant 。人の気持ちを表す形容詞なので、覚えやすいし、いったん覚えると忘れないと思います。この問題を解くにおいては、どれが正解かが簡単にわかりますので、feel reluctant to expand の③の選択肢は、意味がわからなくてもほおっておいてもよいのです。もうひとつよい覚え方があります。反意語willingとセットで覚えることです。 問3 正しいものを選ぶ単純な問題です。簡単です。 問4 また出てきました。opinionが太字下線付きになっています。大問2のAの問3にもありました。6/12, 13掲載も参照下さい。今回の問4では、意見か事実かで悩むことなく簡単に解けるはず。 問5 5つの選択肢があり、そのなかから2つほど最適な解答を選ばなくてはなりません。それだけで難易度が高くなるものです。消去法でやってゆくのがよいでしょう。groceries の単語が出てきますが、意味が分かっていれば、すぐに正誤が分かりそうです。やはり、中学のHere We Go!3年教科書に出ています。go grocery shopping と。 -
2025.06.20
共テ英語リーディング令6・追試を解く㉚
大問2のBの解説です。毎度お伝えしていることを忘れていました。「最初の状況説明文は読まなくてよいです。」読まないことで、少しでも時間が稼げればよいからです。読まなくても正解できます。今回のは少し長いです。3行ほとんど使用。Aは3行ですが、3行目はshopの1単語だけ。 問2 Emma implies that □. □に何が入るかを選ぶ問題。implyの意味が出てこないとき、どうする?「言う」としてみて選んでゆけばよいと思います。矛盾するようなら、「反対」するなどとして読んでゆけばよいのです。この文は、S+V+that節です。文型に意識した勉強を続けていれば、意味もすぐに出てくるようになるはず。imply: to suggest that sth is true or that you feel or think sth, without saying so directlyの意味です。 こういう文章の場合は、賛成か反対か、肯定するか否定する、のどちらかで意味を探ってもよいでしょう。ある単語帳では、「~を暗に意味する;「~を必然的に伴う」とあります。これをそのまま覚えるのは実戦的ですかね? -
2025.06.19
共テ英語リーディング令6・追試を解く㉙
大問2のBを解きます。繰り返しますが、令和7年はこれまでとは出題構成が変わっていることに注意してください。今回解いているのは令和6年の追試験です。大問1と大問2は、これまでAとBの2つの構成でしたが、令和7年はAとBの2つはなく、1つだけです。 この問題は、とても簡単だと感じました。時間もかからないと思います。問5だけ、少し読み直しをさせられましたが。電車やバスやタクシーでの移動に応じて、ポイントがもらえ、ポイント特典のサービスの説明の広告を読んで答える問題です。日常生活でありがちなサービスですから、理解もしやすいと感じました。解き直しをしているときに、あれあれ、と悩んでしまう問題のようにも感じました。 問1 次の土日にフリーで旅行するのに、何ポイント必要か?と問うています。設問欄は、ポイントの数字をならべてあるだけです。選択肢の④だけは、ポイント数ではなく、乗客数ですが。旅行と書きましたが、地方都市内を移動するときにもらえるポイントのお話です。一度読むだけで、簡単に正解できる問題だと思います。 追試験は本試験よりも難しいと聞くことがあります。この問題を解く限りでは、そうは思いませんでした。 -
2025.06.17
共テ英語リーディング令6・追試を解く㉘
大問2のA、単語チェック、続き。 前掲のworth、高校の定期試験、入試ではよく出てくるような印象です。高校の文法の参考書をいくつか見てみます。 ■いいずな書店の総合英語be it is worth visiting the temple. The temple is worth visiting. ■Next Stage Try to foget it; it isn't worth worrying about. It is worth while doing ~. It is worth while to do ~. なんだかややこしいかもしれませんね。これは根気強くいろんな用例に繰り返し触れてゆくしかないように思います。 ■Vintageは索引を引いて調べると、The Egyptian vessel is an invaluable work of art, so it is displayed behind a thick pane of glass in the museum. という文が出ており、invaluable を選択する問題の中に、worthlessの単語があります。難しいですね。 -
2025.06.16
共テ英語リーディング令6・追試を解く㉗
大問2のA、単語チェック、続き。 ✅thoroughly 一度覚えたら忘れないように思います。発音を正しくできますね。 ✅replacement 中学NEW CROWNの教科書にはreplaceが出ていますから、中学生英語と思ったほうがよいですね。Lesson 5に出てきますから、2学期に入ってからですね。3年の教科書。 ✅cost-effective effective は中学Here We go!(光村)に出ていますから。中学生英語です。難しくなってきているものです。覚えやすい単語ですから、苦労することはないと思います。 ✅commuter 日常的に使われる単語のように思いますが、浸透度が低いように感じます。 ✅thanks to すぐに覚えることのできる連語ですね。英作文にもしばしば使えそうです。 ✅worth これは複数の辞書を比較すると面白いです。研究社の辞書には、「目的語を取るため、前置詞と考える人もいる」、とあります。大修館の辞書は、前置詞としてあります。なんだか、こんがらがってしまいますね。こんなときは、どうするか、辞書の用例の文をしっかり読むようにしましょう。私はそうしています。 -
2025.06.15
共テ英語リーディング令6・追試を解く㉖
大問2のAの単語チェック、続き。 前掲にavoidと関連した多くの単語を覚えてほしいことをお伝えしました。「動名詞が続く動詞」で習うものです。これの代表的な動詞として、覚え方があります。だいぶ受験生には浸透しているようで、知っている生徒も多いと思います。「メガフェプス(megafeps)」です。実は私は、こんな覚え方はしないほうがよいように思います。megafepsとは、mind, enjoy, give up, avoid, finish, escape, put off, stop の頭文字を取って並べただけです。皆さんが英語の試験問題を読んだり、英作文を作るとき、いちいちmegafepsの単語を順番に挙げたりすることはないと思います。辞書を頻繁に引く、多くの文章を読む、これをしておけば、こんな暗記法など知る必要もありません。英語が得意になればなるほど、皆さんもきっとそう思うはずです。 ✅adjust これも中学生単語になってきてると思います。NEW HORIZONには出ています。覚えやすいと思います。日本人のmajor leaguerがよく使っているのを耳にします。 -
2025.06.14
共テ英語リーディング令6・追試を解く㉕
大問2のAの単語チェック、続き。 ✅avoid 今や中学生単語と思ったようが良いでしょう。東京書籍のNEW HORIZONには出ています。高校では動名詞の単元で必ず出てきます。admit, consider, deny, enjoy, escape, imagine, mind, miss, postpone, put off, practice, recommend, resist, stop, quit, suggest, これらすべて覚えましょう。ちなみに、高校生がよく使うVintageに載っているのをそのまま抜き出しました。 ✅Do you want to avoid mechanical problems miles from home? 単語でなく文を抜き出してみました。なぜかというと、miles from homeの箇所の私の訳が正確かどうか分からないからです。意味合いは何となく分かるのですが、解き直しのときは、こうした疑問は徹底的に調べたり、質問したりすべきかと思います。こうした学習が、どこかで役に立つはずなのです。トライプラス国分寺駅北口校の英語教師に聞いておきます。 -
2025.06.13
共テ英語リーディング令6・追試を解く㉔
大問2のAにある単語チェックの続きです。 ✅rural 反意語も覚えましょう。辞書に類義語として、rustic, pastoralも出ていますから、これも一緒に。 ✅reduce この単語は、今や中学教科書で習うようになっています。induce, produceの単語も合わせて学習して覚えましょう。 ✅while 問題文では、You can enjoy daily exercise while reducing your environmental impact on our town.とあります。whileの品詞を説明できますね。分からなければ辞書を引いて調べましょう。ちなみに、この文、上手に日本語に訳せますか? ✅concern この単語は、単語帳でちょろちょろっと勉強するのではなく、辞書をしっかりチェックしておくほうがよいです。動詞と名詞がありますが、動詞は特にしっかりと。よく使う熟語もありますので、覚えましょう。concerning もよく使われます。これも。 ✅long-lasting ここでは、lastの単語を覚えましょう。辞書には、last ₁、last ₂とあります。別単語です。 -
2025.06.12
共テ英語リーディング令6・追試を解く㉓
大問のA、問3、昨日掲載しました。とても重要です。 後で解き直してみて、意地悪に感じる生徒も多いかもしれません。問の文のopinionをわざわざ太字と下線付きにしています。他の問題にはこんな表記はないので、太字になっていることに気が付きなさいよ、という出題者からの注意事項と考えなくてはなりません。こんな細部にまで注意を向けないといけないのですね。過去問を解いて、解き直しをしっかりすることの意義は、こんなところに感じられます。 問4を見てみましょう。顧客コメントの正しいものを選ぶ問題です。私は消去法でやって、残ったものが合っているかも確認して正答を導きました。簡単かと思います。 問5も簡単でしょう。自転車屋さんが何を伝えようとしているか、選ぶだけです。 ✅maintain 大学受験をするならば、必須かと思います。が、今や、中学で習う単語になっています。maintenanceの名詞形も覚えやすいですね。英英辞典を見ると類義語として、preserve, insist, keepが出ています。 ✅encourage これも中学レベルの単語になっています。encouragedの受け身もよく使われます。 -
2025.06.11
共テ英語リーディング令6・追試を解㉒
大問2のA、設問の問3です。 ★★★この問題、是非解いてみてください。こんな問題を出すのだな、と考えさせられます。 Which of the following matches one customer's opinion? 客の意見に合うものはどれか? ①客A 平日自転車に乗る ②客B 学校まで15分 ③客C スタッフがもっと情報提供してくれれば ④客D 最上位のプランを評価している この問題、私は不正解。候補は2つに絞られると考えて選びました。正解はもうひとつの方でした。では、他のひとつ、なぜ不正解なのか?私は考えに考えました。何度も何度も読み、辞書で単語の意味をよくよく調べてみました。しかし、なぜ間違いだったのか、さっぱり分かりませんでした。その日はあきらめて、翌日、また何度も何度も読み返しました。単語もまた調べました。なかなか分かりません。あきらめかけて、ふと、問の文に目がゆきました。上記にある文です。最後のopinionが太字&下線がつけられています。あっ、と思いました。選択肢の文は、事実を述べているもの、意見を述べているものに分かれます。そうか、やっと正解、不正解の理由が判明しました。 -
2025.06.10
共テ英語リーディング令6・追試を解く㉑
大問2のA、設問の問2です。 All the plans refer to 〇〇. すべてのプランが言っていることは?という問い。3つあり、料金とサービス内容がそれぞれ違います。共通しているものは、ということですね。 ①部品の無料交換 ②サービス頻度 ③割引率 ④製品の信頼性 ③は、2つのサービスでは言っています。①部品の無料交換、1つのサービスで、ブレーキのケーブルが無料というのはあります。④修理についての内容で、製品が信頼できるよ、とは全く言っていないので、明らかに間違い。②は、年2回、年4回、毎月のサービスがあるので、これが正解。簡単のようですが、⓵、③に惑わされないことですね。 -
2025.06.09
共テ英語リーディング令6・追試を解く⑳
大問2のA、簡単だが、選択肢で迷わされてしまうと説明しました。具体的に説明できるとよいですが、頑張ってみます。 いつもと違い、設問文を先に解説してゆきましょう。 問1 自転車屋が〇〇ということをsuggestしている。 ①サイクリングは日々のよい運動 ②公共交通は環境的にサステナブルであるべき ③大学は自転車のメンテを援助すべき ④ギアをアップグレードすると、安全、長持ち、エコ ②reducing your environmental impact の記載があり迷うかも。drive less これも。④need upgraded gearsの記載があるので迷うかも。③は、そのような意見はどこにもされていないので、明らかに間違い。あまりにも最もすぎる⓵を選ぶのが正解です。最もすぎて、②,④と迷ってしまうのかもしれません。冒頭から、we are being encouraged to exercise moreや、you can enjoy daily exercise と書いてあります。初っ端に書いてあることだから、正解でないかも、といぶかりすぎないことですね。 -
2025.06.08
共テ英語リーディング令6・追試を解く⑲
大問2のA。共テのどの問題もそうですが、前提説明の文章は読まずに進めて大丈夫です。どんなことが書いてあるのかを示しているだけなので、本文そのものを読むだけで十分です。どんな文か示しておきます。 You are studying at Plainburg Community College in the US. You go to college by bicycle and find this advertisement on campus from a local bicycle shop. どこの大学に行っていようが、そんなことは全く解くうえでは関係ないことです。無視、無視。 広告の表題から、自転車のメンテについて書いてあることが分かります。そして第2部として、メンテナンスパックの種類(ランク)と利用者のコメントが書いてあります。内容はおそろしく簡単なのではないでしょうか。しかし、いざ設問に進んでみると、???なんだ、と選択に迷わされるのではないでしょうか。 -
2025.06.07
共テ英語リーディング令6・追試を解く⑱
共テ過去問、英語に限らず、どんどん今のうちから解き進めましょう。夏休み完成のつもりで今から進めると、とても有利だと思います。高得点を取ってゆくには。 大問2を解きます。これもAとBに分かれます。ここで注意すべきことがあります。大問1と同様に令和7年度の本試験は、大問2も、これまでのようにAとBの2つの問題ではなく、1つだけです。おそらく、令和8年度の試験もこうなるのでは。過去問の研究をする際には、問題構成も気にすると思います。変化があったときに慌てないようにしましょう。問題の難易度が変わるわけではありませんので。 問は5つありますが、どれも、迷わせるような選択肢ばかりのように感じました。問題文はやさしいな、と感じるものの、いざ、正解を選択するとなると、迷ってしまい難しいと思わせるような作問をしているように感じます。共テでは、こんな迷いが後に続く問題に影響を与えてしまうこともあるかもしれませんね。大丈夫です。過去問を何度も解き直すと、迷わずに正解を選べるようになるはずです。 -
2025.06.06
共テ英語リーディング令6・追試を解く⑰
共テ過去問、どんどん解き始めましょうね。高校生は期末テストがありますが、テスト前に少しでも解いておくとよいです。期末後、夏休みまでの期間、そして夏休み前半、夏休み後半。第4クールまであります。期間を設けて計画的に進めてゆくとよいです。解いて、一緒に解き直し学習をしてみましょう。 前掲の続きです。大問1のBの問題文は終わりましたので、設問文の単語チェックをしておきましょう。その前に、前掲の文で、keepの単語がありました。辞書でかなりの量を割いている単語のひとつですから、しっかり学習しておきましょう。 ✅affection affectは中3教科書(三省堂)に出ていますね。光村にはaffectionも巻末索引に。中学生が習う単語もずいぶんと増えたものです。前置詞forが続くのですね。動詞と名詞の意味のつながりがつかみにくいように思います。しっかり繰り返し学習して定着させましょう。 ✅abandon 覚えやすい単語でしょう。 -
2025.06.05
共テ英語リーディング令6・追試を解く⑯
共テの過去問、高校3年生は当然ですが、高2生も、いまのうちからどんどん解いてゆきましょう。解いたら、一緒に解き直しをしましょう。 英語リーディングの令和6年度、追・再試験の問題を解いています。 大問1のB、どんな問題なのか、出ている単語チェックをしています。前掲、sheepの単語がありました。辞書を見ると、ram, ewe, lamb, muttonの単語も出ていました。ewe なんて知らないぞ、そして発音は?you と同じ発音だそうです。ram と lambの違いは?スーパーで「ラム」のお肉が売っているのをよく見かけますが、どっちなのでしょうか?lambのように私は思うのですが? lambの発音にも注意ですね。 ✅goat 今度はヤギです。山羊と書くのですね。皆さんは羊とヤギの違いは分かりますか?同じウシ科ヤギ亜科に属する、とあります。辞書をみると、ヤギにはちょっとかわいそうな意味で使われることがあるようですね。最近、雑草をたべさせるために放し飼いにしているのを時々見るようになりました。 ✅またありました、help。 Volunteers help keep them safe. -
2025.06.04
共テ英語リーディング令6・追試を解く⑮
大問1のB、単語チェック、続きます。 ✅information 注意したいのは、問題にあるようにinformation on the catsです。information に続く前置詞は、about, on, as to, concerningです。of はないそうです、辞書の説明だと。information + that節、もあります。このthatの品詞は説明できますね。英作文に役立つと思います。 ✅put on おなじみの連語として覚えましょう。ただし、問題文では、連語ではなく、ただの動詞で使われています。受け身で使われています。putは不規則動詞ですが、その活用は大丈夫ですね。putは、辞書でもしっかり確認しておいた方がよいです。ある辞書には、<類語比較>として、put,lay, set, placeについてそれぞれ詳しく説明されています。あわせてしっかり調べておくとよいですね。 ✅adopt 何年か前にも出ていました。内容も同じように猫のことでした。 ✅sheep 単複同型ですね。5/24掲載にも単複同型の名詞がありましたね。fish も。carp 赤ヘルファンはよく知っているのでは。 -
2025.06.03
共テ英語リーディング令6・追試を解く⑭
大問1のB、単語チェック、続きます。ただ内容が読み取れればよい、それでも良いでしょう。しかし、「引き出し」をたくさん持っておくことも良いかな、と。少しでも生徒さんたちの役に立つと私もうれしいです。 ✅help こんな文です。Volunteers help feed and care for the cats. 簡単に意味は分かりますね。feedの単語は大丈夫ですね。問題はhelpです。feed, careは名詞ですか、動詞ですか?どちらとも取れるように思います。動詞としたとき、help feedと動詞が続く文を見たことはありますか?日本の学校で英語を習うとき、動詞がこのように続くことはありえない、ときっと教わるはずです。helpの場合、これがあるのですね。これ、共テには毎年のように出てきます。一度、helpを辞書で調べてみてください。奥深い動詞で、文型をしっかり学べておくだけで、応用がしっかりききます。 -
2025.06.02
共テ英語リーディング令6・追試を解く⑬
大問1のB、単語チェックをしています。 ✅at least 塾にある中学単語帳には出ています。中学レベルの連語だと思ったほうがよいでしょう。leastは形容詞なのですが、これは最上級です。原級、比較級は? ✅once Once you start, ~とありますが、品詞は何か分かりますね。 ✅train ここでは、train you to take care of the animals と動詞です。Train+目的語+to doの文型です。先に掲載していますが、動詞の文型ごとの単語帳を作ってみると、英語力は高まるように思います。 ✅fond be fond of の連語はよく覚えていると思います。ここでは、feel fond of となっています。 ✅briefly 簡単でしょう。briefの形容詞、名詞があります。名詞の意味が複数ありますが、briefsでunderpantsの意味がありますね。 ✅temporary contemporaryも一緒に覚えましょう。temporaryの反意語も一緒に。 -
2025.06.01
共テ英語リーディング令6・追試を解く⑫
大問1のB、続きです。 Websiteのお知らせの内容を問う問題。Aはビラ、BはWebsiteでのお知らせで、このようなパターンの問題は頻出ですね。私立大学でもこのような形式の問題を出すところもあるでしょう。Bは、とっても簡単だと思います。 単語のチェックをしておきます。 ✅mission 表題のところに出ています。中3の光村図書の教科書には出ています。三省堂には出ていません。塾の中学用の単語帳には出ており、英検2級レベルとされています。この問題を解くときに意味が出てこなくても飛ばして読んで大丈夫です。 ✅care ここでは動詞で出題されていますね。中学生で習うtake care ofのcareは名詞ですね。care forの連語で覚えましょう。 ✅previous 高校生単語のようですが、簡単に覚えられていると思います。発音は正しくできますね。 ✅No experience is needed. 文を載せましたが、このような否定文、そして受け身の文は、しばしば共テには出ているかと思います。このような文が作文で簡単に書けるようにしておくと、とても良いですね。 -
2025.05.31
共テ英語リーディング令6・追試を解く⑪
大問1のBを解きます。 設問数3、各2点合計6点の配点。 ◆ポイント: 冒頭の説明文は読まずに進める! ここでも冒頭の説明文は読まずに進めてよいです。問題文に書かれてある内容をとらえて解くだけですから。少しでも時間を稼ぎましょう。 ちなみに、冒頭説明文を示しておきましょう。 You are studying in the US and are interested in volunteering during your stay. You find the advertisement on your school website. 第1問のAが、チラシ、そして、Bはwebsiteに書いてある内容を読み取る問題です。どこに書いてあるかなど、全く問題を解くにあたり影響はありませんから、いきなり問題文を読んでゆけばよいのです。この問題では、「ボランティア募集!」の次に、Animal Supportとありますから、動物に関するボランティアの募集であることがすぐに理解できます。この問の文章は簡単で読みやすいでしょう。ボランティアの条件と犬、猫、子供動物園がやっていることなどが書いてあるだけです。 -
2025.05.30
共テ英語リーディング令6・追試を解く⑩
大問1のAの単語チェック、最後です。 ✅shade 日本語でも日常使われるようになってきたように思います。特に、ちょうどこの頃の季節から。ホームセンターではたくさん販売されていますね。sunshadeで覚えやすと思います。サングラスという意味もあるのですね。 ✅spot 設問文は動詞で使われています。動詞の文型、おなじみのものがたくさんあります。 ・+目的語 ・+目的語+前置詞+(代)名詞 ・+目的語+as[for]補 I spotted him at once as an American. こんな文です。 ・+that節/wh節 I soon spotted what the mistake was. こんな文。 上記3番目でよく使われる動詞は、regardが思い浮かびます。 He regards himself as a patriot. このように、同じ文型の単語が頭に浮かぶようになると勉強が面白くなってくるように思います。 regardを調べたときに、considerを同時に調べることが多いかと思います。辞書で調べたときには。 -
2025.05.29
共テ英語リーディング令6・追試を解く⑨
大問1のAの単語チェック、もう少し。 ✅may Hikers may have the chance to~の文です。中学で習っていますが、5/26掲載のmightとともに、辞書でしっかり確認してみましょう。かなり骨が折れますが、このような作業が英語を得意科目にしてくれます。 ✅admire 覚えやすい単語とは思います。動詞です。文型を見ると、少ししかないです。 ✅scenery 今や中学生で習う単語になりました。Sceneの単語との違いも調べておきましょう。 ✅summit 簡単ですね。皆さんがよく聞くのは、summit conference(meeting, talks)のことですね。いやいや、スーパーマーケットを思い浮かべる人のほうが多いかもしれません。私は通勤途上で毎日のように前を通りますから。 ✅encounter ちょっとだけ覚えにくいかもしれませんね。ただ、設問文を読めば、意味が思い出されるでしょう。辞書でたくさん調べてみました。一番頭に入りやすかったのが、英英辞典です。SYN.(同義語/類義語)としてmeet, run into, come acrossが載っていました。 -
2025.05.28
共テ英語リーディング令6・追試を解く⑧
大問1のAの単語チェック、あと少し。 ✅length 中学の教科書(三省堂、光村、東書)の索引には載っていませんね。トライプラス国分寺駅北口校の中学生に推奨している塾用の単語集「Complete Selection 2800」には載っています。英検2級レベルの単語のようです。発音、正しくできるでしょうか? ✅warning 発音は大丈夫でしょうか? 動詞はwarnです。辞書では動詞は必ず文型が示されています。 1. a [+目] b[+目+前+(代)名] c[+目+to do] d[(+目)+that節] 動詞を学習するときは、文型もチェックすることです。英語学習に「効率性」を求めるならば、とても効果あり。試してみてください。adviseの単語と比べてみてください。そっくりではないですが、とても似ています。文型ごとにまとめた動詞専用の用例集(単語帳)をつくってみることをお勧めします。国公立大の2次試験、英検準1, 2級では、英作文の力が試されます。きっと役に立つはずです。一朝一夕にはいきません。じっくり時間と日数をかけて取り組みましょう。これをやったら確実にやっていない人との差を実感するはず。 -
2025.05.27
共テ英語リーディング令6・追試を解く⑦
単語チェック、続き。 前掲のbald。辞書には⦅類音⦆boldと出ています。この単語も覚えましょう。それぞれ正しい発音も。この単語の3つ目の意味は、皆親しみがあると思います。「ボールド体の」、「太活字の」。 ✅narrow 中3で習います。対義語も大丈夫ですね。wide, broadです。辞書によって対義語の記載があったりなかったり。トライプラス国分寺駅北口校には、英語の辞書が13冊そろっています。単語帳が26冊。国語系は13冊。近隣他塾には負けていないと思います。まだまだそろえたく思っています。電子辞書を購入してみようと考えています。調べると、その収録数に驚かされます。価格によって数が違うのですが。パソコンで見ると、スクロールするだけで量が多すぎて、見づらいです。電気屋さんでカタログを見た方がよさそうです。明日、早速行ってみることにします。 ここまで問題文にある単語。次に設問文から拾ってゆきます。 ✅be included in 簡単 ✅direction 私は「方向」、「指示」の意味が思いつくのですが、辞書に「道順」が。これですね。解き直しでは辞書で単語チェックすることは大事だと思います。 -
2025.05.26
共テ英語リーディング令6・追試を解く⑥
前掲続き、単語チェック。前掲の最後は単語でなく、文を抜き出しました。意味は簡単に理解できるでしょう。しかし、私は、「, home」のところがうまく理解できませんでした。英語の教師に質問すると、「同格のコンマ」ですよ、とあっさり。高校生で習ったはずですよ、と。 ✅cattle 私は高校生のときに覚えたように思います。その後、タンザニアに旅行に行ったときにマサイ族が牛の放牧をしていて、ガイドが、この単語を使っていたので、もう忘れることはありません。経験は大事。 ✅be used to おなじみの熟語ですね。発音は正しくできますね。 ✅as 3段落の2番目の文頭。接続詞です。as はしっかり学習しておくとよいです。 ✅might 文法の接続詞でしっかり学習していますね。辞書も繰り返し見るのもよいです。 ✅catch sight of 簡単に覚えられる熟語です。 ✅deer 単複同型の名詞ですね。 ✅superb 文を読めば簡単ですね。 ✅observe 中3で習ったはずです。 ✅bald 発音は大丈夫ですか?解くときには分からなくとも気にしない。bald eagleとあります。米国の国鳥のハクトウワシです。 -
2025.05.25
共テ英語リーディング令6・追試を解く⑤
第1問のA、どんな単語があるかを見ましょう。簡単すぎると思うでしょう。しかし、うまく訳すのが難しい文が共テでは以外に多いように思います。 ✅go hiking おなじみの表現です。簡単。go fishing, go camping, go shopping, まだまだたくさんあります。go を辞書でじっくり眺めることもとても勉強になります。 ✅flyer flierのつづりもあります。令和5年はhandout, 令和7年はpamphletの単語が使われています。 ✅trail 問題文では訳す必要もないと思います。しかし、解き直し学習では、きちんと辞書を引いて調べておいたほうがよいです。 ✅go through 簡単ですね。 ✅path 私はすんなり一度で覚えて、ずっと忘れることがありません。誰しも、こんな単語が何個もあるはず。 ✅divide 文脈からも簡単に意味が分かりますね。 ✅Take the left-hand path to enjoy the LowlLand Trail through the woods, home to many birds and small animals. -
2025.05.24
共テ英語リーディング令6・追試を解く④
第1問のA。2つのハイキングコースが紹介されたビラの内容を読み取る問題。 ◆ポイント: 日常的によく使われる単語がよく出てくる ここで"Flyer"という単語があるのですが、高校生でどのくらい意味を知っているでしょうか?あまり学習する機会がないような単語なのではないでしょうか?共通テストには、この単語のような英語圏で日常的に使用される単語がしばしば出てくる印象です。これも過去シリーズでも申し上げてきていますが、共通テストの対策に限って言えば、受験用の単語帳はほとんど役に立たないと感じています。問題を作成する先生たちのことを考えると、CNNやBBCなどのニュースやテレビのドラマ、英字新聞などよく観たり、読んだりしているのではないでしょうか。高校生が共テ対策をするには、日々、英語に触れる機会を多くしてゆくことでしょうね。良いサイトを発見しました。 「英語教員のためのポータルサイト えいごネット」です。私も日々これで勉強してゆこうと思います。 -
2025.05.23
共テ英語リーディング令6・追試を解く③
第1問 AとBの2つ問題があり。設問が2つ、3つで、各2点合計10点。文章も簡単ですが、解答においては、うっかりミスが起こりえるような問題になっているように感じます。 ◆ポイント ⓵前段の状況説明の文は読まずに進めるべし! ②何かを紹介する”ビラ”は必ず出る Aは"Flyer"が示され、その内容についての設問です。”チラシ”、”ビラ”のことですね。今回は2つのハイキングコースを案内された”ビラ”です。共通テスト解説をするのも、今回で4シリーズ目なのですが、毎度毎度私は一貫して、最初の設問文は読まずに進めてよいと説明してきています。第1問に限らず、すべての大問について言えることです。読まないことのメリットは、時間の節約です。秒単位にはなりますが、トータルでは、1分半は時間節約になるでしょう。こんな文です。 You are studying in the US and your class is going hiking. You are reading a flyer from your teacher. 先生がこんなビラを配ったよ、という状況説明だけです。こんな前段の文は読む必要は一切ありません。 -
2025.05.22
共テ英語リーディング令6・追試を解く②
共通テストの英語リーディングの令和6年度の追・再試験の解説です。共通テストは、ただただ速読力を問われるテストと考えてよいと思います。最後の問題までたどりつくことが難しければ、前掲のように、まるまる大問ひとつを捨てるというのも作戦の一つです。前掲では、第6問を捨てると満点で76点と説明しました。第6問、捨てると言っても、マークだけは終了20秒前に一気にしましょう。例えば、すべて1をマークした場合、6点かせげます。2をマークした場合6点、3をマークした場合、6点、4をマークした場合、0点。2つ選択で両方あって正解の問題もありますから、それはあきらめましょう。 第5問を捨ててみる作戦もありかも。そうすると他で満点を取れば、85点もとれます。これは相当な高得点です。第6問より第5問のほうが難しい、という生徒も少なくないと思いますし。第5問をすてて、マークだけする場合、3をマークすると6点かせげます。なんと91点ですよ。偏差値だと70は超えるでしょうね。 -
2025.05.21
共テ英語リーディング令6・追試を解く
共通テストの英語リーディングの令和6年度の追・再試験を解いてゆき、解説したいと思います。 トライプラス国分寺駅北口校では、英語の共通テスト対策として、過去問を解いてもらう時期は様々です。生徒一人一人の受験勉強の進み具合によって異なってきます。比較的多い例は、夏休みの終わりまでに、目標点数に到達できるようにカリキュラムを進めます。共通テストの準備は時間をかけてやるべきで、夏休みだけでは不十分です。すぐに取り組んでいただきたく、今回の掲載をしてゆくつもりです。 追・再試験は、本試験と同様の問題構成です。注意すべきは、令和7年度から問題構成が少し変化しています。令和8年度は令和7年度の構成と同様となるのではないでしょうか?構成が異なるだけで、対策するに影響はないでしょう。以下のような構成です。 第1問 A, B 配点10点 第2問 A, B 配点20点 第3問 A, B 配点15点 第4問 配点16点 第5問 配点15点 第6問 A, B 配点24点 最後まで解ききれなかった生徒も少なくないはずです。大事なことは目標点数に到達することで、例えば第6問を捨てて、第5問まで76点満点取る目標もありなのです。 -
2025.05.01
受験への準備
いつから開始すれば良いのでしょうか? いろんな答があると思います。生徒さん一人一人、状況が違いますから。そして、受験型式も多岐にわたっていますから。答を求めたいならば、塾での進路相談を受けてみるのは、有効な手段のひとつです。トライプラス国分寺駅北口校では、入塾されずとも、進路相談だけでも受付しております。 大学入試を例に、いつ開始すればよいか考えてみましょう。高校3年生ならば、すぐにトライプラス国分寺駅北口校に相談ください。すぐに開始していただくようお願いします。志望する大学、その入試形態にもよりますが、時間が足りない生徒さんが多い傾向にありますから。総合型選抜の入試を考えておられるならば、入試は10月~12月です。共通テストを受けなくてはならない国公立大志望だと、8か月後です。科目も多いし、大変な学習量が必要になります。学校の定期試験、クラブ活動、文化祭もありますから両立させてゆかねばなりません。だから、今すぐにトライプラス国分寺駅北口校に相談ください。もう手遅れだ、という時期がいつかは来ます。だから今すぐに。 -
2025.04.30
中学社会、歴史の教科書の楽しみ
歴史の教科書も、掲載された写真を見てゆくことは、私の楽しみです。今回は、帝国書院の教科書のみ購入しました。一番最後の項が、「国際社会におけるこれからの日本」。最新の教科書には、ウクライナの避難民とボランティアの写真がありました。そして、「グローバル化の進展と感染症」についての記載と昼間に人っ子ひとりいない渋谷のスクランブル交差点の写真がありました。また、NGOの活動の記載もあり、アフガニスタンで銃撃されて亡くなった医師の「中村哲」さんの写真と活動内容の紹介がありました。最後の締めくくりの項、「未来のために歴史から学ぶ」、前の教科書とは、文章がずいぶん違っている印象です。「歴史で学んだことを」未来に生かしてゆきましょう、という同じ趣旨ではありますが。新しい教科書では、「感染症の問題」の言葉を加えています。次の改訂でまた新たな”問題”が出てこないことを願いたいです。「未来の子供たちのために」、という言葉をよく大人は使います。本当は、大人がもっと学ぶべき、正すべきだと思っています。 -
2025.04.29
中学社会、公民の教科書の楽しみ
公民の教科書、これも掲載された写真をチェックするのは、私は楽しいです。今回は、帝国書院の教科書のみ購入しました。日本の首相や米国大統領は、必ず出ていますね。新しい教科書では、岸田元首相、バイデン前大統領。その前は安部元首相、トランプ大統領でした。その前も同じく。行政機関の組織図も必ず出ています。前は「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部」がありました。2020年のときの組織図です。今回、「国際博覧会推進本部」が。大阪万博のことですね。当塾の教師が早速行ってきて、授業中に高校生の生徒に行くべきだ、とおすすめしていました。生徒は夏休みに行けるように計画を練ってみるようです。「デジタル庁」、「こども家庭庁」も加わっています。 労働環境の変化のページでは、「『仕事x休暇』のワーケーション」が新たに出ていました。コロナのときに急速に広まったように思います。現代の紛争のページには、ウクライナ侵攻も新規も出ています。次回は、新規な情報が出てこないと願いたいです。「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)、RCEP協定も新規に出ています。 -
2025.04.28
中学社会、地理の教科書の楽しみ
当塾生は、演習授業や自習で塾に置いてある教科書、参考書をよく使用しています。先日購入した中学社会、地理の教科書を見てみました。当塾では、地理の教科書は3冊目です。いつも購入した直後、掲載写真をすべて見て楽しんでいます。大谷翔平選手、また出ています。2022年の写真です。前の教科書は、2018年のもの。その前は平成31年発行のものですが、ICHIRO選手が出ていました。次回の改訂では、きっと、青いキャップの大谷翔平選手が載るようになると思います。九州地方の単元の最初には、大分県の由布岳と観光列車の「ななつ星」が。超豪華なようですね。その前は、「ゆふいんの森号」でした。宮崎でのプロ野球キャンプの写真も必ず出ています。今回は、Halksでしょう。帽子のつばが黄色なので。その前は、Giants、その前がBaystars。次回の改訂は、また違うチームの写真になるのでしょう。沖縄のビーチにあるホテルの写真は、前のと同じでした。その前は違うホテルでした。次回の改訂では、きっとまた違うホテルになるでしょう。試験には出ないですかね。いやいや、「観光」に関連する事柄は、試験にも多く出されていますよ。 -
2025.04.27
洋楽を聴くと英語に親しめるのでは
中学の英語の教科書の紹介をしておりましたら、Billy Joelの”Pressure"にたどりつきました。ちょっとだけ、歌詞を見てみます。 You have to learn to pace yourself Pressure で始まります。その1小節の終わり、 And You'll have to deal with Pressure 歌詞も簡単に検索できますから、一度聴いて、歌詞を見てみるとよいでしょう。中学で習う英語の表現ばかりです。 deal という単語、4月に入ってからしばしば耳にします。合衆国大統領の報道ニュースを観ていると。 Billy Joelの"Just the Way You Are"も続けて聴いてみました。まだまだたくさんあります。私が高校生のとき、夜遅い時間に学生用に英語の放送をやっていてよく聴いていました。そこでも洋楽の紹介をしていました。ある日、Carpentersの"Yesterday Once More"の紹介をしていました。そこから、何度もこの曲を聴きました。英作文で役立つことも多かったです。 -
2025.04.26
NEW CROWN 中3の改訂(3)
Lesson 3 を読み進めると、「Reading Lesson 1」に音楽のお話があります。ここにもBeatlesの曲を例示しています。"She Loves You"と"Yesterday"です。Lesson 2では、”Help!”の紹介がありましたが、その前のページには、Taylor Swiftの”Shake It Off"、Bruno Marsの"Count on Me"を文化祭で歌うという話もあります。歌詞が巻末付録に掲載されています。さらに、Carole Kingの"You've Got a Friend"とBruno Marsの”Just the Way You Are"が。これは教科書の見開き、「Feel the Power of Words」に歌詞の一部が掲載されています。英語の歌を聴いて、歌詞を見て歌えるようになると、英語の勉強が楽しくなると思います。Taylor Swiftとその曲はたくさんの中学生が知っているのでは。”Just the Way You Are”、私は、Billy Joelの曲のほうが思い浮かびますね。私の彼の好きな曲は"Pressure"です。 -
2025.04.25
NEW CROWN 中3の改訂(2)
続きです。 Lesson 2を読み進めてゆくと、ありました、楽曲についてが。The Beatlesの"Help!"です。巻末には、歌詞が掲載されていますから、インターネットで曲を聴いてみて覚えてみると、英語の上達が早くなりますよ。 その前のページにあれあれ、と思った表現が出ていました。 It's important for us to reduce waste for the environment. この表現は、これまでの教科書だと中2のLesson 2の不定詞を学ぶところに出ていました。新しい教科書では、3年に移ったのですね。 Lesson 3に進むと、「Cranes for Peace」の題です。広島市の修学旅行のお話です。最後に「The Story of Sadako」のお話が。これは前の教科書と題材は同じですが、学習単元が「受け身」の表現です。前のは、「分詞の後置修飾でした。 習う順番が違っているだけですから、これによって生徒の皆さんが学ぶに難しくなる、ということはないでしょうね。 -
2025.04.24
NEW CROWN 中3・英語の改訂
中2と同様に、がらりと変わっています。昨年までのは、「Starter」として、有名な楽曲の”Stand by Me"と"True Colors"の紹介があったのですが、なくなっていました。なかなか良い文章でした。新しい教科書は、2年で学習した「現在完了形」の復習から始まっています。これがLesson 1です。昨年までのは、Lesson 1で「現在完了進行形」を学習するものでした。 It has been rainning since this morning. I have been playing soccer for two hours. この表現でした。 新しい教科書では、これがLesson 2に出てきます。Part 1 に。 We have been discussing it since last week. さらにPart 2に進むと、ちょっとびっくり。 My friends helped me carry my drum set. この表現は、昨年までのだと、最後のLesson 7に出ていたのです。保護者の方々は、これを中学で習うのかと驚かれるかもしれません。昔は高校での履修でしたから。 -
2025.04.23
NEW CROWN 中2の改訂(2)
前掲で増えた単語を少しだけ紹介しました。もうちょっとだけ、続きを見てゆきます。 achievement, across, adaptation, addiction(こんな単語まで!), advice, affect(こんな単語まで!)。ここまで調べて、気が付きました。中2<新>の巻末の単語は、3年生の教科書にあるものも載せていました。<旧>では、3年生の教科書にあるものは載せていません。では、と、中3<旧>を見てみました。addiction, affect なんて単語は載っていません。これらは、新規に増やされた単語ということになります。 なくなっていた単語もありました。active, adult, advertise など。 まだAのごく一部の単語しか見ていませんが、一つ一つ順番に見てゆくと、きっと難しい単語がたくさん加わってきているのではないかと思います。時々、紹介してゆけたらよいと考えています。 -
2025.04.22
NEW CROWN 中2の改訂
教科書の改訂版の一部をトライプラス国分寺駅北口校にそろえましたので、早速内容チェックしてみました。英語、NEW CROWN 中2から。 ✅教科書のサイズが大きくなった。A4サイズになりました。横幅は以前のままですが、縦幅がB5サイズからA4サイズへ。 ✅教科書中の「登場人物」はそのまま。 ✅巻末収録の単語数 数えていませんが、増えていると思います。 <旧>巻末資料P.25~43、19ページ分 <新>巻末資料P.26~46、21ページ分 文字のサイズも同じ、そして、教科書サイズも大きくなっていますし、ページ数も増えていますから、確実に増えているように思います。 こんな表記もありました。 <旧>「太字の語は特に大切な語である(3学年で約800語)」 <新>「太字の語は特に大切な語である(3学年で約1,000語)」 太字にした単語が増えただけのもありました。alone は、<新>で太字に変わっています。 なくなった単語もありました。above は<旧>にはありましたが、<新>にはなくなっています。 <新>で加わった単語、少し挙げてみましょう。 academic, academy, accept, according -
2025.04.21
令和7年度の教科書改訂
令和7年度(2025年度)、教科書の改訂がありました。 4/16(水)に、教科書販売店で購入してきました。中学の教科書の販売初日で、レジは行列でした。トライプラス国分寺駅北口校の常備用として、英語、社会の教科書を購入。 【英語】 NEW CROWN 三省堂 Here We Go! 光村図書 NEW HORIZEN 東京書籍 【社会】 中学校の地理・中学校の歴史・中学校の公民 帝国書院 トライプラス国分寺駅北口校は、国分寺駅から徒歩3分の立地であることから、国分寺市、小平市、小金井市、府中市在住の生徒さんが多いです。よって、それぞれの市が採用する公立中学校の教科書をできるだけそろえるようにしています。特に、公立中学校の生徒さんの英語の個別指導の授業には教科書は欠かせませんので。 -
2025.04.20
共テ-英語リーディングを解く:総括
2025年の共通テスト、英語リーディングを解き、解説してきました。 総括は簡単です。 ・2次試験、私立大にあるような難解な文章はなし ・80分の時間内に最後まで到達できる速読力が必要 ・日常生活で使うような単語や表現が目立つ ・現在使われている英語表現ばかり(古臭い英語表現は一切ない)(これは、トライプラス国分寺駅北口校の英語の教師の説明) よって、共通テスト、英語リーディングの対策は、「速読力」を磨くことのみ、です。簡単に言うな、と叱られそうですが、事実だから仕方ありません。簡単ではありませんよ。時間をかけて、多読してゆくことが対策なのです。共通テストまでは、9か月あります。高校2年生だと21か月あります。「速読力」を磨くには十分な時間です。毎日、英語に触れてゆくことです。毎日欠かさずやらないと磨かれません。100点満点取れる人は皆そうしています。 最後に、このようなシリーズを掲載しているのは、共通テストを受ける予定の生徒みなさんに、少しでも早く準備を開始していただくきっかけになればと思っているからです。是非とも高得点が取れるよう、応援しています。 -
2025.04.19
共テ-英語リーディングを解く(48)
2025年、共テ、英語リーディング、第8問、解説、続き。 問5の選択肢の英文4つは難しいと思います。3行と長いですし。 ①と②の選択肢を例に見てみます。 ①The amount of money that governments around the world spend on space exploration could not only reduce hunger but also make primary education available in developing countries. ②The data show that it costs less to ensure clean water for people in developing countries than for governments around the world to explore space. not only や less あたりが入ってくると、少し難しくなるように思います。私自身は、どうもこのような否定の単語が入ってくると、読解が難しくなるなと感じます。多読して慣れてゆくのが一番だと思います。 -
2025.04.18
共テ-英語リーディングを解く(47)
2025年、共テ、英語リーディング、第8問、解説、続き。 [Step 3] は、「宇宙開発の再考」と題した文章があり、空欄を2箇所埋めてゆくようになっています。文章の冒頭にSpace exploration should not be a priority, と強く述べ、その理由を3つ述べる形式になっています。理由を述べる根拠として、[Source A]と[Source B]の記事を読んでゆかなくてはなりません。Source Aの文章の内容が、そのまま問4の解答につなげられます。 Source A を読みます。14行の英文です。長いですが、First, とSecond, と2つの問題を述べてあるだけで内容は簡単に理解できると思います。CO2と宇宙ゴミの問題です。 Source Bは、グラフもあります。宇宙開発にかけるお金はどんどん増えており、それと世界中での問題事項にかかる費用とグラフで対比しています。この内容がどうであるのかを問5で答えるようになっています。問5のそれぞれの選択肢の設問文は長く、難しいと思います。 -
2025.04.17
共テ-英語リーディングを解く(46)
2025年、共テ、英語リーディング、第8問、解説、続き。 問3 宇宙開発に反対する立場の意見を答える問題です。反対の立場は、MeilinさんとNaomiさんです。Meilinさんの言っていることは、4/15の掲載に書いています。宇宙人の侵略の話でしたね。Naomiさんは、宇宙は事故が多すぎるる、と言っています。こんなに事故の多い仕事はない、と言っています。問3はとても簡単です。 問3を解き終えると、[Step 3] Create an outline of your essay、とあり、A Reconsideration of Space Explorationという題名で簡単にまとめられたメモ書き程度の文章があります。2箇所ほど空欄になっております。ただ、ここを埋めてゆくためには、問題文を読み進めなくてはなりません。私は解きながら、宇宙開発に疑問をもった意見が書かれているだろうなと思いました。それで正解でした。話の展開が読めたわけですね。これも、第8問がそう難しくないと感じさせることなのでしょう。 -
2025.04.16
共テ-英語リーディングを解く(45)
2025年、共テ、英語リーディング、第8問、解説、続き。 問2が2人の意見が述べている内容を選ぶ問題で、Christineさんの意見を前掲に載せました。もう一人のVictorさんの意見。宇宙開発が経済成長に貢献している、と言っています。私は個人的には、そんなお金はもっと別のところに回せばよいのに、解きながら、感じました。私の場合ですが、このように考えさせながら読めましたので、この問題が面白いなと思いました。すみません、問題の解法には全く関係ないかもしれません。この2人の意見は宇宙開発に肯定的なもので、どんなことで肯定的になれるのか、それを選ぶ問題と考えてよいです。設問の選択肢の文が少し難しいと思います。選択に迷うかもしれません。 問2を解き終えると、[Step 2] Take a positionの題がつけられた、簡単な文章があり、一部空欄になっています。ここにふさわしいものを選ぶ問題です。Take a positionも意味がわからなければ、そのまま読み進めてよいです。宇宙開発に反対の立場だと書いてあります。そう、反対意見であるように、選択肢を選べばよいだけです。 -
2025.04.15
共テ-英語リーディングを解く(44)
2025年、共テ、英語リーディング、第8問、解説、続き。 問1 簡単でしょう。正解以外の選択肢は全く見当はずれで、すぐに正解がわかるでしょう。Meilinさんの意見なのですが、問題を解くのとは別に、面白いと思いました。エイリアンの話を出しています。宇宙人のことです。宇宙開発を進めてゆくと、宇宙人が地球の存在に気づき、征服しようとするかもしれない、と書かれています。このような映画を私はいくつも観てきましたから、映画を解きながらも思い出しました。alian と単語、もし私のように宇宙人を最初に連想するならば、少し調べておいたほうがよいと思います。 問2 5人のうち、ChristineさんとVictorさんの意見はどのようなものかを4択から選ぶ問題です。選択肢にある文章が難しいように思います。また、2人の意見の文章も少し難しいので、正解を選ぶのに難しいように思います。 問題を解くのとは、別に、面白いことが書いてあるなと感心しました。 Christineさんは、「国際宇宙ステーション」を例に挙げ、将来、月や火星に居住地ができる可能性がある、と言っています。ただし、不適切な商用利用、軍事利用はNGだと。 -
2025.04.14
共テ-英語リーディングを解く(43)
2025年、共テ、英語リーディング、第8問、解説。 宇宙開発について書かれた文章を読んで解答してゆく問題です。 最初に[Step 1]とあり、「Read a range of opinions」という題がつけられています。rangeという単語、この問題を解くにあたっては、意味がわからなくても、読み飛ばしてよいと思います。というのは、5人のopinionがずらりと並んでいるからです。これまでの経験から、このような見出しは訳さずとも、あるいは、読まずともよいように感じています。この問題のときやすいところは、この5人のopinionを読んで、すぐに問1があるのです。5人のうちのMeilinさんの意見はどのようなものか、4択から選ぶものです。意見というと肯定的なものと否定的なものに大きく分かれるように思います。Meilinさんは、否定的な意見です。私も宇宙関連のニュース等に触れるたびに、疑問をいだくことが多いです。こんなことも問題を解きやすかったようにも思います。意味がわからない、はっきりしない単語や難しい文型の文章が多くても。 -
2025.04.13
共テ-英語リーディングを解く(42)
2025年、共テ、英語リーディング、いよいよ最後の問題、第8問。 文章が理解しやすく、解きやすかったと思います。ただ、長い。設問も含め、6ページも。私が問題を解くにあたっては、いつもどおり、最初の冒頭の文は読まずに進めました。読まなくても全く問題はないと思います。冒頭の文は、6行もあり、少し長めです。読まねば、15秒は時間が稼げるでしょう。 この冒頭の文、第1問から第8問まで、読む時間を累積すると、1分~2分くらいになるのでは。 問題構成も面白いです。読み進めながら、途中に設問が入ってきており、さらに問題文を読み進め、途中に設問が入ってくる構成です。これが問題を解きやすくしているように感じます。また、題材が宇宙開発についてなので読みやすいのではないかと思います。ただし、難しい単語もたくさんあり、難しい文章もたくさんありますから、内容をある程度正確に読み進めてゆかないと、難しい問題になるように思います。 ■共テ攻略のポイント: 速読力!速読力は読む量に比例します。読みまくることです。単語帳の単語の意味を全部覚えようとしても無駄です。覚えるならば、そこにある例文をすべて暗記することです。 -
2025.04.12
共テ-英語リーディングを解く(41)
2025年、共テ、英語リーディング、第7問、解説、続き。 問3 選択肢の英文も少し難しいかもしれません。そして、5択から2つ正しい文を選ばねばなりません。第4段落がしっかり理解できており、選択肢の英文が正しく読めれば、正解できるはず。 問4 Unihemispheric Sleep、6段落にありましたね。片目をずっと開け続けていて、脳の半分が起きていて、脳の半分が眠っている、というものでしたね。4択から正しい文を選ぶ問題です。選択肢の英文はそう難しくはないかもしれません。 問5 7段落に書いている内容に題名をつける問題です。冬眠のような睡眠に似た状態やクラゲがリラックスした状態のことが書かれてます。これにふさわしい題名を4択から選ぶ問題です。 第7問全体については、解き直しをしてみると、そう難しい問題ではないと感じます。初見で、読み直しなく速く読めるようにトレーニングすることが対策ですね。 -
2025.04.11
共テ-英語リーディングを解く(40)
2025年、共テ、英語リーディング、第7問、解説、続き。 第1部の説明文を読み終えました。次は第2部で、発表用にまとめたアウトラインがあります。これの空欄を埋めてゆく形式ですので、これ自体が問題になっていると考えてよいでしょう。 問1 アウトラインの最初の部分に、間違って記載したものがあり、それを消去しなくてはなりません。A~Dの記載があり、間違ったものを選ぶ問題です。睡眠は何のために重要かを選びます。文章全体がよく理解できておれば、簡単かと思います。選択肢の中にalterという単語があります。覚えておかないと解答に迷うかもしれません。本文の2段落にもある単語ですね。(この文がとても難しいと、4/1と4/2に解説をしています。) 問2は、biphasic sleepとはどんなタイプの睡眠か、これを問うています。円グラフが4つ示されており、ここから選ぶ問題です。第3段落に書いてありますね。本文にlike a nap とありますから、これが大きなヒントでしょう。nap という単語も市販の単語帳では載っていないものが多いのでは。 -
2025.04.10
共テ-英語リーディングを解く(39)
2025年、共テ、英語リーディング、第7問、解説、続き。 第7段落は、文ごとの説明は省略しましょう。Hibernationというパターンの睡眠、正しくは、睡眠のような活動、これの説明です。黒クマの冬眠がその例です。最後の文にjellyfishという単語が出てきます。この文自体も少し難しいと思います。Jellyfishの意味が分かると、文全体も分かりやすくなるかもしれません。文全体が理解できると、jellyshとは何かが分かるかもしれません。jelly という単語を知っていると、jellyfishは想像がつくかもしれません。 jelly は日常生活でよく使う言葉で誰もがしっているものですね。そう、ゼリーです。共通テストの特徴の一つは、日常生活でよく使う単語が多く使われていることでしょう。これらの単語は、受験用の単語帳などには載っていないことが多いように思います。単語帳をしゃかりきに覚えこもうとするよりも、多くの文章を読み込んでゆくことのほうが、共通テストに関しては、とても重要で、対策になるように思います。 最後の8段落は、しめくくりのような1文だけなので解説は不要でしょう。 -
2025.04.09
共テ-英語リーディングを解く(38)
2025年、共テ、英語リーディング、第7問、解説、続き。 第6段落 ・3文目 unihemispheric sleepの説明がはじまります。集団で移動する動物で片目を開け続けているものがいる、とあります。 ・4文目 脳の片方が眠っていて、片方が起きている状態で周囲に警戒をしている、とのことです。 ・5文目 これにより睡眠の回復効果を脅威を警戒しながらでもできる、と。 ・6文目 unihemispheric sleepは、集団で長い距離を飛ぶ鳥にみられる、と。 ・7文目 集団の外側を飛ぶ鳥が、この睡眠を使って、両目をつぶって眠っている仲間を守っている、と。 この文を読むと、不思議に思います。内側の鳥たちは、飛びながら眠っているということなのですね。こんなことが出来るのか、と驚きでもあります。以下のような面白い文になっていることに気が付きました。 Birds (途中省略)use this type of sleep to help protect the other members that sleep with both eyes closed. protectの品詞を考えてみると良いと思います。 -
2025.04.08
共テ-英語リーディングを解く(37)
2025年、共テ、英語リーディング、第7問、解説、続き。 第5段落 ・5文目 とても簡単です。うさぎは穴の中で寝るので安全に長く眠れる、と。 ・6文目 対照的に、象は、とあります。この文も簡単でしょう。 6段落 この段落は少し難しいかもしれません。 ・1文目 The animal sleep patterns discussed so far tend to be typical. 日本語で直訳しますと、「これまで議論した動物の睡眠パターンは典型的になる傾向にある。」、何だかわかりにくいですね。無理やり訳さないほうがよいのかもしれません。先に述べられた睡眠パターンとは別の睡眠パターンの説明が始まるのだな、と思って、この文は無視してもよいのではないかと思います。 ・2文目 また新たな睡眠パターンが出てきました。unihemispheric sleep. そうですね、1文目はこれまでと違った種類の、この睡眠をお話してゆくための前置きみたいなものととらえてよいと思います。この睡眠のパターンは日常生活では気づきがたい、と説明しています。典型的なパターンとは違い、特殊なパターンということなのですね。 -
2025.04.07
共テ-英語リーディングを解く(36)
2025年、共テ、英語リーディング、第7問、解説、続き。 第5段落 3文目のapes の単語もありましたが、platforms の単語もあります。経済ニュースなどを見ていると、「プラットフォーム」という言葉が使われることが多いように感じます。私は、日本語で言えよ、といつも感じているのですが。こう思うのは私だけでしょうか。皆さんが使ったり、連想するのは、駅のホームではないでしょうか。この問題文、Apes sleep on platforms, high above the jungle floor...とあり、ここでの意味は、木の高いところの位置、くらいにとらえてよいのでしょう。 ・4文目 簡単な文です。うさぎのような小さな動物は地中に穴をほってすみかにしている、と。この文の中にpredatorsの単語があります。私のようなじじいの年代は、この単語は簡単に覚えられます。A. Schwarzenegger主演の映画にこの題名があるからです。大学受験用の単語帳にも出ている単語でした。同じく主演の名作映画「Terminator」があります。terminate の単語、覚えたほうがよいです。 -
2025.04.06
共テ-英語リーディングを解く(35)
2025年、共テ、英語リーディング、第7問、解説、続き。 前掲、ちょっとミスがありました。肉食獣と草食獣の睡眠の違いだけ、ではありませんでしたね。ネズミやリスの小動物のことも書いてあります。失礼しました。 第5段落 ・1文目 安全が睡眠パターンを変える。 ・2文目 安全な場所がある動物は睡眠時間が長い、しかし、。。。とあります。この文、後半難しいのでは。 Animals that can create safe spaces tend to enjoy longer periods of sleep, but those that might need to stay alert sleep less.後半の文のthatの説明、この文の動詞がどれか、説明はつくでしょうか? ・3文目 Apes という単語が出てきました。動物の名前と推測できますが、何でしょう?知らなくても、アプスという動物だと思えばよいだけです。ジャングルの高いところで寝る、と。猿かもしれません。辞書で調べました。発音が[eips]でした。アプスではありません。単数形がape で「類人猿、または広義でサル」とありました。 -
2025.04.05
共テ-英語リーディングを解く(34)
2025年、共テ、英語リーディング、第7問、解説、続き。 第4段落: ・2文目と3文目 ねずみやリスは動き回ってエネルギーを消耗する、よってしばしば、しかし短い時間の睡眠をしばしば必要とする ・4文目 ライオンは肉食動物で消化に時間がかかるので長く睡眠をとる ここの英文中の一部、少しわかりにくいかもしれません。紹介しておきます。 because their food sources satisfy their hunger for longa periods 私は、単に消化に時間がかかる、としていますが、food sourcesをどう訳すべきなのか難解です。ライオンが食べる肉のことなのでしょうが。この文の中に、carnivorousの単語があります。こんな単語は知らなくてよいと思います。専門用語の域にある単語と思います。続く5文目に馬のようなherbivoresとありますから、肉食獣、草食獣の意味だと理解できるはずです。 ・5文目 馬のような草食動物は、その一方で、とあります。睡眠が短いと。そして理由が述べてあります。 第4段落は、単に、肉食獣、草食獣の睡眠の違いを述べているだけです。文も簡単です。 -
2025.04.04
共テ-英語リーディングを解く(33)
2025年、共テ、英語リーディング、第7問、解説、続き。 第3段落 ・1文目 異なった睡眠パターンあり ・2文目 3つのパターン、⓵monophasic ②biphasic ③polyphasic を示しています。これらを順番に説明してゆくことが容易に分かると思います。 ・3文目 ⓵monophasicの説明です。人間などがこれにあたり、何時間か活動し、何時間か寝るパターン ・4文目 ②biphsicの説明。起きている時間と寝ている時間が2回あるパターン。うち1回の睡眠は居眠り程度だと。 ・5分目 ③polypasicの説明。犬や猫がこれだそうです。1日4~6回の睡眠と起きている時間を繰り返すパターン。 次の4段落目にどうつながってゆくのでしょうか。これだけみると、3つのパターンが紹介されているだけなので、さらに深堀させた文章になってゆくのでしょうか? 第4段落 ・1文目 animai's size, physical needs, and dietによって睡眠パターンがいろいろある。なんだか、第3段落を発展させてゆくような感じではなく、違った角度から睡眠のパターンを見てゆくのでしょうか。 -
2025.04.03
共テ-英語リーディングを解く(32)
2025年、共テ、英語リーディング、第7問、解説続き。 第2段落、3つ目、4つ目の文、簡単でしょう。第3段落につなげてゆくための文です。種により睡眠のパターンが異なっている、と述べています。ということは、第4段落から、いろんなパターンの説明があるはずだと推測できるでしょう。 第3段落: Different sleep patterns are identified. 核となる文がこれです。(省略して書いています。)identified、ここをうまく訳すことが出来るでしょうか?受け身になっていますね。「受け身」の文章、共テ、その他大学入試には、おそろしく多く出ています。英語においては、日常的にしょっちゅう出てくるものです。多読すると慣れてゆくはずです。単語帳では、「~を特定する」と出ています。「パターンが特定される。」と訳してもよいのでしょうが、私は、「パターンが認められる」と訳して解いています。文の意味が分かればどちらでもよいのでしょうが。単語帳だけの単語勉強には限界があるように、これまでもずっと述べてきています。この単語、「IDカード」をいつも連想し、そこから意味を導き出しています。 -
2025.04.02
共テ-英語リーディングを解く(31)
2025年、共テ、英語リーディング、第7問、解説です。 第2段落、2つ目の文、難しいと思います。そのまま見ておきます。 For animals with brains and central nervous systems, sleep is generally defined as an altered state of consciousness characterized by specific body positions, closed eyes, a general decrease in physical activity, and slower response rates. 後半部分のように、〇、△、□、and ■とつなげられると読みづらくなるかもしれません。大事なことは、〇、△、□、■がどこにかかってゆくかを混乱しないようにすることでしょう。もし混乱するようならば、しっかり精読して、文の構成がどうなっているかをじっくり確認することが必要です。こうした作業をしっかり時間をかけてやってゆくことで、初見の英文がしっかり読めてくるようになるはずです。 -
2025.04.01
共テ-英語リーディングを解く(30)
2025年、共テ、英語リーディング、第7問、解説です。 第2段落: ・1つ目の文: 意味は読み取れるように思います。単純な文に並列した情報が付加されているだけですが、情報が増えるだけで、読み取りが難しくなる生徒もいるでしょう。 SVCの文章なだけです。「睡眠は不可欠だ。」これが核になる文。これに、何にとって不可欠かを加えてます。「動物の健康にとって」、と言っています。さらに「動物の体にとって」と並列させて情報を加えています。さらに、for their bodies to function efficiently と余計なものがくっついています。文法がわからなくても読めるでしょう。しかし、「function」の品詞が何かは、読み直し、解き直しするときには、分かっていたほうがよいと思います。 ・2つ目の文: 読解力がないとかなり難しいと感じると思います。何せ文が長いのです。4行もあります。少し難しい単語がちらほらありますから。核になる文がこれです。 Sleep is defined as an altered state of consciousness.です。うまく訳せて意味がつかめるでしょうか? -
2025.03.31
共テ-英語リーディングを解く(29)
2025年、共テ、英語リーディング、第7問を解きます。 題が「動物の睡眠パターン」。毎年出る自然科学系の説明文です。配点は16点。3点が4問で、4点が1問。冒頭の状況説明の文章は、これまでの問題と同じように、読まずに進めても大丈夫だと思います。問題構成は、動物の睡眠に関する記事と、記事内容を発表するためのアウトラインの2つで構成されています。アウトラインの空欄箇所に適切な文章などをあてはめてゆく形式です。問題文は2ページにわたり、ずっしりとあります。難しい単語も増えている印象ですし、科学者が使う専門用語が出ているので、訳さずともよいのですが、読みにくくなっている印象です。難しい問題と感じた受験生も多かったのでは。記事は8段落構成です。順番に見てゆきます。 第1段落: 書き出しの文。家の猫、人間の睡眠を例に挙げています。導入部分の文章で、簡単に理解できますし、文章の中での重要度はほとんどないです。よって、問題を解くにあたっては、なんら影響なしです。 第2段落: 急に難しく感じるように思います。2つ目の文が4行もあり、長いのと、少し難しい単語があるせいで、読み取りを難しくさせるかもしれません。 -
2025.03.30
共テ-英語リーディングを解く(28)
2025年、共テ、英語リーディング、第6問、続きます。 問2は、Melodyはどんな超能力を持っているか、選ぶ問題です。これは、A~Fの6つの内容から、4つを選ぶ問題ですので、厄介かもしれません。合っているものを探しながら、消去法でやってゆくとよいのでは。私は、音を完璧にまねできる、のBは正解なので、選択肢の②にBがないので、まずは、これを消去しました。Aは、高いところを飛ぶ、なので、この能力は書かれていないので、間違い、よって、⓵も消去しました。残る③、④で、Fは、瞬間移動ができるとあるので、これを含まない③も消去、残る④が正解だとわかります。 問3は、主人公の母が後悔したことについて答えればよいのですが、第3章がしっかり理解できておれば、簡単です。問4は、物語に書き加えるとよいのはどれか、5択から2つ選ぶ問題です。私のように、きちんと読めなかったら、難しく感じるように思います。 第6問の解説はこれで終わります。私にはどう解説してよいのか、戸惑ってしまうような問題でした。皆さんは、この問題をどう思ったのか、感想を聞いてみたいです。 -
2025.03.29
共テ-英語リーディングを解く(27)
2025年、共テ、英語リーディング、第6問、続きます。 第3章、こんな文もありました。 Someday, when the time is right, you'll meet her. このright、どんな訳がよいのでしょうか?調べて見ました。この表現は、日常会話ではよく使われているそうです。今回の問題は物語文ですし、物語文をたくさん読んでおくと、きっとこの表現に触れることがあるのでしょう。多読することですね。 第3章の後半で、主人公は特殊能力を使って、ハイカーを助けることにし、それがもとで、ヒーローのチームにスカウトされた、とあります。そして、最後の第4章、Melodyがヒーローのチームを去るとの知らせがあり、そこから主人公とMelodyは一緒に働いた。こんな物語です。 次が第2部で、この物語の作者へのフィードバックのメールがあります。ところどころ空欄があり、これにふさわしい解答を選ぶ形式になっています。問1は、主人公の成長の様子を古い順に並べるものです。物語では、時の順ではないですが、簡単に答えられるように思います。5択あり、うち1つは全く関係ないことで、これが少しいやらしい問題ですね。 -
2025.03.28
共テ-英語リーディングを解く(26)
2025年、共テ、英語リーディング、第6問、続きます。 第3章、6行目から難しいと思いました。 I learned my parents had been told to send her to a special facility for extraordinary children, because her powers could help humanity. "Someday, when the time is right, you'll meet her. I know now that we should never have let her go. We won't let that happen to you, " said my mother. 解き直しでじっくり丁寧に訳してみると、理解できました。本番で一発で理解できるようにならないといけません。had been told to send, never let her go, won't let that happen, ここが私には一発目では難しかったです。多読、精読を繰り返してのトレーニングしかないように思います。 -
2025.03.27
共テ-英語リーディングを解く(25)
2025年、共テ、英語リーディング、第6問、解説続きです。 ヒーローの物語、どんなお話なのかまとめてみます。4章の構成です。 第1章: 私は、世界的に有名なBluebirdというテレビ番組の中でのスーパーヒーローである。6人のメンバーの一人。有名になりたいがため、にせヒーローだと気づいていなかった。 第2章: ある日の番組収録。Bluebirdが下水溝に落ちた猫を助ける設定。下水溝には番組制作スタッフも猫と一緒にいたのだが、猫が本当にいなくなってしまった。そこへ突然、スーパーヒーローの一人、Melodyが現れた。Melodyは瞬間移動が出来、猫の鳴き声など、どんな音でも出せる能力を持っている。MelodyはBluebirdに、「猫はあなたを信用していない。」と言って、猫の鳴き声を出して、猫を見つけ出した。猫を救出したと自慢しているBluebirdに、Melodyの「馬鹿げている。」との声がどこからともなく届いた。 第3章: Bluebirdの子供の頃の話で、空を飛べる能力を持っていることにある日気づいて。。と続きます。 私の場合ですが、この3段落の内容がはっきり読み取れませんでした。次回に続く。 -
2025.03.26
共テ-英語リーディングを解く(24)
2025年、共テ、英語リーディング、第6問、解説続きです。 この問題の開設、難しいです。どんな問題かを振り返ります。冒頭の説明文は、問題を解くときには読む必要なし、と私は言い続けていますが、読んで、どんな内容なのかを知りましょう。Harryは作家を目指しており、コンテスト応募用に2人のヒーローの物語を書いて、あなたがそれを読んで感想を与える、というものです。問題文は、その物語と、読んだ感想のメール文の2部構成です。物語は4章に分かれています。瞬間移動ができるなどという、現実離れしたお話が含まれており、私の場合ですが、内容がとらえがたかったように思います。そういえば、当塾の英語の先生が、生徒に「ハリーポッター」のペーパーバックを読んでみることを薦めていました。今回の問題には、このような対策が必要なのかなと感じました。いろいろなジャンルを多読しておくことが必要なのでしょう。 -
2025.03.25
共テ-英語リーディングを解く(23)
2025年、共テ、英語リーディング、第6問、解説続きです。 3段落目、「ある日のこと」、で始まります。そう難しくないと思います。最後の1文、こんな文でした。 The truth was, a member of the television crew was waiting in the underground drain with the cat. 私は、このような形の文は初めて見る気がします。was のあとに、「,」があります。この文の意味としては、 The truth was that a member ~. のSVCの文で訳せばよいのかと思います。接続詞のthat を「,」で代用するという用法があるのでしょうか?私の宿題として、調べなくてはなりません。手っ取り早く、トライプラス国分寺駅北口校の英語の先生に聞いてみようと思います。 4段落目、これも難しくないと思います。5段落目、Suddenly, で始まります。スーパーヒーローの一人のMelodyが現れるのです。テレビ番組の内容なのか、実際に起こった話なのか、訳が分からなくなってしまっていました。読み直しをしても、よく分かりません。 -
2025.03.24
共テ-英語リーディングを解く(22)
2025年、共テ、英語リーディング、第6問。私にとってはかなり難しかったので、とことんまで解き直しが必要かと思います。意訳も含み、日本語に訳せない英文が多かった印象です。これを克服するには、多読をしてゆく、つまりそれなりの日数をかけてトレーニングが必要になるのかと思います。受験生の皆さんは、共通テストまで日数はたくさんありますから、共通テスト満点を目指すこともまだまだ出来ますよ。 問題を解くにあたり、ここでも、冒頭の場面説明の文は読みませんでした。2行ほどの文。読まなくても大丈夫かと思います。最初の文が、スーパーヒーローである、なんて始まります。私はここで、なんだこれは、感じました。フィクションを描いているのだな、嫌だなあ、と。こういう直感はあたるもので、案の定、内容を詳細にとらえられませんでした。最初の段落は読み取れました。2段落目も。最後の文がI was unaware that I was a fake superhero.でしたが、ここも訳せました。形容詞にunawareのような否定の意味の単語があると、戸惑うことが私の場合、あります。これも多読でカバーできることです。 -
2025.03.23
共テ-英語リーディングを解く(21)
2025年、共テ、英語リーディング、第6問を解きます。2023,2024年の過去問を解いた経験から、第4問から一気に難しくなると予想していたのですが、第5問まで、とても簡単な文章でした。いよいよ第6問からは難しくなるはずだ、と解き始めました。とても難しいです、私にとっては。案の定、配点12点中、6点しか取れませんでした。ここまで、67点中、47点の得点です。20点も失っています。ここまでの得点率が70%です。 私にとって、何が難しかったかというと、分からない単語はほとんどなかったのですが、日本語に訳せない文章が多かったように感じました。解くに真ん中からそれ以降。解くにあたって読み直しをして時間を使いすぎました。これで最後の問題までたどり着けないことになります。このようなとき、本番でどう対応すべきかも考えておいたほうがよいでしょう。思い切って、次の大問に進むのもありかと思います。次の問題が解きやすいこともあるからです。 -
2025.03.22
共テ-英語リーディングを解く(20)
2025年、共テ、英語リーディング、第5問、解説、続きです。 単語チェックをしてみます。簡単な単語ばかりです。意味や品詞が分からないなら、単語力が足りないと思って、頑張って勉強してください。 ✅in charge これは連語です。よく使います。 ✅servant ✅preserve ✅mayor ✅anxious ✅draft (第4問についての解説で、3/16に掲載している、第4問の解説でも書いている単語) ✅venue これは私が分からなかった単語。分からなくても文脈からなんとか意味を導きだせます。私は駄目でしたが。 ✅reserve ✅material ✅permit ✅provide ✅suggestion 発音注意です。 ✅diagram これらの単語を見る限りでも、問題文はかなり平易であるとわかるでしょう。 -
2025.03.21
共テ-英語リーディングを解く(19)
2025年、共テ、英語リーディング、第5問、解説、続きです。 単語のチェックをしようと思ったのですが、最初から不定詞が連発しています。前掲の「help organize」もそうですね。 ✅I am happy to be the representative…. ✅This event is to promote the local economy. ✅I hope to work as a civil servant…. 最初の3行の文にこれだけ。さらに、 ✅I would like you to confirm…. ✅Below is a list of things that still need to be decided. 2つ目の先生の返信には、そう多くはないですが、数か所ありました。 上記中には、不定詞の他、関係代名詞、受け身の用法も含まれていますので、文法事項がしっかり説明できないのであれば、中学校のテキストで復習してもよいと思います。大学受験は”高尚な"問題を解いてゆかねばならない、と思っている生徒も多いかもしれません。共通テストに限っては、9割がた中学の文法事項で読めるでしょう。 -
2025.03.20
共テ-英語リーディングを解く(18)
2025年、共テ、英語リーディング、第5問、解説、続きです。 You will help organize a special conference for local businesses. 前掲で、問題の冒頭にある場面・状況の説明の文にある文を示しました。 この文の主語、動詞、簡単に答えられるはずです。次にorganizeの品詞、この文の文型は答えられますか? 注目してほしいのは、help organize の部分です。この表現はおそらく教科書には出てきていないように思います。もしかしたら大学入試には出てきており(共テには過去にもすでに出ています)、そのうち教科書に載ってくるように思います。これを高校の授業では教えていないのではないかと思います。辞書で調べると説明がありますので参照してみるとよいでしょう。 そんな文法事項が分からなくても、問題が解ければよいのだ、と思っている生徒もいるかもしれません。共通テストで満点をとれさえすれば、それでよいのだ、これも意見として正しいのかもしれません。私は、きちんとした文法の知識も学習しておくべきのように思っています。 -
2025.03.19
共テ-英語リーディングを解く(17)
2025年、共テ、英語リーディング、第5問、解説です。 語数がここから1.5倍くらいに増えています。問題も、先生へのメール、先生からのメールと2種類の文章で構成されています。学生がイベントを企画し、その内容を先生に伝え、先生がアドバイスを伝える、といった内容です。これまでずっと解説してきたように、私は、冒頭の状況説明文は読まずに解きました。これは3行の文で、読まないと少しは時間稼ぎができるように思います。解き直しで読んでみました。上記に伝えた内容どおりで、読む必要なく問題は解けるはずです。 語数が増えたようですが、イベントの日程表が占めるスペースも少なくないので、ページ数の割には長くはなく、時間もあまり取られないように思います。何にせよ、問題文は難しくはありません。 冒頭文は読まなくてよい、と申しました。実は、とても興味深い表現があります。 You will help organize a special conference for local business. 興味深い、と私が言ったことにうなずいている生徒は、かなり英文法を勉強しているように思えます。 -
2025.03.18
共テ-英語リーディングを解く(16)
2025年、共テ、英語リーディング、第5問を解きます。 第4問が、難しくなるぞ、と構えていたところ、そうでもなかったので、ここから難しくなりそうで嫌だなあ、と思いながら解きました。そうでもありませんでした。語数も増えて長くなっていますが、割とすらすら読めたと思います。第5問、配点は16点。第1問からここまで55点。問1~問5。問2が2箇所あり、各2点。他は各3点。私は、問3が不正解。3点失いまして、ここまでで14点の失点です。よって、ここまでの得点率は74%です。解き直しで読み直しましたが、「参加登録〆切が7日前は短すぎる。」とライアンさんがアドバイスしていますので、これを解答につなげなければなりませんでした。もうひとつ、間違えた原因が、venueの単語の意味が分からなかったからのように思います。選択肢にMain Hall as the venue とありました。よくよく考えると、Main Hallだけでも解答できましたから、知らない単語があると焦ってしまうのだな、と感じます。 -
2025.03.17
共テ-英語リーディングを解く(15)
2025年度、共テ、英語リーディング、第4問、続きです。 出ている単語をチェックしています。上級者には不要です。知らない単語があれば、平均点以上とることは難しいのでは。春休み、徹底的に単語力の強化が必要だと思います。 ☑ improvement ☑ instead ☑ notice ☑ describe ☑ belonging ☑ consume ☑ recommend ☑ reduce ☑ possession ☑ manner 日本語になっていますが、それが先行しすぎているように思います。英語としてしっかり辞書で確認しておいたほうがよいように思います。 ☑ face-to-face ☑ appear ☑ impolite ☑ affect ☑ negatively ☑ aspect ☑ significant ☑ fulfillmnet ☑ summary ☑ avoid ☑ rewarding ☑ appropriate ☑ concluding ☑ paragraph ☑ argument ☑ content ☑ moreover ☑ otherwise ☑ replace ☑ satisfied ☑ decrease ☑ outcome -
2025.03.16
共テ-英語リーディングを解く(14)
2025年度、共テ、英語リーディング、第4問、続きです。 ポイントを示すようにしてきておりますが、この問題の場合は、どう言っていいやら。すらすら読めて内容理解できるよう語彙力、文法力は高めておきましょう、このくらいしか言えません。過去問や模試の問題、問題集を利用して多読するに限ります。 問題の題材は、おもしろいものです。スローライフを試そう、というものです。中学生、高校生は、とにかく忙しい、それが一番だと思います。スローライフということはおそらく全く考えにくいものでしょう。社会人となって、ふと立ち止まってみる機会を得る、そこで試してみようかな、と思うのかもしれません。 今回はどのような単語が出ているかを示しておきます。確実に覚えておくべき単語ばかりと思ってください。意味がわからないならば、単語力不足だと思ったほうがよいでしょう。 ☑draft 冒頭の説明にある単語です。「ドラフト」、プロ野球選手などのドラフト会議、社会人になるまで私は、この意味しか知りませんでした。辞書で調べると、この単語、面白いと思いますから引いてみてください。draft beer というのもありますね。これは保護者様向け。 -
2025.03.15
春期講習スタート!
トライプラス国分寺駅北口校の2025年春期講習がまもなく始まります。 3/17(月)~4/8(火)の期間です。期間中は、通常期とは異なり、すべての曜日で開校時間が13:00~22:00です。日曜日はお休みです。20日ありますから、テーマを絞った短期集中型の学習ができます。 春期講習コースの例。 ✅英検特訓コース(準1級~5級まで対応可能)(TEAP, TOEIC, TOEFL, IELTSなども対応可能) ✅数検、算数検定特訓コース(準1級まで対応可能) ✅共通テスト対策コース ✅大学入試過去問対策コース ✅大学入試対策、基礎力充実コース ✅都立高校受験対策コース ✅中学受験対策コース(難関校対策も可能) ✅新学年先取りコース この春休みからの通塾で、新学年での学習、受験勉強にはずみをつけてゆきましょう。 -
2025.03.15
共テ-英語リーディングを解く(13)
2025年度、共テ、英語リーディング、第4問、続きです。 ■ポイント 問題構成の変化への対応力を! 前掲で書いたように、難しくなってくるぞ、と慣れてしまっていたのが、簡単に読める文章、設問も難しくないと感じました。途中で気が付くのですが、これまで、第6問までの構成が、第8問までの構成になっております。こんなことで戸惑わないでね、と言っても、私もそうですが、あれれ、と戸惑って、焦ってしまうこともあるかもしれません。過去問を徹底的に研究しているから生まれる焦りなのかもしれません。かつて設問毎の標準時間を示して、予定どおりに解き進めてゆくことを提案しました。これをやると、今回の共テは、予定が狂ってしまい、焦りを招いてしまうかもしれません。問題構成の変化があるのだと認識しておくことですね。対応力を!、と安易に言ってしまいましたが、結局は、多くの問題を解きまくり、英語力を高めることが対策なのでしょう。 -
2025.03.14
共テ-英語リーディングを解く(12)
2025年度、共テ、英語リーディング、第4問。 ■ポイント 冒頭の状況を説明した文章は読まなくてよい! 問1~4、各3点で、12点の配点です。ここまでで39点あります。2023、2024を解いたときには、第3問から難しくなり、解くのに嫌だなあ、という感想を持った記憶があります。しかしながら、第3問、第4問とも、簡単に感じました。 簡単と言えども、私は問1を間違えました。これは完全なうっかりミスです。真逆の意味の単語を選択してしまいました。3点失い、ここまでで11点も失っています。ここのミスは、とても悔いが残ります。どうか受験生の皆さんは、模試でこのような失敗をして、本番ではないように! 私が問題を解くにあたっては、これまでどおり、冒頭の状況説明をした文は読みませんでした。今回は3行と文字数が増えていますから、短縮できる時間も少し多めです。問題文を読みながら、生徒が書いた文章を先生が添削をしてくれている状況なのだな、と思いました。解き直しで、冒頭の文を読むと、まさにその通りでした。 -
2025.03.13
共テ-英語リーディングを解く(11)
2025年度、共テ、英語リーディング、問3、続き。 ■ポイント 多読が必要! こんな文がありました。 From that day on, our focus shifted and the band took a step forward on its musical journey. 解き直しで読み直していますが、onとmusical journey、がよくわかりませんでした。 1. on から調べてみました。辞書のfromの箇所に、from then on, from now on があり、『継続を明確にするため「ずっと」の意の副詞が添加される』、とありました。これでしょう。 2. musical journey、なんだかよくわかりませんが、私の勝手な解釈ですが、バンドとして目指すべき方向に進んでいった、ということなのでしょうか? 語彙力、文法力が大事なのでしょうが、多読して多くの表現に触れてゆくことが大事なように感じます。そう思うと、「英語力を効率よく高めるために」などとは考えないほうが良いように感じます。単語帳を四六時中見ているよりも、辞書を四六時中引きまくっている生徒のほうが強い気がします。 -
2025.03.12
共テ-英語リーディングを解く(10)
2025年度、共テ、英語リーディング、問3、続きです。 ■ポイント 問題文の内容理解は、なんとなく、では駄目! 前掲で簡単な文章です、と書きました。簡単なようで、実は難しいように解き直していて気が付きました。きちんと日本語で訳せるかというと、訳せていないのです。詳細に正確に読み取れていない証拠だと思います。私の場合ですが、これが弱点なので、ここを強化してゆくようにする必要があるのです。受験生の皆さんも弱点があればそれを発見し、それに対処してゆくことで得点力をアップしていただけたらと思います。 バンドメンバーのリーダーが書いたお話で、どうもしっくりこない自分たちの演奏に違和感を持ち、録画した演奏を聞いて、気が付いた、とあります。 Each of us is showing off. We're playing for ourselves, not for the band!、とありました。最初の文が私は訳せませんでした。show off を辞書で調べると、「ひけらかす」、でした。問題を解くには影響ない箇所なのですが、実力UPのためにも、解き直して完璧にしてゆくことが大事だと思いました。 -
2025.03.11
共テ-英語リーディングを解く(9)
2025年度、共テ、英語リーディング、問3を解きます。 ■ポイント 「簡単な文章なのですが、全問正解できないのはなぜ?」→注意深く読んでいなかったから。 ここでも、冒頭の説明文は読まずに解きました。読む必要はないと思います。解き直しで何が書いてあったかを確認しました。「あたなは交換留学生でUKの高校にいる。先生が、おもしろいお話を見つけてと頼んで、こんな話を来週クラスで発表することにした。」(ちょっと直訳からひねってます。) 問題文は簡単です。しかし、私は問2が不正解。書いてある内容が選択肢にあり、それを順番に並び替える問題です。解き直しで愕然としました。私が間違えた理由、registered をresigned と勘違いして読んでいました。とんでもないミスですね。The band registered for a contest. こんな選択肢です。resignの後にforが続くことはありませんね。問1~3の構成で、配点が各3点。合計9点。ここまでトータルで27点で、8点も私は失っています。解き直しで間違えた理由を徹底的に分析することですね。本番で高得点を取ればよいのです。 -
2025.03.10
共テ-英語リーディングを解く(8)
2025、共テ、英語のリーディングの第2問、解説、続きです。 ☑ would 問題文では、Emergency services would be improved. から始まり、would を使った文がさらに3つ続きます。文法書では、「助動詞」の章で説明がされているはずです。しっかり勉強しておきましょう。 さらに以下の文がありました。 Someone in the audience asked if flying taxis would soon be available around the world. ここでのwouldは、上記のwouldとは用法が違うことは分かりますね。しっかり文法的な説明ができるように。 ☑ assessment 問2に出ています。environmental assessmentの日本語はよく聞くと思いますので、意味も大丈夫と思います。a tax assessment の言葉も知っておいたほうがよいかと思います。 問題とは別に、上記のenvironmental、発音、そして、つづりが書けるようにしておいたほうが良いです。入試、英検などで書くことがきっとあるはずです。 -
2025.03.09
共テ-英語リーディングを解く(7)
2025、共テ、英語のリーディングの第2問、解説です。 読むには難しくない問題でしょう。どんな単語が出ているのかを見ます。 ☑ zero-emission 最近よく聞くようになった言葉です。CO2を出さない、とのことと思いますが、emission は日本語でどう訳しますか?辞書を引きます。 「1.(光・熱・ガスなどの)放出 (2.以下は省略)」です。英英辞典を引くと、以下を発見。 emissions trading = carbon trading a system that gives contries and organizations right to produce a particular amout of CARBON DIOXIDE and other gases that cause GLOBAL WARMING, and allows them to sell this right Zero-emissionについての話題は、今後もますます出題されてくるように思いますし、今年度の多くの大学で出題があったように思います。探せましたら、紹介してみたいと思います。 -
2025.03.08
合格報告!( 3/8 12:15時点)
*複数合格は⦅⦆書きで記載 ■国公立大学 東京都立大学 理学部 数理科学科 合格! ■私立大学 上智大学 外国語学部 ロシア語学科 合格! 東京理科大学 創域理工学部 数理科学科 合格! 立教大学 観光学部 交流文化学科 合格! 学習院大学 法学部 政治学科 合格! 中央大学 理工学部 数学科 合格! 中央大学 理工学部 生命科学科 合格! 法政大学 生命科学部 環境応用科学科 合格! 東洋大学 国際観光学部 国際観光学科 合格!⦅2⦆ 東洋大学 国際学部 国際地域学科 合格!⦅2⦆ 東洋大学 生命科学学部 生命科学科 合格! 成蹊大学 理工学部 データ数理学科 合格! 芝浦工業大学 工学部 物質化学課程化学・生命工学コース 合格! 工学院大学 先進工学部 生命科学科 合格! 日本獣医生命科学大学 獣医学部 獣医保健看護学科 合格! 麻布大学 生命・環境科学部 環境科学科 合格! ■都立高校 田無高校 合格! ■私立高校 日本体育大学桜華高校 合格! トライプラス国分寺駅北口校の生徒の2025年度入試の合格実績を報告しております。 おめでとうございます! 3/8(土)12:15までにご報告をいただいた合格実績を掲載。 -
2025.03.08
共テ-英語リーディングを解く(6)
2025、共テ、英語リーディングの第2問。問1~4、配点各3点で、合計12点です。 ■ポイント: 冒頭の説明文は読まずともよい! 私は問4を間違えました。これで第1問、第2問までで5点を失いました。述べられていることを選べという問いなのですが、素直に選ばずに考えすぎたことが原因でしょう。 問題文の題材は、「空飛ぶ車」についてです。昨今話題になることが多く、受験生にも親しみのある話題で、読みやすかったように思います。難しい単語もありませんし。 私が解くにあたっては、これまでずっと解説してきたように、冒頭の説明文は読みませんでした。時間を少しでも短縮するためにも、受験生の皆さんも読まずともよいと思います。何が書いてあるかというと、「未来の輸送についてレポートをするにあたり、それについて書かれたブログを読みます。」、です。「空飛ぶ車」について書かれたブログを読んで、そこに書かれていることについて質問されているので、前置きの説明を読む必要は全くないのです。 -
2025.03.07
共テ-英語リーディングを解く(5)
2025、共テ、英語リーディング第1問、続き。 ■Point 1. 簡単な単語でも馬鹿にせずに! 2. 基本的な文法事項も再確認! shallow 皆、意味は分かるでしょう。恥ずかしながら、私は分かりませんでした。どこかで見てきているはずです。定着していないのですね。deepの反対ですね。解くには支障なしでしょうが。 Avoid any plastic or rubber items not intended for aquariums. こんな文が。解くには支障なしでしょうが、intended を上手に訳すことは以外に難しいように思います。辞書にわかりやすい例文がありました。These flowers are intended for the party. intended の文法的な説明も大丈夫ですね。notがついていない形で勉強することが多いかと思いますので、こういう形にも慣れておく必要はあると思います。 設問文にこんなのが。 The customers most likely to benefit from this pamphlet are ~. benefitの品詞は分かりますね。 -
2025.03.06
共テ-英語リーディングを解く(4)
2025、共テ、英語リーディングの第1問、続きです。 ■Point 1. 簡単な単語でもしっかり調べてみましょう。 2. 基本的な文法事項も確認しておきましょう。 点数が取れれば、それで十分なのですが、きちんと問題文が理解できているか、つまり、きちんと日本語に訳せるのかを、解き直しで確認したほうがよいと思います。単語と文法が確実に身についていることが必要なのかと思います。 最初にaquarium の単語が出てきます。挿絵もあるので、これを水族館と訳す生徒はいないとは思います。家庭で魚を飼うための水槽だな、とすぐに分かります。おそらく、ほとんどの方が水族館として勉強してきたように思います。水槽の意味もあるのですね。 freshwater の単語もありました。これは「淡水の」という意味ですね。淡水魚を飼うために、どのような水槽としなくてはならないかを初心者向けにパンフレットで説明したものですね。意味が分からなくても創造がつくでしょうから、問題を解くには問題ないです。「海水の」は? salt-water です。こんな風に辞書を調べてみることは無駄にはならないと思います。 -
2025.03.03
合格報告!( 3/3 9:30時点)
本日は、都立高校の合格発表日です。 【都立高校】田無高校 合格! 【私立高校】日本体育大学桜華高校 合格! 【私立大学】*複数合格は⦅⦆書きで記載 上智大学 外国語学部 ロシア語学科 合格! 東京理科大学 創域理工学部 数理科学科 合格! 立教大学 観光学部 交流文化学科 合格! 学習院大学 法学部 政治学科 合格! 中央大学 理工学部 数学科 合格! 中央大学 理工学部 生命科学科 合格! 法政大学 生命科学部 環境応用科学科 合格! 東洋大学 国際観光学部 国際観光学科 合格!⦅2⦆ 東洋大学 国際学部 国際地域学科 合格!⦅2⦆ 東洋大学 生命科学学部 生命科学科 合格! 成蹊大学 理工学部 データ数理学科 合格! 芝浦工業大学 工学部 物質化学課程化学・生命工学コース 合格! 工学院大学 先進工学部 生命科学科 合格! 日本獣医生命科学大学 獣医学部 獣医保健看護学科 合格! 麻布大学 生命・環境科学部 環境科学科 合格! トライプラス国分寺駅北口校の生徒の2025年度入試の合格実績を報告しております。 おめでとうございます! 3/3(月)9:30までにご報告をいただいた合格実績を掲載。 -
2025.03.03
共テ-英語リーディングを解く(3)
2025、共テ、英語リーディング第1問。 ■Point 1. 問題構成に変化。2部構成から1つに。配点10点➡6点。 2. 冒頭文章は読む必要なし➡時間確保のため 過去問をしっかり解いてきた生徒は、あれっ、と思ったかもしれません。これまで、第1問はAとBの2部構成だったのが、ひとつだけに変わっていました。よって、配点もこれまで10点あったものが、6点になっています。 2024年度の解き方解説では、冒頭の状況説明の文章は、第1問から第6問共通して、読む必要はない、とお伝えしてきております。よって、私も読まずに解きました。今回の第1問は、解き直しでは読んでみましたが、やはり、読まなくても解いても問題ないと思います。 私が間違えた問3、水槽の飾り物、自然由来のものと人工的につくられたもの、しっかり読まずに読み飛ばしていて、熱帯魚を買った経験が邪魔をしたようです。先入観や自分だけの常識で解いてはいけないですね。イラストとAvoid any plastic or rubber items、の文から正解を得られるはずです。簡単な文章のようですが、情報量が多いので、そこが問題を難しくしているように思います。 -
2025.03.02
共テ-英語リーディングを解く(2)
2025年度、共テ英語リーディングを一緒に解きながら、解説をしてゆきます。 問1に入る前の冒頭に、解答番号の表記があります。1~44とのことです。前年2024年度、前々年2023年度は1~49でした。 マーク箇所が5つ減ったことになります。こんなことは気にせずによいです。また、この冒頭の日本語の指示の文は読まずともよいです。共テ英語リーディングは速読力を最も問われます。最後まで解き終えるには、偏差値が58くらいないと無理なように思いますので、1秒でも余計な箇所は読み飛ばして時間を確保できるようにしてみてください。 第1問。例年と同じく、パンフレットが示されています。Aquarium、そしてBeginners!、とあります。ご家庭で熱帯魚などを水槽で飼いたい人に方法を教えているもののようです。3つポイントが書いてあります。 1.どんな魚を飼うか 2.飾り物を選ぶ 3.飾り物の配置 問は1~3の3つ。各2点で配点が6点。私は、問3を間違えてしまいました。これは以外に難しいかもしれません。間違えの原因は、しっかり読めていなかったことです。私の場合は、きちんと読み返しをすれば、得点できたと思います。 -
2025.03.01
共テ-英語リーディングを解く(1)
2025年度(令和7年度)の共通テストが1/18, 19に実施されました。少し遅れましたが、私も、何科目か解き始めています。英語のリーディングを解き、解説をしてゆきたいと思います。ちなみに、当塾では英語リーディングとリスニングは100点が狙える試験であることを説き、実際に数名の生徒は100点満点を目標に臨みました。当塾での最高点が94点でした。これで十分な得点なのですが、本人は満点でないことを悔しがっていました。 私が問題を解くにあたり、WPM(= words per minute、1分間で何単語読めるか、の指標)を意識してみました。(当欄の2/2,3,4にWPMについて掲載あり。参照ください。)共テでは、150WPMは確保したほうがよい、との記事を見たことがあり、私の読みの速度が不十分であることが分かったからです。 なお、「共テを解く」のシリーズの掲載を2024年9月あたりからやっておりますので、まずは自分で解いてみて、解き直し時に、私の解説を参照していただけると幸いです。少しは役立つかもしれません。 さあ、本日からは、2025年度英語リーディングを一緒に解いてゆきましょう。満点目指して! -
2025.02.27
合格報告!(2/27 11:00 時点)
■上智大学 外国語学部 ロシア語学科 合格! ■東京理科大学 創域理工学部 数理科学科 合格! ■立教大学 観光学部 交流文化学科 合格! ■学習院大学 法学部 政治学科 合格! ■中央大学 理工学部 数学科 合格! ■中央大学 理工学部 生命科学科 合格! ■法政大学 生命科学部 環境応用科学科 合格! ■東洋大学 国際観光学部 国際観光学科 合格! ■東洋大学 国際学部 国際地域学科 合格! ■東洋大学 生命科学学部 生命科学科 合格! ■成蹊大学 理工学部 データ数理学科 合格! ■芝浦工業大学 工学部 物質化学課程化学・生命工学コース 合格! ■工学院大学 先進工学部 生命科学科 合格! ■日本獣医生命科学大学 獣医学部 獣医保健看護学科 合格! ■麻布大学 生命・環境科学部 環境科学科 合格! トライプラス国分寺駅北口校の生徒の2025年度入試の合格実績を報告しております。 おめでとうございます! 2/27(木)11:00までにご報告をいただいた合格実績を掲載。 -
2025.02.26
合格報告!(2/26 11:00 時点)
■上智大学 外国語学部 ロシア語学科 合格! ■東京理科大学 創域理工学部 数理科学科 合格! ■立教大学 観光学部 交流文化学科 合格! ■学習院大学 法学部 政治学科 合格! ■中央大学 理工学部 生命科学科 合格! ■法政大学 生命科学部 環境応用科学科 合格! ■東洋大学 国際観光学部 国際観光学科 合格! ■東洋大学 国際学部 国際地域学科 合格! ■東洋大学 生命科学学部 生命科学科 合格! ■成蹊大学 理工学部 データ数理学科 合格! ■芝浦工業大学 工学部 物質化学課程化学・生命工学コース 合格! ■工学院大学 先進工学部 生命科学科 合格! ■日本獣医生命科学大学 獣医学部 獣医保健看護学科 合格! ■麻布大学 生命・環境科学部 環境科学科 合格! トライプラス国分寺駅北口校の生徒の2025年度入試の合格実績を報告しております。 おめでとうございます! 2/26(水)11:00までにご報告をいただいた合格実績を掲載。 -
2025.02.21
合格報告!(2/21 13:00時点)
■上智大学 外国語学部 ロシア語学科 合格! ■東京理科大学 創域理工学部 数理科学科 合格! ■立教大学 観光学部 交流文化学科 合格! ■学習院大学 法学部 政治学科 合格! ■法政大学 生命科学部 環境応用科学科 合格! ■東洋大学 国際観光学部 国際観光学科 合格! ■東洋大学 国際学部 国際地域学科 合格! ■東洋大学 生命科学学部 生命科学科 合格! ■成蹊大学 理工学部 データ数理学科 合格! ■芝浦工業大学 工学部 物質化学課程化学・生命工学コース 合格! ■工学院大学 先進工学部 生命科学科 合格! ■日本獣医生命科学大学 獣医学部 獣医保健看護学科 合格! ■麻布大学 生命・環境科学部 環境科学科 合格! トライプラス国分寺駅北口校の生徒の2025年度入試の合格実績を報告しております。 おめでとうございます! 2/21(金)13:00までにご報告をいただいた合格実績を掲載。 -
2025.02.21
合格報告!(2/21 11:00時点)
■上智大学 外国語学部 ロシア語学科 合格! ■東京理科大学 創域理工学部 数理科学科 合格! ■立教大学 観光学部 交流文化学科 合格! ■学習院大学 法学部 政治学科 合格! ■東洋大学 国際観光学部 国際観光学科 合格! ■東洋大学 国際学部 国際地域学科 合格! ■東洋大学 生命科学学部 生命科学科 合格! ■成蹊大学 理工学部 データ数理学科 合格! ■芝浦工業大学 工学部 物質化学課程化学・生命工学コース 合格! ■工学院大学 先進工学部 生命科学科! ■日本獣医生命科学大学 獣医学部 獣医保健看護学科 合格! ■麻布大学 生命・環境科学部 環境科学科 合格! トライプラス国分寺駅北口校の生徒の2025年度入試の合格実績を報告しております。 おめでとうございます! 2/21(金)11:00までにご報告をいただいた合格実績を掲載。 -
2025.02.20
合格報告!(2/20正午時点)
■上智大学 外国語学部 ロシア語学科 合格! ■立教大学 観光学部 交流文化学科 合格! ■学習院大学 法学部 政治学科 合格! ■東洋大学 国際観光学部 国際観光学科 合格! ■東洋大学 国際学部 国際地域学科 合格! ■東洋大学 生命科学学部 生命科学科 合格! ■成蹊大学 理工学部 データ数理学科 合格! ■芝浦工業大学 工学部 物質化学課程化学・生命工学コース 合格! ■工学院大学 先進工学部 生命科学科! ■日本獣医科学大学 獣医学部 獣医保健看護学科 合格! ■麻布大学 生命・環境科学部 環境科学科 合格! トライプラス国分寺駅北口校の生徒の2025年度入試の合格実績を報告しております。 おめでとうございます! 2/20(木)正午までにご報告をいただいた合格実績を掲載。 -
2025.02.19
合格報告!(2/19 正午時点)
■上智大学 外国語学部 ロシア語学科 合格! ■立教大学 観光学部 交流文化学科 合格! ■学習院大学 法学部 政治学科 合格! ■東洋大学 国際観光学部 国際観光学科 合格! ■東洋大学 国際学部 国際地域学科 合格! ■成蹊大学 理工学部 データ数理学科 合格! ■芝浦工業大学 工学部 物質化学課程化学・生命工学コース 合格! ■工学院大学 先進工学部 生命科学科! ■日本獣医科学大学 獣医学部 獣医保健看護学科 合格! ■麻布大学 生命・環境科学部 環境科学科 合格! トライプラス国分寺駅北口校の生徒の2025年度入試の合格実績を報告しております。 おめでとうございます! 2/19(水)正午までにご報告をいただいた合格実績を掲載。 -
2025.02.18
合格報告!(2/18正午時点)
■立教大学 観光学部 交流文化学科 合格! ■東洋大学 国際観光学部 国際観光学科 合格! ■東洋大学 国際学部 国際地域学科 合格! ■成蹊大学 理工学部 データ数理学科 合格! ■芝浦工業大学 工学部 物質化学課程化学・生命工学コース 合格! ■工学院大学 先進工学部 生命科学科! ■日本獣医科学大学 獣医学部 獣医保健看護学科 合格! ■麻布大学 生命・環境科学部 環境科学科 合格! トライプラス国分寺駅北口校の生徒の2025年度入試の合格実績を報告しております。 おめでとうございます! 2/18(火)正午までにご報告をいただいた合格実績を掲載。 -
2025.02.17
合格報告!(2/17正午時点)
■立教大学 観光学部 交流文化学科 合格! ■東洋大学 国際学部 国際地域学科 合格! ■成蹊大学 理工学部 データ数理学科 合格! ■芝浦工業大学 工学部 物質化学課程化学・生命工学コース 合格! ■工学院大学 先進工学部 生命科学科! ■日本獣医科学大学 獣医学部 獣医保健看護学科 合格! ■麻布大学 生命・環境科学部 環境科学科 合格! トライプラス国分寺駅北口校の生徒の2025年度入試の合格実績を報告しております。 おめでとうございます! 2/17(月)正午までにご報告をいただいた合格実績を掲載。 -
2025.02.16
大学受験の準備(8)
大学受験の準備を、ある大学を例にお話ししてきましたが、これまで述べたことは、「入試情報」に書いてあることを参照したものでした。ある大学の2025年度の入試に向けたものです。ホームページからダウンロードして印刷しました。私が閲覧したのは7月くらいでしたが、春先には出されているのではないかと思います。受験するにあたっては、「入学試験要項」にさらに詳細な情報があり、必ず、これをもとに出願、受験しなくてはなりません。この大学は、これを9月に公開していました。大学によっては、11月と、かなりぎりぎりまで出さない大学もあります。よって、前年度のものを2年生のうちから見ておいたほうがよいでしょう。よい、というよりもそうすべきのように思います。トライプラス国分寺駅北口校では、三者面談のときに、志望校の入試情報や入試要項を印刷してお渡しするようにしています。 -
2025.02.15
合格報告! (2/15正午時点)
■立教大学 観光学部 交流文化学科 合格! ■成蹊大学 理工学部 データ数理学科 合格! ■芝浦工業大学 工学部 物質化学課程化学・生命工学コース 合格! ■工学院大学 先進工学部 生命科学科! ■日本獣医科学大学 獣医学部 獣医保健看護学科 合格! ■麻布大学 生命・環境科学部 環境科学科 合格! トライプラス国分寺駅北口校の生徒の2025年度入試の合格実績を報告しております。 おめでとうございます! 2/15(土)正午までにご報告をいただいた合格実績を掲載。 -
2025.02.15
大学受験の準備(7)
大学受験で最も大事なこと、合格点を取ることです。それに直結する、受験準備において最も重要なことは、受験科目とその配点を早くから把握しておくことかと思います。オープンキャンパスに行くことが必要以上に重要視されているように思えてなりませんが、私には疑問です。オープンキャンパスに行かなくては合格を出さない、という大学はないように思います。(推薦入試は別かもしれません。) さて、他にも、きちんと調べなくてはならないことはたくさんあります。1つしか受験しない生徒はあまりいないように思います。複数の大学、学部、学科の受験が一般的であるように思います。その場合、自身の受験日程や手続きの一覧表を作っておいたほうがよいでしょう。高校で用意して生徒に渡して書かせることが多いようです。ただ、学校から用意する場合、10月~11月と、かなりぎりぎりのようですので、早くから自身で準備しておいたほうがよいと思います。この作業、以外にしんどいものです。時間も多く取られるはずです。だから、早くから準備しておいたほうがよいのです。 -
2025.02.14
大学受験の準備(6)
私大受験の共テ利用・一般入試では、受験科目とその配点を把握しておくことも大事です。前掲のある大学の入学情報を見ますと、いろいろな種類があります。どんなのがあるのかみて見ます。共テ利用でも同様ですが、一般入試での種類を見ておきます。法学部を例に。 4教科型と3教科型があります。4教科型は均等配点の1種類ですが、3教科型は、以下のような方式があります。 ・均等配点 ・国語重視 ・最高得点重視 ・英語重視 ・ベスト2均等配点 これらが、入試日、学科と試験科目のマトリックス表に記載されております。スマホでスクロールして見るのは大変かと思います。印刷したほうがよいでしょう。A4サイズでは、小さすぎて見づらいでしょう。A3サイズで印刷したほうがよいです。科目も注意が必要です。国語は、漢文を除く、とあります。大学によって、古文、漢文両方、古文だけ、現文だけ、というのもありますので、しっかり今のうちから知っておき、学習計画に役立てるべきでしょう。ちなみに、上記は、英語外部試験も利用できます。その場合は、当日2科目だけでよいのですね。あ、ベスト2均等配点なら、1科目でよいのでしょうか?どこに書いてあるのか探せません。 -
2025.02.13
大学受験の準備(5)
ある大学の「一般選抜」の「共通テスト利用」と「一般入試」の「併願」について、入試情報に掲載してある例を示しておきます。 併願例<国公立大学との併願、法学部志望、英語外部試験資格を取得している受験生> ・法学部法律学科 大学入学共通テスト 前期5科目均等配点 ・法学部企業法学科 大学入学共通テスト 前期5科目均等配点 ・法学部法律学科 大学入学共通テスト 前期4科目英語重視 ・法学部企業法学科 大学入学共通テスト 後期3科目最高得点重視 (2出願までは一律20,000円/3出願目以降1出願につき10,000円) ・2/8 法学部法律学科 一般入試 一般前期3教科 最高得点重視型 ・2/8 法学部企業法学科 一般入試 一般前期4教科 均等配点 ・2/9 法学部法律学科 一般入試 一般前期4教科 均等配点 ・2/9 法学部企業法学科 一般入試 一般前期3教科 英語重視 ・2/9 法学部企業法学科 一般入試 一般前期3教科 最高得点重視2回目 (同一試験日2出願までは一律35,000円/同一試験日3出願目以降、1出願につき20,000円) 併願割引が入って、上記合計140,000円です。このような受験生もいるでしょう。 -
2025.02.12
合格報告!(2/12 AM時点)
■成蹊大学 理工学部 データ数理学科 合格! ■芝浦工業大学 工学部 物質化学課程化学・生命工学コース 合格! ■工学院大学 先進工学部 生命科学科 合格! ■日本獣医科学大学 獣医学部 獣医保健看護学科 合格! トライプラス国分寺駅北口校の生徒の2025年度入試の合格実績を報告しております。 おめでとうございます! 2/12(月)AMまでにご報告をいただいた合格実績を掲載。 -
2025.02.12
大学受験の準備(4)
次に同じ大学での「一般選抜」を見てゆきましょう。 ・大学入学共通テスト利用入試 ・一般入試 ・多面的評価入試 ・実技入試 この大学は、4種類あります。目を通してひとつひとつ理解してゆくのが大変かと思います。一般入試と共通テスト利用には「英語外部試験の利用」も含まれています。英検、GTEC、TEAP、IELTSが対象です。例えば、英検準1級でスコアが2304以上だと、英語を200点換算してもらえるようです。 「併願」についても書かれています。いろんなパターンがあります。例えば、「同一学部・学科で試験日の異なる併願」があります。受験料は多くかかりますが、たくさん受験できますから、合格可能性が広がるように思います。 -
2025.02.11
大学受験の準備(3)
2/9にお伝えしたことの続きです。少し詳しくみてゆきましょう。 推薦入試にどのような種類があるのかを、ある大学を例に見てゆきましょう。 総合型選抜は推薦入試にここでは含めます。 【総合型選抜・学校推薦型選抜】 ■総合型選抜・学校推薦型選抜(公募制) ・AO型推薦入試 専願のみ ・自己推薦入試 専願のみ ・学校推薦入試 総合評価型 専願のみ ・「独立自活」支援推薦入試 専願のみ ・学校推薦入試基礎学力テスト型 併願可能 ■その他の学校推薦入試について ・指定校推薦入試 ・附属高等学校推薦入試・協定校推薦入試 ・運動部優秀選手推薦入試 他、「特別入試等」もあります。留学生、社会人、転入の入試です。 これらは、「一般入試」とは異なり、高校での学校の成績、小論文、面接、プレゼンテーションなどで合否判断をされ、また、「年内入試」と呼ばれているよう、年内、秋から冬にかけて入試、合格発表がなされます。この形態での受験をするならば、高校1年生のうちから、学校の成績をしっかり取っておかなくてはなりません。いろいろあって分かりにくそうですが、どの大学でもよいので、一度しっかり読むと、以外と簡単に理解できると思います。 -
2025.02.10
合格報告!
■成蹊大学 理工学部 データ数理学科 合格! ■芝浦工業大学 工学部 物質化学課程化学・生命工学コース 合格! ■日本獣医科学大学 獣医学部 獣医保健看護学科 合格! トライプラス国分寺駅北口校の生徒の2025年度入試の合格実績を報告しております。 おめでとうございます! 2/10(月)AMまでにご報告をいただいた合格実績を掲載。 -
2025.02.09
大学受験の準備(2)
前掲で大学受験をしてゆくにあたり、以下を早めに把握しておくように、とお伝えしました。 ☑入試形態 ☑受験科目 ☑科目ごとの配点 トライプラス国分寺駅北口校では、興味のある大学のホームページから、「入試情報」と「入試要項」をダウンロードして、印刷して、目を通すことをお願いしています。決して簡単に思わないでください。この大学を受験するのだ、と仮定して目を通してゆくと、かなりの重労働となるはずです。当塾生には、必要なものは印刷をしてお渡ししています。オープンキャンパスで配布されることもありますが、紙媒体のものは一切なく、すべて電子データで公開している大学も多くなってきていますし。 高校3年生には、このような書類を6月~7月初旬の面談で必ず、お渡ししていますが、本格的な受験勉強を開始しているときに、初めて見るようなことでは、重労働なものですから、後回しにしてしまいがち、そして、秋になって、勉強時間を削らなくてはならないくらい、入試要項の理解をしなくてはならないはめになってしまいます。だから、1年生、2年生のうちに目を通して、ある程度の理解をしておくことは必須なのです。 -
2025.02.08
大学受験の準備
トライプラス国分寺駅北口校では、三者面談を定期的に実施しております。高校生には早期から大学受験の準備を始めるようにお願いしています。ここで言う準備とは、学力を上げるための受験勉強をしてゆくことではありません。以下のことを早くから把握しておくように、ということです。 ☑どのような受験形態があるのか? 推薦、一般選抜が主な区分です。これが、さらにそれぞれ細分化されてゆきます。おそるべく細分化していますので、早期にどんなに調べるのが大変なのかを実感しておいた方が間違いはないです。 ☑受験科目は? きちんと調べておかないと、3年生になって、今更間に合わない、ということになりかねません。要注意です。 ☑科目毎の配点は? ある国立大学の2次試験ですが、英語400点・社会100点などという極端な配点も少なくありません。共通テストと2次試験の比率も様々です。少し余談になりますが、「ここの大学は数学、理科は9割以上得点できるので、英語は3割取れれば、合格できます。」という生徒が当塾におりました。トライプラス国分寺駅北口校では、このような大学受験の準備については、高校1年生の1学期の三者面談でお話しています。 -
2025.02.07
春期講習のカリキュラム提案
トライプラス国分寺駅北口校では、春期講習(3/15~4/8)の期間でのカリキュラム提案を、生徒ひとりひとりに行っています。どのようなことをするのか、すでに確定しているものを、一部ですが、簡単に示します。 ☑高2生A君 英検2級対策 過去問4回分 8コマ ☑高2生A君 物理 映像授業(Try IT!) 1月~4/8まで すべて受講+演習問題プリント 自主学習 ☑高2生A君 数学 共通テスト2回分、私大過去問2回分 12コマ ☑高2生B君 英検2級対策 過去問4回 12コマ ☑高2生C君 英語・数学 共通テスト対策 過去問3回分 20コマ ☑高2生C君 生物 映像授業(Try IT!) 1月~4/8まで すべて受講+演習問題プリント 自主学習 ☑高2生D君 英検準1級対策 10コマ ☑高2生D君 英語・数学・物理 共通テスト・私大過去問 30コマ ☑高1生E君 英検準1級対策 過去問3回分 9コマ ☑高1生E君 数学 共通テスト過去問 3回分 9コマ まだまだいろんなカリキュラムがあります。 -
2025.02.06
トライプラス国分寺駅北口校の三者面談
トライプラス国分寺駅北口校では、生徒、保護者、教室長の三者面談を定期的に実施しています。1月~2月にかけては、1年先を見据えての学習計画を提案したり、一緒に考えていったりしています。そして必ず、目標数値の設定をしてもらうようにしています。昨日は高校1年生と面談し、学年末テストでの校内順位、来年2年生の学年末テストでの校内順位の目標を設定しました。校内順位の他、クラスで1位を目標とする科目も決めました。また、英語検定準1級を6月に受験し、その準備をいつから開始するのかを決めました。もちろん目標は合格すること。勉強もそうですが、クラブ活動も一生懸命やっている生徒です。野球部ですが、自分の打率などの記録はきちんと取っていなかったので、これを記録してゆくことも目標としました。この生徒とは、学年末試験が終わっての3月中旬までに、また三者面談をいたします。校内順位が目標達成できていることを期待しています。野球の記録にも期待しています。卒業までにホームランを1本でも打ってくれるとよいな、と期待しています。 -
2025.02.05
来年度(令和8年度)の入試の準備
トライプラス国分寺駅北口校の高校3年生は、すでに年内入試で合格を決めた生徒もいるのですが、共通テストを終え、国公立大学の2次試験、私立大学の一般入試を受験してゆくことになります。多くの合格実績を出してくれるものと期待できます。 さて、現在の高校1,2年生は、1月中旬から三者面談を実施してきており、受験に対する意識の確認をしています。そして、受験の準備をどうしてゆくべきかを話し合います。一番大事なことは、将来どういうことをしたいかをしっかり考えることかと思います。そのために、どの大学に進学するのがよいかを決め、合格するために必要な学力を身につけてゆくことです。 トライプラス国分寺駅北口校の春期講習では、共通テストや私立入試の過去問を解いてもらい、個別指導の授業で取り扱います。早すぎることはありません。夏休みからで大丈夫と考えていると、本当に時間が足りなくなって、後悔したりすることは多いはずです。 -
2025.02.04
共通テストに必要なWPM(3)
英語のWPMについて、当塾の教師の一人は、250~300くらいだそうですが、「あまり意識しなくてもよいです。」と一言。そんなことをいちいち計測するよりは、毎日、英語の文章を読みまくっておれば、自然に上がってくる、とおっしゃいます。その前提として、最低限の文法力はしっかり身につけておく必要はあるとおっしゃっています。そして、単語の品詞についての理解もしっかりとする必要があると。塾で英語が苦手だという生徒に共通していることは、品詞に対してまったく意識が向いていないことがひとつとして挙げられます。単語が持っている役割ですから、品詞をしっかり理解することは、英文を読むスピードも早くなりますし、英作文の能力も高まるはずです。中学生の教科書には、必ず説明されていますよ。もうひとつあります。発音記号です。高校生でも発音記号がまったく分からない、という生徒が多いのは事実です。覚えようとしなくても、自然と発音記号は理解できますから、意識を向けるとよいです。発音記号はそれを見て発音できればよいので、いちいちこれをノートに書いたりして覚えようとしないことです。見て、音を聞いて確認する、それだけでよいです。 -
2025.02.03
共通テストに必要なWPM(2)
共通テストの英語のリーディングに必要なWPMは、150WPMとのことを紹介いたしました。数値を示されると、自分がどのくらいなのか知りたくなります。これまでの掲載で、私が実施した音読の時間を問題ごとにお伝えしてきていますが、WPMを計測してみたことはありませんでした。2024年度の第6問のBの問題文で計測してみました。758語÷406秒x60 = 112WPMでした。まだまだトレーニングする必要があるのだな、と痛感いたしました。ただ、このスピードで70点~80点は取れるので、私程度のスピードでも何とかなるものだと思ってよいかもしれません。ただし、この数値は、最初に問題を解いたときのものではなく、計測のために再度読み直したときのものなので、初見のときのスピードはもっと遅いはずです。また、112WPMは、くやしいな、と思い、再度計測してみました。120WPMに上がりました。何度も音読の練習をしてゆくと、150WPMに少しずつ近づいてゆくように思えます。私も塾の生徒に負けぬよう、トレーニングを続けようと思います。ちなみに、当塾の英語の教師の一人にお尋ねすると、250~300だそうです。すごい。 -
2025.02.02
共通テストに必要なWPM
共通テストのリーディングは、速読力を必要とされます。 読む速さを評価する指標に「WPM」があります(WPM= words per minute)。1分間で何単語読めるか、の指標で、以下の式で計算します。 WPM=(文章の単語総数)÷(読むのにかかった秒数)x60 共通テストに必要なWPMは、150WPMだそうです。この数値はかなり高いそうです。高校生の平均が75WPMだそうで、実にこの2倍の速度が求められているそうです。150WPMは、以下のようにはじき出されています。 共通テストの語数が約6000語で、試験時間が80分。余裕をもって解答時間を確保するために、読む時間を半分の40分と設定して計算されています。 6000語÷40分で、WPMが150。(6000÷2400x60= 150) ちなみに、ネイティブスピーカーのWPMは200~400だそうです。これが書かれてあった記事では、受験に必要なWPMは120程度と書かれていました。受験生の皆さんも、150WPMを目標にしてトレーニングを積んでゆきましょう。それには、まず、自身のWPMを計測してみることが必要ですね。 -
2025.02.01
2024共テ英語・リーディングの総括
2024年度の共通テストを解き終えて、総括をしておきます。現、高1、高2生に向けたメッセージでもあります。 1. 満点が狙える試験です。是非、今から、満点を狙ったトレーニングを開始してください。 2. 速読力がないと満点は無理です。速読力は短期間で養うことは無理です。今から開始して、夏前あたりの模試で満点を出すようにトレーニングしましょう。 3. 語彙力と文法力の強化も必要です。 ⓵語彙力 市販の単語帳にたよった単語学習は思い切って止めましょう。無駄なだけです。1年からの教科書の単語を徹底的に拾い上げて、辞書を引いて、用例を書き込んだ自身の単語帳を作成してゆくことです。 ②文法力 学校で分厚い文法書を買わされているはずです。何度も繰り返し、全部覚えるつもりで。5周回やってみてください。 4. 3.だけやるのは、速読力はつきません。多読してください。読んだ文章は、必ず1度精読してください。精読した後、音読を50回やってください。文章は山ほどあります。共通テストの過去問を手始めにやってもよいです。 2月から開始してみてください。3月末には、視界が開けたように、びっくりするほど上達しているはずです。 -
2025.01.31
2024共テ英語リーディングを解く-94
設問文にある単語を見ます。 ☑infer 問題を解くときには、意味は無視してもよいでしょう。5番目のスライドに入れるに適した文を入れるだけの問題ですから。設問文はこうです。 What can be inferred about ~?です。前年2023年の第6問のBの問5、全く同じ設問文です。 過去問を解いて、解き直し学習をしっかりやっておくべきなのですね。 過去問の設問でどんな聞き方をしているのか、整理してまとめておくと、解くスピードも少しあがるような気がします。私の宿題として、まとめておこうと思います。塾生には、参考資料としてお渡しできるでしょう。 第6問のBの読み直しをしてみて気が付きましたが、科学分野での専門用語やそれに近い用語が多く出てきているように思いました。単語帳で単語学習をするだけでは足りないように思います。ではどうしてゆくか?多くの文章に触れてゆくことです。そこで語彙数を増やしてゆくのです。科学分野について、皆さんもある程度の知識を持っているはずで、意味を類推しながら読めると思いますが、受験勉強で多く読んで、語彙力を強化しておくと、本番ですらすらと読めるようになるはずです。 -
2025.01.30
2024共テ英語リーディングを解く-93
第6問のB、まだまだ単語チェックが続きます。 ☑microorganism 私は、この単語は初めてでした。organismの単語も調べて見ました。 a microscopic organismと用例がありました。Organ, organic, organization, organize, organizer, 一緒に全部覚えましょう。 ☑multiply ☑property ☑food-borne 問題文では、food-borne illuness とあります。borne、これの原型と意味は大丈夫ですね。 ☑tolerant 1/27にtolerate を掲載しています。 ☑upset 以外と難しい単語のように思います。第7段落中にありますが、同じような用例が辞書にありました。 ☑diarrhea また、見たこともない単語が。文から類推できるように思います。 ☑numb これも見たことがないです。問題文にはnumb hands とあり、また前後から体の不調のことが書かれてあるので、意味の想像はつきます。 -
2025.01.29
2024共テ英語リーディングを解く-92
第6問のB、単語チェックを続けます。 ☑temporarily イギリス英語が異なっていることも学習しておきましょう。形容詞のtemporaryとcontemporaryも合わせて。後者には名詞もありますよ。 ☑metabolism メタボ、学生の皆さんでもよく聞く言葉ですよね。私たちがよく使う「メタボ」は、metabolic syndrome のことです。問題文を読めば、意味がつかめるはずです。3枚目のスライドにもこの単語が出ており、問2に直接つながっています。「太ること」と勘違いしてしまうと、不正解になる可能性があるので、この際、しっかり、日本語の意味を覚えておいたほうが良いでしょう。 ☑reduce ☑appetite 私は、この単語は大学生になってからは、完全に記憶に定着しました。appetizerという単語を覚えたからです。「食前酒」という意味だからです。 ☑ingredient いやいや難しい単語ですね。問題文を読みながらだと、意味を知っていなくても、すぐに出てくるはずです。 ☑It is also believed that ~(12/18に同じ形について記載していますね。) -
2025.01.28
2024共テ英語リーディングを解く-91
第6問のB、まだまだ単語チェックが続きます。 ☑vaporize 辞書の例文で覚えてゆくとイメージがわき、覚えやすいと思います。問題文を示しておきます。 The compounds in wasabi vaporize easily, delivering a blast of spiciness to our nose when we eat it. Deliveringを文法的に説明できるようにしっかり文法のテキストで学んでおいた方が 良いです。 ☑blast 上記の文中にありますね。 ☑conduct 問題文中では動詞で、過去分詞形で使われています。動詞と名詞でアクセントが変わってくることは大丈夫ですね。conductor という名詞の意味も大丈夫ですね。 ☑cease 発音は大丈夫ですね。音読をするには、正しい発音でしないと意味がありませんよ。リスニングテストもあるわけですから、正しい発音を覚えておくことは大事です。きれいな発音ではないですからね。ネイティブのような発音は大学入試や英語検定では要求されません。正しい発音が要求されます。 ☑exposure 写真部の生徒はこの単語は楽勝ですね。 -
2025.01.27
2024共テ英語リーディングを解く-90
前掲、単語のつづき。 ☑induce 意味がわからなくても、文意はつかめると思います。 ☑range 2段落目の7行目は名詞、特に10行目は動詞で使用されていることが瞬時に把握できることが大事ですね。 ☑tolerate 大学入試では共テ以外でも頻出です。名詞形、形容詞形も合わせて覚えましょう。名詞形は2種類あります。設問の問4(スライドの5番目)に名詞形が出ています。この単語が出ている文を抜き出しておきます。 The reason some people cannot tolerate chili spice but can eat foods flavored with wasabi is that the spice compounds in it are low in density. この文の主語、動詞、そして第何文型なのかが分かるでしょうか。もし分からなければ、高校1年からの文法を学び直す必要があると思ってください。文法がしっかり理解できている生徒は、速読力も上がるはずです。そうでないと、いくら読んでも、速読力は上がりませんから、これだけは注意しておくべきです。
- 1理解できるまでお子さまと向き合う個別指導スタイル
- 2生徒の気持ちを理解できる講師と出会える担任制
- 3自分のペースで学習できるオーダーメイドカリキュラム
- 4お子さまの理解度・到達度が分かる学習プログラム
- 5授業のない日も自由に自習できる演習エリア
- 6繰り返し見る事の出来る映像授業の「Try IT」
- 7単元別学習・苦手克服が出来る演習プリント/オリジナル教材
-
お問い合わせまずはお電話でお問い合わせください。
-
無料
体験授業無料で体験授業を受けていただけます。トライプラスの指導効果を実感してください。 -
学習状況
の確認お子さまの目標や現在の学力を確認し、学習プランをご提案します。 -
ご入会トライプラスでの指導法や学習プランにご納得いただけた場合、ご入会のお申込みをお願いします。
-
担任講師
の決定お子さまの目標や受講科目、そして性格まで配慮した上で最適な担任講師を選定します。